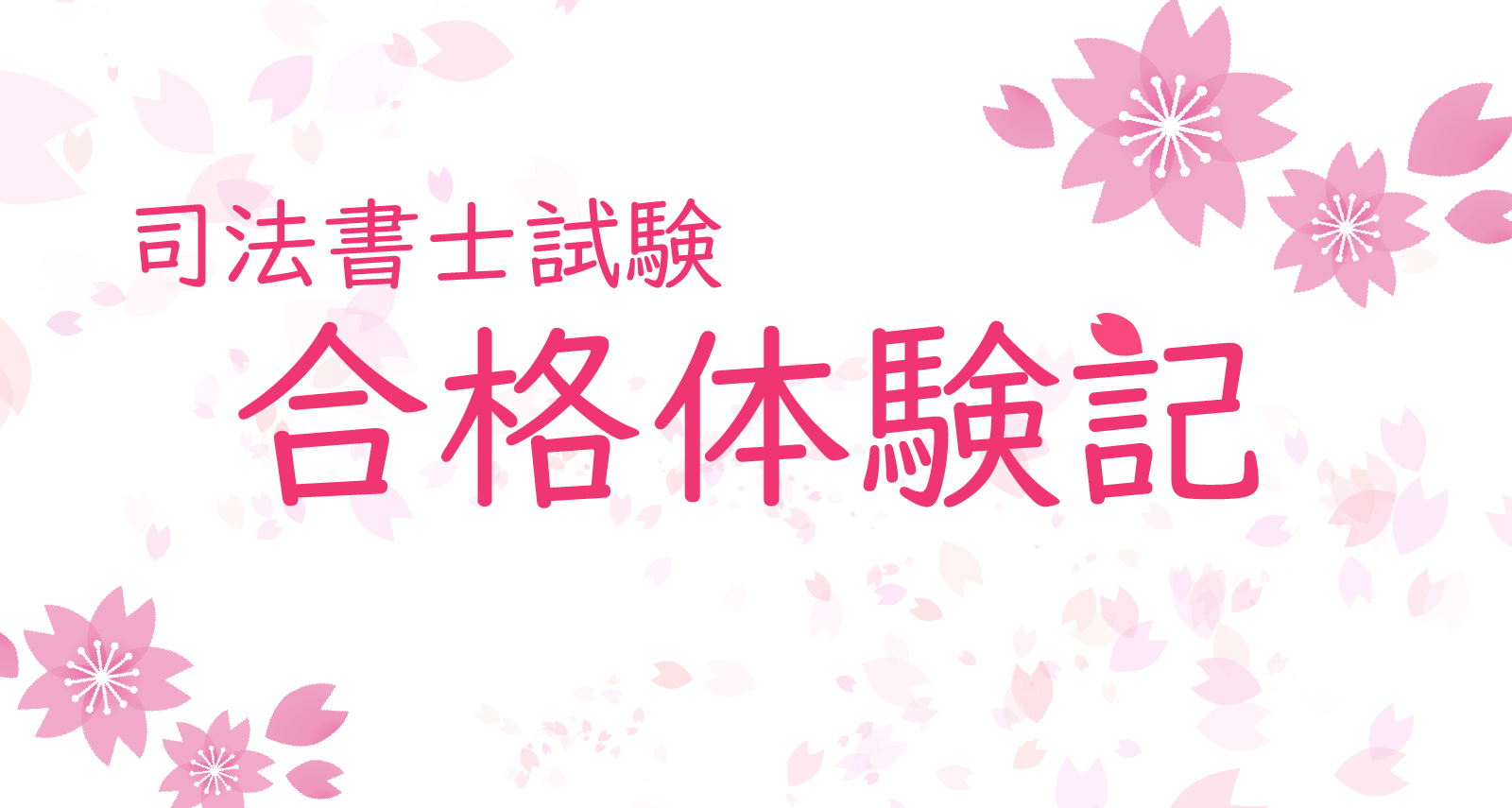S.Yさん
過去問攻略パーフェクトコース
なぜ司法書士資格を目指したか
新卒で金融関係の会社に入社し、営業職として働いていたときに、上司や先輩から「専門性を持ちなさい」と指導されたことがずっと心に残っていました。
結婚と転居を機に会社を退職し、子どもが幼稚園に入ったのをきっかけに、まずは宅建士、次に行政書士資格を順に取得しました。行政書士試験で自分に課していた得点目標を達成できたため、大学生の頃から憧れていた司法書士試験に挑戦することを決めました。
予備校選びのポイント(クレアールを選んだ理由)
行政書士の学習を通して「条文を重視することの大切さ」を痛感していたため、クレアールの『択一六法』に強い魅力を感じました。 また、受講費用が比較的リーズナブルである点も大きな決め手となりました。
クレアールで学んで良かった点
講義は無駄がなく非常にわかりやすく、答練や模試も「多すぎず・難しすぎず・ちょうど良い」バランスでした。また、模試が5月末に終了するため、直前期の1か月間を自分のペースで調整できた点も良かったです。
CROSS STUDYの活用法
⒜ 利用タイミング
1単元が終わるごとに、カテゴリ順でCROSS STUDYを進めていました。
⒝ 学習時期ごとの使い方
3月頃までは単元ごとに使用し、直前期には苦手分野(重要度★4・★5の単元)を中心に繰り返しました。
⒞ 機能の活用法
重要度設定は、⒞年度の合格体験記を参考に自分の理解度に応じて次のように分類していました。
- 間違えた+理解度低い → ★5
- 正解したが理解度低い → ★4
- 普通 → ★3
- 概ね理解 → ★2
- 復習不要 → ★1
また、キーワード検索機能を使い、例えば会社法では「責任」、不動産登記法では「前提」「単独」、民事訴訟法では「不服」など苦手ワードを含む問題を抽出して集中的に演習しました。
⒟ 紙の問題集との使い分け
択一式の過去問演習にはCROSS STUDYのみを使用し、紙の過去問題集は使いませんでした。
CROSS STUDYによって、子どもを寝かしつけた後の布団の中や、習い事の待ち時間など、ほんの隙間時間でも演習できたのが大変助かりました。
また、CROSS STUDYを解いていく上で不明点があったとき、すぐにスマホやタブレット上でPDF版の『択一六法』や『合格書式マニュアル』を参照できる点も非常に便利でした。
「CROSS STUDYとPDF教材がなければ、私は合格できなかった」と言っても過言ではありません。
学習全般
学習のポイント・心構え
わからない点に深入りしすぎず、まずは一通り全範囲を回すことを意識しました。試験範囲は広いですが、よく言われている通り出題は基本事項が中心です。枝葉末節にこだわるよりも、原則や立法趣旨を意識した学習を心がけると得点が伸びやすいと思います。
学習スケジュール
基本的には「科目別ベーシック答練 択一式編」の解答締切に合わせて復習し、CROSS STUDYを解いていました。学習期間の全期間を通じて基本的に答練と模試の締切は厳守していました。市販のまとめ本も活用し、間違えた箇所や重要事項は直接まとめ本に書き込んでいました。
直前期(4月頃〜)は、「実力完成総合答練」の実施と復習・まとめ本の回転・CROSS STUDYによる苦手分野演習を軸に学習しました。
子どもの体調不良などで、突然時間が取れなくなることも多かったため、週に2日は「予備日」としてスケジュールに余裕を持たせていました。予定どおりに学習が進んだときは、予備日をCROSS STUDYによる苦手分野演習にあてました。
効果的な学習方法(科目別・記述式対策など)
不動産登記法の択一式の過去問を解く際には申請書をイメージして取り組みました。不明点はすぐ『合格書式マニュアル』を参照することで、記述式の対策にもつながったと思います。
記述式の学習初期には『合格書式マニュアル対応問題集』をやり込み、ひな形の基礎を固めました。
その後、『記述式ハイパートレーニング問題集』を繰り返すことで、実戦対応力を高めることができました。
午後の部(記述式)の時間配分と工夫
答案構成用紙の利用を最低限にすれば、記述式のスピードアップが図れると考えていたので、『記述式ハイパートレーニング』や答練で記述式を解くときに、どこまで答案構成用紙を使わないで正しく解けるか意識して、探りながら解いていました。
私の場合は不動産登記記述式ではほぼ使わず、商業登記記述式は役員変更関連と決算期の変更と募集株式発行等の株式の計算に答案構成用紙を使っていました。商業登記記述式では答案構成用紙の利用をあまり削れませんでしたが、おそらく各々得意不得意があると思うので、こういう点でも答練を活用して探っていくのが良いと思います。 色々と工夫したものの、本試験では択一式:60分、記述式(不動産登記):50分、記述式(商業登記):70分で解答、見直し時間はわずか2〜3分しかなくギリギリでした。
試験中の工夫と解答順
午前の部・午後の部ともに問題順にそのまま解答しました。順番を変えることでマークミスや記載欄の混乱が生じるのを避けるためです。記述式では赤青鉛筆で問題文の重要箇所(間違いやすいポイント)をチェック。赤青鉛筆はマーカーと違いキャップの開け閉めが不要で時間短縮にもなりました。
午後の部の問題を試験時間内に解答するためのコツ
午後の部のスピードアップには、択一式も記述式も迷いなく解答できる問題を増やすことが大事だと思います。
択一式については過去問(CROSS STUDY)の重要度★4および★5の問題の繰り返しを行い、必要に応じて『択一六法』等に戻り苦手分野をひとつひとつ潰していきました。5肢択一形式の問題を解く際は、軸肢検討か全肢検討かについてはどちらかにこだわらず、確実に自信があるものは軸肢検討、少しでも不安なものは全肢検討をしていました。この匙加減も、答練で意識して調整していました。
記述式については勉強できる時間が限られていたため、ひな形の習得と『記述式ハイパートレーニング』の繰り返しに絞っていました。対策を絞ったことで『記述式ハイパートレーニング』の問題については即答レベルまで仕上げることができました。
また、答練において不動産登記の前提となる登記の要否や申請形態(単独申請なのか共同申請なのか)に迷って時間を使ってしまうことがあったので、直前期に、CROSS STUDYで「前提」や「単独」をクロスワードとして、不動産登記法の択一式過去問を検索し、該当の肢を再確認しました。
昨年出産してから机に座って勉強できる時間が極めて限られていたため、今年度はフルサイズの問題は答練と模試しか取り組めませんでしたが、学習範囲を絞ったことでかえって知識の精度が増し、スピードアップが図れたと思います。
実は直前期には「記述式は机に座って色々な問題を多く解く時間がないと厳しいかもしれない…」という不安があったのですが、寝かしつけ後の布団の中や家事育児のほんのちょっとした時間に、『記述式ハイパートレーニング』や『合格書式マニュアル』のPDFをスマホやタブレットで繰り返し参照すること、CROSS STUDYでの不動産登記法・会社法・商業登記法の択一式対策時に『合格書式マニュアル』を頻繁に参照することで力を伸ばすことができました。
苦手分野の克服について
CROSS STUDYで何度も間違える問題や解説部分の図表のスクリーンショットを撮り、スマホやタブレットのメモ機能に張り付け、隙間時間に確認するようにしていました。
また、特に理解が足りないと感じた分野の復習の際には、テキストの記載を、普段子供や友人と話すときに使うような平易な言葉に直して、頭の中で自分に説明するようにしていました。
平易な言葉にうまく直せないときは簡単な図や表にして(走り書きメモ程度)、しばらく持ち歩いて隙間時間に見て理解に努めました。
答練・模試の活用
令和7年度の学習では、赤ちゃんをおんぶしながら答練・模試を解くしかなく、3時間通して取り組むことが難しい状況でした。代わりにタイマーで時間を区切り、実戦を意識して取り組みました(午後択一式60分、不動産登記記述式50分・商業登記記述式50分で区切っていました)。苦肉の策でしたが、いつも突然泣き出す赤ちゃんの対応をしながら演習をしていたため、「本試験で何が起きても大丈夫だろう」という自信がつきました。
また、本試験の2週間前には今年度の答練と模試の間違い箇所をすべて見直しました。令和7年の本試験では商業登記記述式で会計監査人の合併や監査等委員会設置会社が出題されましたが、直前に答練を見直していたので迷いなく解答することができました。
モチベーション管理・リフレッシュ方法
約3年7か月の学習期間の中で、子どもの卒園・入学や第二子の出産を経たこともあり、「挫折を感じる暇もなかった」というのが本音です。日々の答練や模試の期限に追われる中で、些細な達成でも「自分を褒める」ことを意識していました。前向きな気持ちを保つことが何より大切だと思います。
家事・育児との両立
早朝や子どものお昼寝時間を活用して学習していました。睡眠不足は効率を下げるため、睡眠時間は6時間以上確保していました。
また、家事をしながら講義を聞いたり、思い出し学習をしたり、覚えにくい内容は紙に書いてトイレやキッチンに貼って反復していました。
合格の決め手(総括)
今年度は勉強時間があまり取れない中での受験でしたが、「今可能な範囲で精一杯対策をし、自分の力を出し切るまでだ!」と覚悟を決めて臨んだことが大きかったと思います。
記述式に割ける時間が少なかった分、択一式で上乗せ点を狙う戦略を立て、直前期に重点的に取り組みました。
また、常にいつ泣き出すかわからない赤ちゃんが横にいる状態で勉強していたため、本番ではむしろリラックスして受験できたことも勝因の一つです。
受験生へのメッセージ
司法書士試験の対策で大事なことは「捨て科目と極端な苦手分野を作らず、全範囲の基本事項を網羅すること」だと思います。
私のように直前期に長時間勉強できなくても、数年かけてコツコツ知識を積み上げていけば、合格に近づくことが可能だと思います。自分を信じて、前向きに頑張ってください。