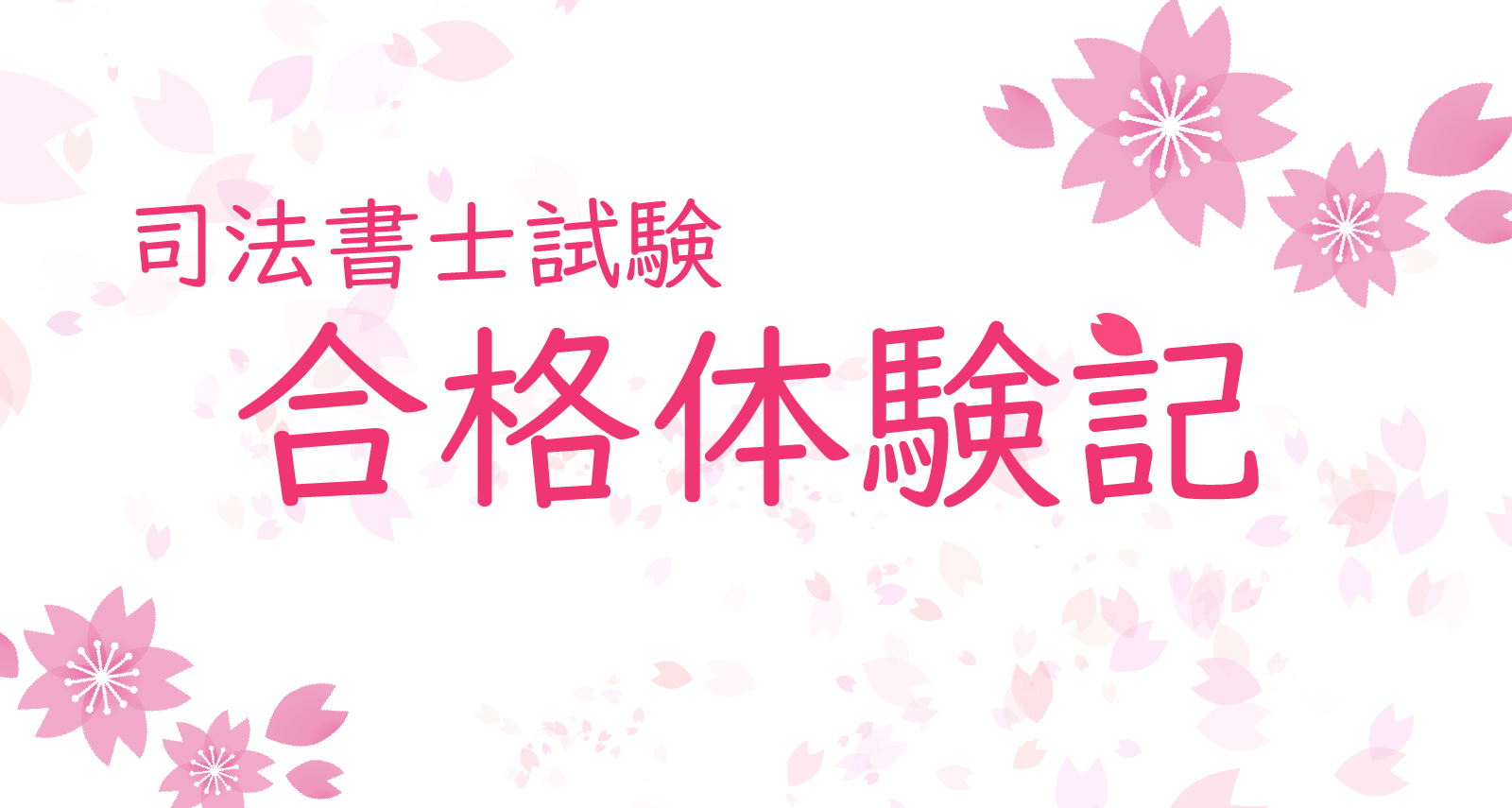C.Yさん
受講コース:中上級パーフェクトBコース
なぜ司法書士を目指したか
仕事で他士業の先生と関わる機会があり、女性の士業に憧れを抱くようになりました。
ちょうど仕事にも飽きを感じ、定年まで働く想像ができなくなっている頃でした。士業だと、定年も関係なく働けるし、子育てなどでキャリアがストップしても比較的復職しやすいので、何か国家資格を取ろうかと考えていました。
そして士業について調べていくうちに、成年後見や空き家対策など社会貢献にも繋がる仕事ができる司法書士を目指そうと思いました。 家族に相談すると、きっと向いていると応援してくれ、1~2年で絶対に合格すると決め、試験の1年前に仕事を辞め勉強に専念することにしました。
なぜクレアールを選んだか
知り合いが大手予備校を受講して司法書士試験に合格していたこともあり、1年目は大手予備校の初級講座を受講しました。1年半のコースを1年切ったところからスタートしたため、1年目は講義を受けるだけで精一杯。過去問も記述式対策もまともにできないまま、午前の部・午後の部ともに基準点以下という結果でした。
2年目は大手予備校の教材を引き続き使いながら、択一式、記述式ともに過去問演習ばかりしていました。そのおかげで、記述式は8~9割とれるようになっていましたが、午前の部は基準点を超えたものの、午後の部が基準点に届かず、またも不合格でした。
2年目で落ちた時は、自身も家族もとても落ち込み、もう撤退するか迷いましたが、やはり諦めきれませんでした。合格まであと少しのところまで来ている手ごたえがあったからです。
2年目の敗因は自分でも分かっていて、過去問を解いた後、テキストに戻って学習していなかったことです。というのも、大手予備校のテキストが内容は充実しているのですが、とても分厚いうえに重たく、正直なところ持ち歩くのが面倒だったのです。そこで過去問を細断して勉強していましたが、過去問の答えを覚えた状態になっただけで、法律の知識を体系的に身に付けられていませんでした。
そこで、2年目の本試験の帰りに色々な予備校から配られたパンフレットが家にあったので見返したところ、クレアールは『択一六法』というコンパクトな教材を使っていること、スマホで使える「CROSS STUDY」という問題演習システムがあること、費用もお手頃だったことから、クレアールの「中上級パーフェクトBコース」を受講することに決めました。
結果としてクレアールを受講して1年で合格できましたが、2年目も引き続き受講することのできる安心保証プランがあったのも精神衛生上、非常に良かったです。
学習の進め方
3年目は貯金が少なくなっていたこともあり、月80時間以内のアルバイト勤務と兼業で学習することにしました。また、これ以上実家にお世話になるのも申し訳なかったので、一人暮らしも始めました。
クレアールは最初に、教材と同時に「学習計画表・配信予定表」を送ってくださるので、それを活用しながら、必ずスケジュール通りに、答練などは締め切りまでに、必ずやりきるよう徹底しました。ここが1年目とは違うところです。アルバイトをすることにより、可処分勉強時間が減ったことで、かえって勉強により集中して臨めるようになりました。
令和6年9月~令和7年2月頃の学習
基本的には「【中級】択一六法マスター講義」を受講→その範囲の過去問を解く→『択一六法』を通読、という流れでやっていました。「科目別ベーシック答練 択一式編」を解いた後は、必ず『択一六法』を通読していました。 CROSS STUDYは、講義で聴き終わったところを順番に一通り解きました。通勤時間や昼休みなどを活用してやっていました。
令和7年3月~5月頃の学習
過去問→『択一六法』を通読→「実力完成総合答練」→『択一六法』を通読のようにすでに解いた問題を何度も解き直しながら、『択一六法』も何度も読んでいました。これを2~3週間かけて全科目行っていました。この頃から、CROSS STUDYを毎日200~300問、全科目をランダムで解くようにしていました。ランダムに解くと、脳が活性化される気がするのでおすすめです。
記述式については、学習2年目の令和6年4月~6月に毎日過去問を1問ずつ解いていたら自然とできるようになっていました。そこで、学習3年目の令和7年は特段新しいことはせず、毎日1問ずつ模試や答練の問題を何度も解くようにしていました。時間短縮のため、略字や略語などを使い、1問30分以内で解くようにしていました(略字や略語を使いすぎると、正しい漢字や正式名称を思い出せなくなるのであまりお勧めしません)。間違えた箇所だけ、「記述式間違いまとめノート」を作っていました。
令和7年6月の学習
最後の1か月はアルバイトをお休みし、毎日10時間以上勉強していました。正直過酷過ぎて何をしていたかあまり記憶にありませんが、間違えた問題を解き直したり『択一六法』を通読していました。あえて難しい問題は深入りしないようにしていました。
CROSS STUDYは間違えた問題や苦手な分野を中心に毎日200~300問ランダムで解くようにしていました。記述式は解くのに時間がかかるので、問題演習はあまりせず、間違いノートを見返す程度でした(直前期の記述式を解く時は、きれいな字で正式名称を書いて解いていました)。
試験日当日
1、2年目は自分で運転して試験会場まで行っていましたが、3年目は試験のこと以外考えたくなかったので、家族に送り迎えしてもらいました。甘えられるときは、周囲に頼ってもいいと思います。
受験番号も1年目、2年目共に二桁番号でしたが、「番号が早くなればなるほど合格率が上がる」と風のうわさで聞いていたので、3年目は願書受付当日の朝一番に法務局に行き出願し、一桁番号を手に入れました。
試験日も緊張していましたが、受験票に書かれた受験番号を見ては、「こんなに早い番号なのだから間違いなく今年は受かる!」と自分に言い聞かせて心を落ち着かせていました。こういったお守りやゲン担ぎも意外と効いたなと思います。
苦手分野の克服方法
学習2年目で受験した令和6年度本試験で、午後の部択一式が基準点に届かず、その原因が不動産登記法で多く失点していたことでした。正直苦手だったので、仕方ない結果だったのですが、とても悔しく、3年目は絶対落とさないと誓いました。
対策として取り組んだのは、『択一六法』の読み込みと過去問演習のみです。これがよかったのか、令和7年度本試験では、不動産登記法の択一式は全問正解できました。私みたいに「分厚い問題集は持ち運ぶだけで嫌」という方にとっては、『択一六法』は至高の教材です。『択一六法』を何度も読み込み、内容を理解し覚えれば必ず合格できます。
過去問もPDFでも提供されるので、いつも『択一六法』とiPad、ノートのみで身軽にどこでも勉強できたのがモチベーションの維持、効率的な学習に繋がったと思います。 何十年も前の過去問演習などする必要はなかったと思います。
午後の部の対策
学習2年目時点で記述式は得意になっていたので、一番解きやすい商業登記記述式→不動産登記記述式→択一式の順で解きました。周りが静かに解いている中、記述式を解くのはいいのですが、択一式を解く時に周りが騒がしいのはストレスフルでしたので、この順番はお勧めしません。そこで、順番通りに択一式→記述式(不動産登記、商業登記はどちらが先でも良い)の順で解くのが良いと思います。
午後の部の時間配分ですが、私はいつも択一式45分、記述式50分ずつで解くように時間を計って練習していました。令和7年度の本試験では、択一式45分→不動産登記記述式50分→商業登記記述式55分で解きました。残り時間15分で択一式の見直しをしていたのですが、商業登記記述式が難しかった余韻をずっと引きずって心臓がバクバクしており、まったく文章が頭に入ってきませんでした。
後から商業登記記述式のケアレスミスがあったことに気づいたので、択一式に戻らず、商業登記記述式の見直しをするべきだったなと後悔しました。結果を見ると、令和7年度の記述式の得点は不動産登記66点、商業登記39点でした。
こういった本番での対応は、その時にならないと対応できない部分もありますが、午後の部は、択一式も記述式も時間との勝負なので、最初から時間が余るように戦略を練って、ひたすらに問題演習して頭を慣れさせるしかないと思います。解答に時間がかかるというのは、知識不足、問題演習不足でしかありません。どのようにして時間短縮するかも人それぞれですが、自分に合った解き方を見つけるために、色々な方法を試して、模試などで調整していくのがおすすめです。
令和6年度司法書士試験から記述式の配点が倍になり、記述式が得意な人にとっては合格を狙いやすくなったと思います。私も記述式がとても好きで、いつも勉強の息抜きとして、記述式の問題を解いていました。記述式はある程度のパターンを覚えたら、問題文からそのパターンに当てはめていけばよいパズルのようなものなので、択一式ほど暗記する量がありません。
モチベーション
1~2年目は専業だったので、自宅にいると時間が無限にあり、甘えた考えが出てきて昼寝してしまうので、図書館に行くようにしていました。
だいたい朝9時から17時までいました。
専業受験生生活で一番つらいのは、社会との隔絶です。一日中家族以外と話さないなんてよくあります。毎日犬の散歩に行き、すれ違う人と挨拶するようにしていました。
3年目はアルバイトを始めたので孤独感が和らぎ、生活にメリハリがつくようになりました。同時にジム、ホットヨガにも通い始め、これが心身ともにとても良い気分転換となりました。
もちろん1~2年目で学習の基礎ができていたから、勉強時間を減らしても合格できたのだと思いますが、1日中勉強に集中するより、色々なことを同時並行でやっていくほうが自分には向いていたように思います。何かを犠牲にしないとなかなか合格は難しい試験ですが、勉強時間を減らしてでも、楽しみながら、リフレッシュする時間を確保するほうが、結果として効率的な勉強に繋がったなと思います。
仕事をしているとどうしても体がしんどくて、勉強机に向かえない日もありましたが、そういう日はベッドで横になりながらCROSS STUDYだけでもやっていました。毎日、自分に厳しくしすぎるとしんどいので、ほどほどに手を抜いてやるのが良いと思います。
総括
令和7年度司法書士試験に合格できたのは、間違いなくクレアールの「中上級パーフェクトBコース」を受講したからです。
やはり独学では難しいところがあります。予備校に学習範囲を絞ってもらい、スケジュールも示してもらいながら、それをこなすだけで合格に近づきます。特に、紙での勉強が苦手な方には、クレアールの教材、CROSS STUDYなどは素晴らしい勉強ツールだと思います。私は、中上級コースと上級コースどちらを受講するか迷いましたが、中上級コースにして基礎固めができました。背伸びせず基礎を確実にすることが合格に繋がりました。
また2年で合格する予定が、3年かかりましたが、それも結果的によかったです。短期で合格していたら間違いなく天狗になっていたし、合格のありがたみが分かっていなかったかもしれません。なかなか思い通りにいかなかった分、家族に心配をかけた分、周りの人や環境に感謝できるようになりました。
「3,000時間の勉強時間確保が必要」と言われている司法書士試験ですが、合格までに何時間かかるか、何年かかるかは人それぞれだと思います。ですが、勉強を続けていけば必ず合格できる試験でもあります。絶対に諦めない心さえあれば大丈夫です。