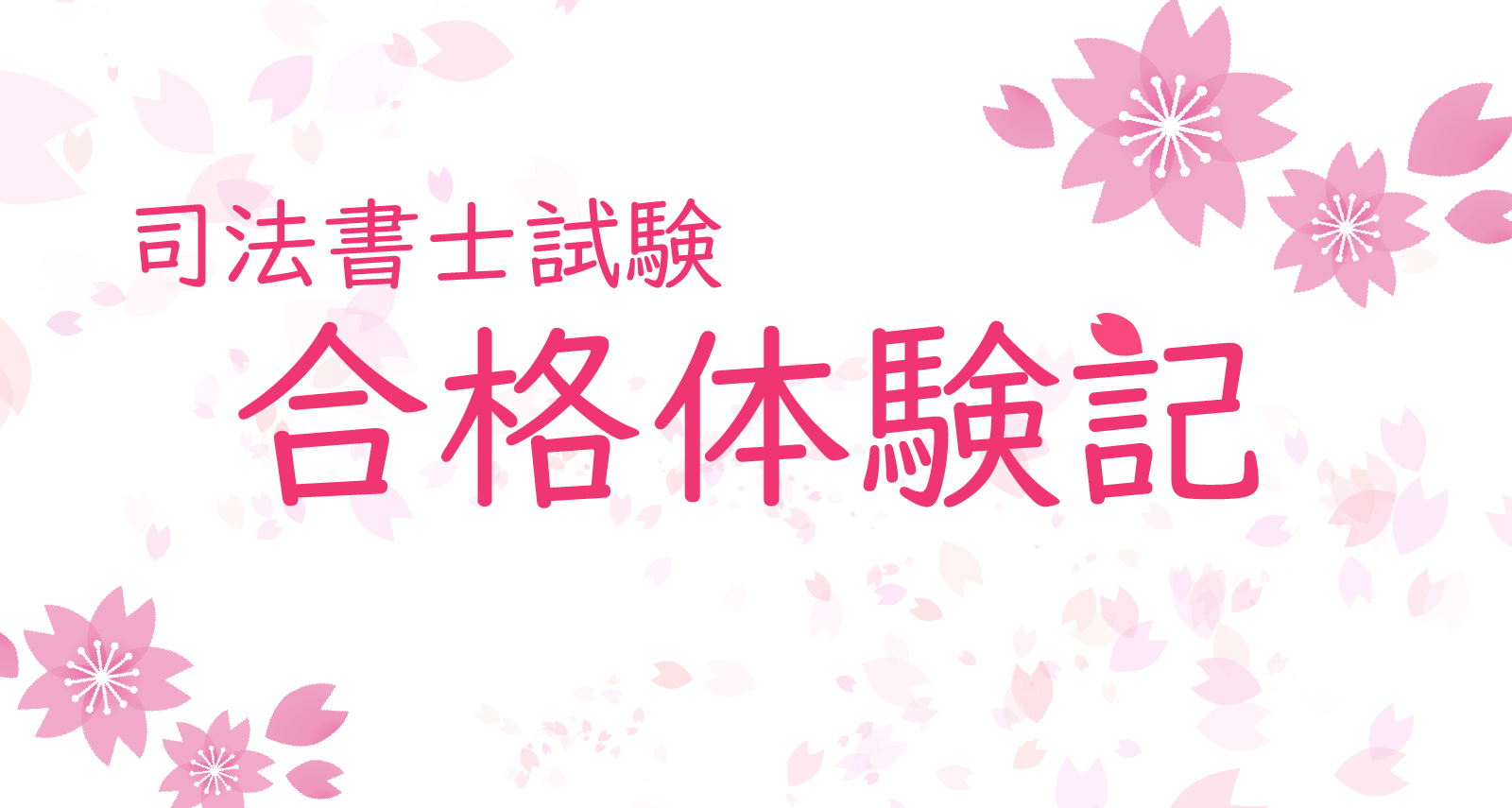本間 大々さん
受講コース:1.5年スタンダード秋コース
※時期によって販売期間外の場合がございます。
司法書士を目指した理由
出だしから恐縮ですが、私自身、これといって「目指した理由」はありませんでした。他の受験生や合格者の方々のように、明確な目標や、かっこいい夢、決定的なきっかけがあったわけでもありません。
強いて言えば、「大学受験での失敗を挽回したい」「難易度の高い資格を取得すれば1年後の就職活動で有利になるのではないか」「自分や周りの人の役に立てれば」といった漠然とした思いでした。
もし皆さんに明確な目的や大義があるのであれば、それを大切なモチベーションとして、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。
予備校選びのポイント
1番の決め手は、受講料でした。まず、予備校を利用しない場合は、自力で相当な量の教材を買い揃える必要があります。さらに、教材選びにかかる労力や、たとえ一通り買い揃えたとしても、さまざまな点を考慮しなければなりません。
教材をどのように活用するのか。本を読むだけで正しい理解が得られるのか。重要度のメリハリを自分でつけられるのか。法改正への対応は十分か。それだけで本当に足りるのか。逆に不要な記載はないか。そもそもその教材が最適なのか。
こうした点を踏まえると、学習開始前も開始後も、教材選びや学習方法の検討等に多くの手間と時間、そして費用がかかってきます。私はこれらの点に自信がなかったため、多少の費用を支出してでも、予備校を利用したほうが効率的かつ効果的だと判断しました。
予備校を選ぶ際には、費用だけでなく、講座の質という観点からの検討も必要です。挑戦する以上、最終目標はもちろん「合格」であり、その意味でも「合格実績」は重要な判断材料です。
また、各予備校が掲げる学習スタイルが具体的にどのようなものか、他の予備校とどのように異なるのかについて確認し、自分に合ったものを選ぶことも必要です。結果論にはなってしまいますが、これらの点においてクレアールが劣っているとは感じませんでした。
私たち世代に顕著な傾向かもしれませんが、いわゆる“コスパ”や“タイパ”といった「効率」は、良いに越したことはないと考えています。学生である以上、金銭的な余裕はありませんが、在学中に合格するために、一定の質を求めた結果、「非常識合格法」を掲げるクレアールにたどり着きました。
クレアールで学習して良かった点
まず、私は他社の講座やカリキュラム(模試を除く)を一切受講していないため、他社と比較することはできません。そのため、私自身の感想に近いものになることを断っておきます。そのうえで、良かったと感じる点を4つ挙げます。
(1)講師陣や質問制度などでお世話になったスタッフの方々
講師の方々の多くは、とても丁寧な講義を行ってくださいます。講義では、テキストの文章に加えて、具体例やわかりやすい言い換え、図やイラスト等を示してくれます。
また、質問制度などを通じて対応してくださったスタッフの方々にも本当に助けられました。質問内容が曖昧であったり、ごく基本的な事項を質問した際にも、丁寧な回答に加えて、関連事項として出題される可能性のあるものなど、プラスアルファの部分までご指摘くださいました。
さらに、私は学習内容に限らず、具体的なスケジュールの立て方や進度調整、学習方法についても、何度もアドバイスをいただきました。今振り返っても、質問制度やスタッフの方々の存在がなければ、合格できていなかったといっても過言ではないです。
(2)教材
教材はどれも素晴らしく、提供される教材のみで十分に合格を目指すことができます。個人的に、択一式・記述式対策のそれぞれで特に役立った教材を1つあげるとすれば、『択一六法』と『記述式ハイパートレーニング』です。
択一六法
クレアールが推奨する教材の1つであり、また、他の合格者さんの合格体験記等からも、素晴らしい教材であることは分かると思います。どの点を「素晴らしい」と評価するかは、受験生のレベルや学習方法、教材の使い方によって変わってくる程に多くあると感じます。
私自身は特にその「構成」に魅力を感じました。よく言われるように、法律学習の基本は「条文から」です。特に司法書士試験では、その意識がより強く求められると感じます。『択一六法』を軸に、条文を基礎として学習を進めていけば、合格は決して難しいものではないはずです。
記述式ハイパートレーニング
記述式対策の教材で、過去問の分析を基に出題類型ごとに整理されています。私は、問題集として利用し、記述式対策の中心としました。
こちらも他の合格者の体験記によく取り上げられる教材であり、多くの受講生がこの教材の良さを実感しているのではないでしょうか。
この教材で出題される類型や基本的な論点を身に着けていれば、どれだけ難易度の高い問題が出題されようと、対応は可能だと思います。
(3)講義
⑴にも関連しますが、講義はとにかく分かりやすいです。ただ、既にご承知のこととは思いますが、1回で全てを完璧に理解することは相当な能力がない限り困難でしょう。また、学習が進むにつれて、講師の説明の意味が後から理解できるようになることもあります。したがって、再度見直した際に講義内容を思い出せるようにしておくため、メモを丁寧に取るなどしておくことも有効でしょう。なお、私は時間に余裕がなかったため、全て2倍速で視聴していました。
(4)答練・模試
答練・模試は、3月頃から本格的に実施され始めます。忙しくなる時期ではありますが、本番のつもりで行い、締め切りは何がなんでも厳守しましょう。その時点での立ち位置の改善すべき点が確認でき、また、学習のペースメーカーにもなるはずです。
CROSS STUDYの進め方
⑴使用頻度やタイミング
学習の基本としていたため、ほぼ毎日使用していました。
⑵利用方法の変化
・初期段階:講義視聴後、該当する単元の過去問を解いていました。
・直前期:教材の読み込み→CROSS STUDYをとにかく繰り返す学習方法を採りました。
⑶復習の際に意識したこと
できない問題をできるようになるから点数が上がります。できる問題を解いても点数は上がりません。総復習する機会も必要ですが、できない問題に絞って取り組むことが効率的だと思います。一定期間を空けた後に同じ問題を解くサイクルを確立し、何度も見返すなどの工夫をしましょう。
⑷各種機能の利用方法
各種機能の利用方法はその人次第だと思います。学習しながら試行錯誤してみてください。
私個人としては、①「確認テスト」②「重要度」③「メモ」の機能を使っていました。
①「確認テスト」
欠かさず解いていました。分散学習にもなり、記憶の定着に繋がります。
②「重要度」機能
日常的に取り組む問題で、間違えたものには★を付け、正答できたら徐々に★の数を減らしていくことで、できていない問題や曖昧な問題とそうでない問題を区別し、直前期においても効率的かつ効果的に復習できました。
③「メモ」機能
テキスト関連ページや簡単な解法、コメント等をメモしていました。格段に効率を上げることができました。
⑸使い始めてからの学習の変化
CROSS STUDYは、合格の助けになったものの1つだと感じています。
また、定期的に品質改善アンケートの様なものがあるのですが、そこで要望として提出した「メモ機能」も早い段階で実装していただき、それ以降はさらに勉強しやすくなりました。
⑹紙冊子の問題集との使い分け
直前期においても紙冊子で問題を解くことはありませんでした。
学習全般
学習を進めていく上でのポイント、心構え
私は予備校選定の段階から一貫して「効率」に拘ってきました。大学の講義やゼミ、考査に加え、サークルや複数のアルバイトと同時並行で学習を進める必要があったため、学習「方法」を常に意識していました。いわゆる方法論(How to)です。
この点について語弊があるかもしれませんが、「言われた通りにやれば合格できるはず」です。分からないことや、分かったつもりのことがあれば質問しましょう。最適解をもらえる環境にはいるはずです。自分で考えて試行錯誤するのはその後だと思います。
学習スケジュールの立て方、学習の進め方
質問制度を利用し、提案いただいた内容を大枠として学習計画を立てました。スケジュールの立て方や学習の進め方は受験生それぞれの事情で変わると思います。是非質問制度を活用してみてください。
効果的な学習方法
前述したように、学習計画については指導・アドバイスいただいた学習方針の大枠を参考にしました。
学習方法についても、まずは「言われた通り」に取り組みました(講義の最初に、教材の使い方などについて指導があります)。
その後は、自分に合った学習方法を試行錯誤しました。効率的で効果的、かつ自分に合った方法を徹底的に追求しました。
例えば、模試や答練単位に加え、月・週単位や毎日で詳細な目標を設定し、自分の現在の学習方法が最適かどうか常に確認していました。可処分時間と処理すべき内容、予定進度と実際の進捗状況の比較、結果の原因分析と次への対策の検討などを行い、効率的で効果的な方法を探りました。
具体的な方法については、調べたり質問したりすれば簡単に情報を得ることができます。このプロセスは合否に大きく影響する重要な要素の1つだと思います。最適な方法を見つけられるよう、努力を重ねましょう。
学習段階と変化
学習初期
講義を視聴→該当単元の過去問演習→後日復習というサイクルで学習を進めました。
直前期
択一式:とにかく教材を何周もすることを意識しました。間違えた箇所に絞って何周もしたことが効果的でした。
記述式:『合格書式マニュアル』でひな形の確認、『記述式ハイパートレーニング』で演習を行っていました。基礎をとにかく徹底したことが効果的でした(ひな形や典型論点を叩き込む!)。
苦手分野の克服
「苦手」の分析から行いました。私の場合は、読み飛ばしや読み違いによって、誤った理解をしていることが多かったです。したがって、講義の再視聴、その単元を集中的に復習する、異なる問われ方をされても答えられるか確認する、解説の隅々まで読み込むことなどによって改善を図りました。
苦手を克服できるか否か(+そもそも苦手だと認識できているか?)でだいぶ変わります。自分の失点パターンや癖を把握することから始めましょう。
具体的な対策
午後の部の効率的な時間の使い方
午後の部は「時間との闘い」と言われますが、適切な対策を講じることにより、一定の正答率を保ちながら制限時間内に解き切ることは十分可能だと考えます。
私は択一式について、基本的には3肢を検討し、難易度の高い問題のみ全肢を検討するようにしていました。時間はかかりますが、その分、正答率を安定して確保できます。
時間短縮の対策としては、過去問や類似問題が出題された際に瞬時に判断できるようになる必要があると考え、CROSS STUDYを活用しました。その結果、本試験では択一式を45分程度で解き終え、35問中30問以上の得点をすることができました。
問題の解き方(ミス防止)
午後の部は、制限時間が厳しいですが、基準点を超える程度の正答率も求められます。私は、どんなに簡単な問題であっても必ず3肢以上を検討するようにし、読み飛ばしや読み違いによるミスを減らすことを意識していました(前述)。
モチベーション維持
集中力が切れたとき、リフレッシュ方法など
集中力は誰でも切れるものです。問題はそれとの向き合い方だと思います。私は、だらけてきたと感じたときは、音楽を活用して集中のギアを上げていました。
挫折、モチベーション維持
自分を追い込んで焦らせる、ご褒美を設定するなど、モチベーションの保ち方は人それぞれだと思います。
私の場合、少し特殊かもしれませんが、塾講師のアルバイトをしていたこともあり、生徒さんに「勉強しろ」と言う以上、「自分も勉強しなければならない」という一種の責任感が生まれ、それが自然とモチベーションの維持につながっていました。
そもそも、学習できる環境があること自体、とてもありがたく、恵まれていることだと思います。その意識があれば、簡単に嫌になったり、「今日は勉強しない」という選択肢が出てきたりすることはないと思います。
そのうえで、私は大きな挫折を感じることもありませんでした。もし挫折や不安を覚えることがあっても、それは勉強することでしか払拭できませんし、それこそが一番の解決方法です。そんなことを考えている時間があるなら、勉強しましょう。サボっても構いませんが、後々痛い目を見るのは自分自身です。それが嫌なら、勉強するしかありません。やらない理由=言い訳ならいくらでも思いつきます。そんなことを考えている暇があれば、勉強しましょう。
学業との両立
学生の身分で恐縮ですが、「両立はできないはずがない」と考えています。実際に、様々な背景をもった諸先輩方が合格されています。どうか「自分は特別な環境だから合格できない」などとは思わず、勉強を続けてください。効率を上げる工夫や、優先順位を見直して時間を生み出す方法はいくらでもあるはずです。
その他
私は、先輩方の合格体験記から多くを学びました。成功例だけでなく、失敗例にも触れることで、学習方法を考える上で大いに参考にさせてもらいました。
私の体験記も、どなたか一人にでも意味のあるものになればと思い、執筆させていただきました。是非「本気で」勉強してみてください。合格は、そう難しくないはずです。
これまで本当に多くの方にお世話になり、支えてもらいました。直接ご挨拶ができていない方もいるため、この場を借りて心より感謝申し上げます。