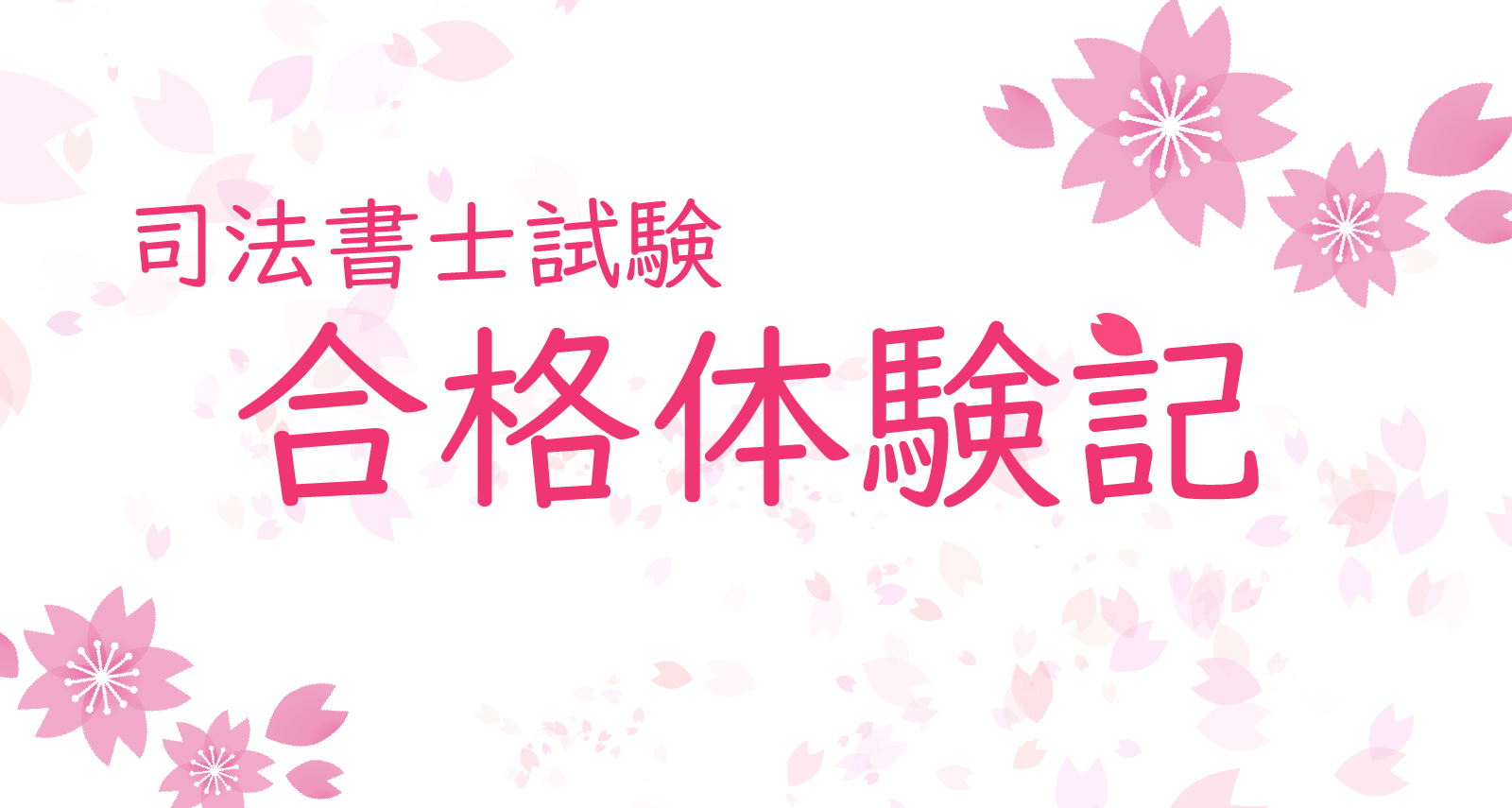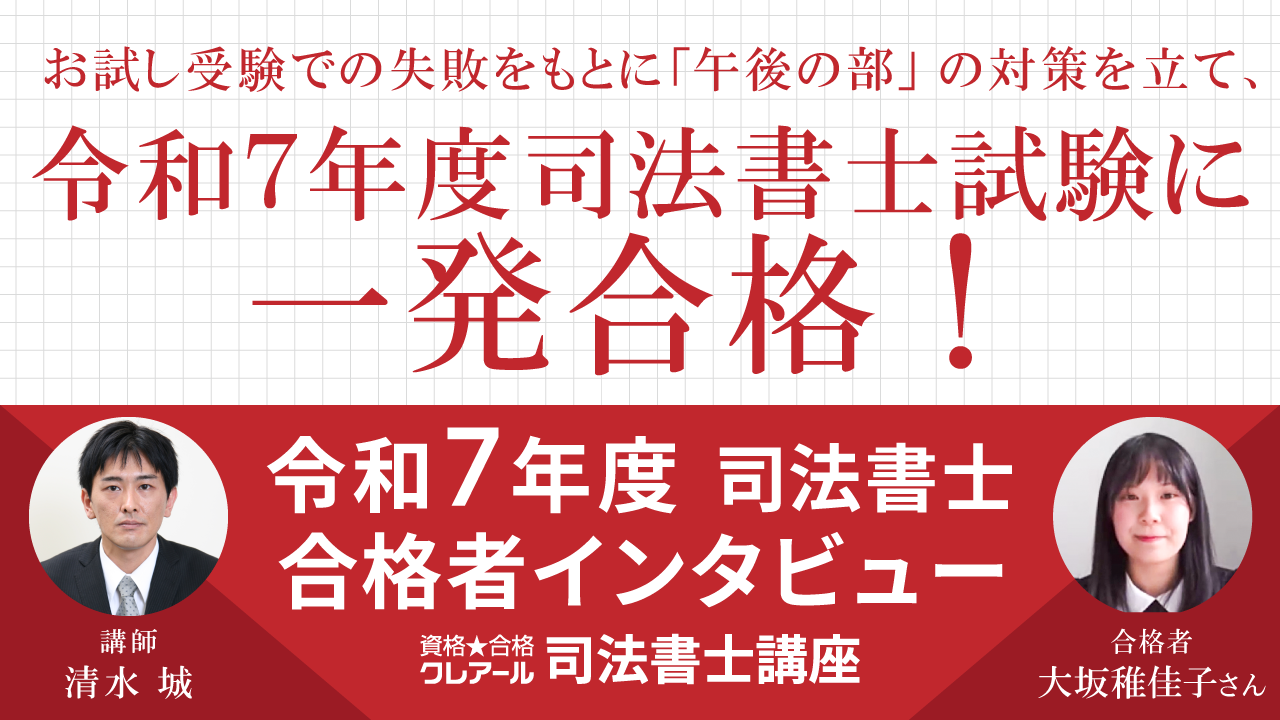大坂 稚佳子 さん
受講コース:1.5年スタンダード秋コース
※時期によって販売期間外の場合がございます。
なぜ司法書士を目指したか
3年前に夫の転勤に付いていくために仕事を退職し、平日に時間がありました。「働かないといけないな」と思いつつも、またいつ転勤があるか分からず動けずにいたところ、家族が家を購入する機会があり、司法書士の先生に登記でお世話になったことから、司法書士という仕事を知りました。さらに仕事内容を調べていくうちに、相続や成年後見に関する業務など、これからの社会に必要とされる仕事であること、またそういった相談に乗ることで人の役に立てる仕事であることから興味が湧き、目指してみることにしました。
予備校選びのポイント
色々な予備校の資料請求をさせていただき、口コミを調べたりもしましたが、クレアールの合格体験記で皆さんが口を揃えて「『択一六法』が良い」と言われていたので、私も「『択一六法』で勉強してみたい」と思ったのが最大の理由です。実際、条文ごとに超訳や判例、過去問等の必要な情報がすべて揃えられており、学習の際に非常に役立ちました。
またお試し受講で視聴した講義がシンプルで分かりやすかった点と、講義やテキスト、答練・模試など充実した教材内容に対して、価格がお手頃でコストパフォーマンスが良かった点が、クレアールを選んだ主な理由です。
クレアールで学習してよかった点
講義、教材、CROSS STUDYなど全てがバランスよく、一通りカリキュラムに沿って学習するだけで合格レベルの力がついた点です。
さらに先ほども述べましたが、『択一六法』が非常に良かったです。「『択一六法』の記載内容を、全部見たまま記憶できれば、余裕を持って合格できるのに…」と何度も思いました。内容を全部覚えることが出来なくても、間違えやすい論点や重要な論点などが図表にまとめられていて、その図表を思い出すことで問題を解く際に助けられたこともありました。『択一六法』自体のサイズもコンパクトで持ちやすくてお気に入りです。
また、「実力完成総合答練」と「全国公開模擬試験」が直前期に送付されますが、どちらも非常にレベルが高い問題ばかりで、かなりやりごたえがありました。答練は制限時間通りに一度解くだけでも力が付きますが、何回も解いて復習することによって合格レベルを上回る力が付くと思います。
CROSS STUDYの進め方
(a)使用頻度、タイミング、学習時期ごとの利用方法の変化
お試し受験前までは「とても便利だな」と思いつつも、紙の過去問題集を解いたりするのに忙しく、定期的に配信される「確認テスト」を解くくらいでした。令和7年の4月から試験直前までは、1日50問から100問とノルマを決めて毎日解きました。紙の過去問題集は何周もしていたので、それ以外の問題を大量に解くことができてよかったです。
また、特定の科目を選択せずに(全ての科目カテゴリにチェックが入った状態で)使用していたので、色々な科目をミックスして飽きずに解き続けることができてありがたかったです。寝る前に使用するのがメインでしたが、スマホ一つで完結するので、ちょっとしたお出かけ中のスキマ時間などにも活用していました。
(b)各種機能の利用方法
一度間違えた問題、当てずっぽうで偶然合っていた問題について、重要度を★5にしていきました。全問題を解き終えた後は★5の重要度を設定してある問題を抽出して再度解き直し、さらに間違えた問題には「間違えやすい問題」のユーザータグを設定していきました。何回か解いていく中で理解して正解できるようになっても、ユーザータグを最後まで外さないでおき、時間がある時に検索をかけて苦手な問題を見返せるようにしていました。結構な問題数でしたが、「こんなにも間違えやすい問題数があるのか」と危機感を覚えることで、むしろ勉強のモチベーションにつながっていました。
(c)CROSS STUDYを使い始めてからの学習法の変化
本格的に活用し始めたのが令和7年の本試験の直前期にあたる4月からだったので、それまでは講義を聞いてテキストを読み込んで、過去問、記述式の問題集を解くという紙媒体での勉強が主でした。それらが終わってからは答練・模試を解き、空いた時間に問題数を決めて演習するのと、寝る前の暗記やスキマ時間にも活用させていただきながら、分からなかったら『択一六法』を見返して振り返るという学習法に変わりました。
学習スケジュールをどのように立てて進めたか
仕事や学業と両立されている方が多い中、私は専業の受験生だったのであまり参考にならないと思いますが、平日の日中7時間ほど勉強し、土日は完全に休むといったスケジュールで学習をしていました。
スケジュールとしては、まず出題範囲の全体像を把握するために、講義を基本4法から一通り視聴しました。良く分からない箇所も多々ありましたが、「とりあえずどういう科目があって、それぞれどういう内容なのか」を理解するためにテキストを読みながら視聴しました。講義の視聴は最初の半年くらいで終了し、お試し受験前には全て聞き終えることができました。
その後過去問に取り組み、間違えた問題はチェックし『択一六法』や『基本テキスト』で再度確認しました。令和7年度の本試験までに、過去問題集はマイナー科目以外は8周しました。問題集の出題年度の上に、何周目で間違えたのか数字を書いてチェックし、次ページの解説の重要な部分に蛍光マーカーを引いていたのですが、複数回間違えるポイントは色を変えて赤ペンで線を引いて、3回以上間違えた問題の解説部分にはさらに濃い黒色ペンで囲ったりと、解説のページを見て「どの論点の問題を間違いやすいのか」がすぐわかるように書き込みをしていきました。
記述式の勉強は、「合格書式マニュアル解説講義」を視聴した後、分からないなりに記述式問題を解いてみようとすぐに始めました。『合格書式マニュアル』でひな形を覚えたら「【初級】基本マスター講義 記述式編」、「【中級】記述式解法マスター講義」、「記述式ハイパートレーニング解説講義」と順に学習していきましたが、難易度が異なる問題がたくさんあり、何周もすることで体で覚えることができました。
また手を動かして紙に文字を書いていくという作業をするのが学生以来でしたので、新鮮でもあり、「択一式の勉強に飽きてきたら記述式に切り替える」ことでやる気の維持にもつながっていました。
効果的であった択一式対策
やはり過去問を何周もすることです。間違えた問題についても、解説を読んで分かったつもりにならず、「なぜ間違えたのか、なぜこの答えになるのか」を自分で説明できるまでやりこむようにしました。繰り返し解くにはCROSS STUDYも効果的です。過去問には何度も出てくる論点・知識も多く、慣れてきたら「ここの正誤を聞きたいのだな」とポイントが分かるようになると思います。
効果的であった記述式対策
記述式はまずひな形を覚えることが重要です。私は『合格書式マニュアル』を活用しました。最初はひな形を覚えるために使用し、その後は『記述式ハイパートレーニング』などの問題集を解いていきながら何度も立ち返っては、『合格書式マニュアル』でひな形を確認することでかなり知識が深まります。『合格書式マニュアル』は、基本的なひな形が網羅されていて、見出しですぐ確認したいひな形を引くことができて、素晴らしいひな形集だと思います。
『記述式ハイパートレーニング』等の記述式対策教材も試験のために練られた問題が多く、特に『記述式ハイパートレーニング』は何度解いても間違えるくらい難しかったですが、かなり記述式の対策になりました。
先ほども述べましたが、「実力完成総合答練」を含めて、記述式問題を何度も解くことで力が付きます。また記述式の学習が始まったら、「1日1問は記述式の問題を解く」「1ページはマニュアルを読む」などと自分でノルマを決めて、記述式の勘を鈍らせないようにすることも重要だと思います。
苦手分野の克服について
会社法・商業登記法と民事訴訟法・民事執行法・民事保全法が苦手でした。
会社法・商業登記法はなじみが薄く、理解したつもりになってはすぐ忘れていましたが、記述式の問題を解き始めてからは、組織再編や設立等、択一式と関連する分野について知識が深まっていきました。やはりどうしても身近な科目ではないので、択一式、記述式ともに1日に1回は問題に触れ、繰り返し解いて慣れていくことが重要かと思います。
また、民事訴訟法等については、過去問を解く際、今自分が民事訴訟法の問題を解いているのか民事保全法の問題を解いているのか分からなくなるほど、よく分かっていませんでした。そのため、学習の2年目になって講義をまた一から聞き直し、テキストをもう一度丁寧に読み込み過去問に取り組みました。何回か解いていくことで頻出の論点が分かり苦手意識は薄れていきました。『択一六法』に記載されている暗記用の図表もとても重宝しました。
午後の部の効率的な時間の使い方
午後の部は午前の部に比べて、時間が本当にタイトだと思います。私は令和6年度にお試し受験をしましたが、解く順番や時間配分などの対策を特に取ることもなく、なんとなく択一式と記述式で半々くらいの時間配分でいいかなと思って受験したところ、大変痛い目に遭いました。
私の場合ですが、お試し受験では、順番通り択一式から解いていき、3時間の制限時間のうち不動産登記記述式が終わった時点で残り30分となっており、商業登記記述式は問題文を読んで「登記の事由」を記載する時間しかありませんでした。
考える時間も必要ですが、書くという作業だけでも時間が結構取られますので、このような事態に陥らないために事前に時間配分を決めて、記述式のメモは何が解答に必要な情報か一目で把握できる簡潔なものにするなど、日ごろから練習していくことが重要だと思います。
午後の部の解答の順番について
お試し受験を経験して解答の順番が非常に大事だと気付きました。
そこで作戦を考えたところ、まず商業登記記述式は例年不動産登記記述式よりは難易度がそれほど高くない印象を受けました。また他の合格者の方もおっしゃっていましたが、「商業登記記述式は記載量こそ多いものの、書いた分だけ採点されるため、不動産登記記述式より点数を取りやすいだろう」と考えました。
そのため次年度はまず商業登記法記述式から、その次に不動産登記記述式、そして残った時間で択一式を解くことに決めました。時間はそれぞれに1時間ずつ使うことを目安としました。
令和7年度の本試験では、商業登記記述式が例年より難しい気がしましたが、最初に取り掛かったため焦ることもなく、落ち着いて解けました。結局択一式には1時間30分ほど時間を残せたので、私にとって最適な解答順番でした。
択一式は時間が少なくなってもキーワードを拾いつつ、最低2つの選択肢を読むだけでも解答を導けると思うので、配点の高くなった記述式から取り組む方が個人的にはおすすめかなと思います。
これから受験される方は、答練や模試を受けつつ、「択一式と記述式のどちらが得意なのか」「何にどのくらい時間がかかるのか」を分析し、本番までにご自分にとって最適な解答順番と時間配分を見つけられたらいいなと思います。
答練・模試で本番を見据えてどのような対策をしたか
「実力完成総合答練」や「全国公開模擬試験」を解くことで本当に力が付きました。本試験が近づいてくると、結構な頻度で送付してくれます。届いたら1週間以内に、毎回本番だと思って緊張感を持って取り組むようにしていました。
「実力完成総合答練」が始まるまでは、解答時間を意識して記述式の問題を解いたことがなかったので、制限時間のとおり解こうとすると、意外と時間が足らないことに気づきました。また、答練や模試の後に返却される「個人成績表」では、自分の点数や順位を確認できるのですが、低い順位を見て、「まだまだ合格までに実力が足りていない」と気付くきっかけになりました。『合格書式マニュアル』では見たことがあるのに忘れていて解けなかった問題も多く、「本番で同じ問題が出たら絶対に間違わないようにしよう」と3回解き直しました。
実際本番の試験の商業登記記述式では、『実力完成総合答練』で書き方が分からずに間違えた「会計参与の合併による変更」という、答練と全く同じ論点が出題されました。復習したばっかりだったので迷わず書くことができて、確実にここは点が取れたと嬉しかったのを覚えています。
印象に残ったパレット記事
全て読みごたえがありましたが、確認テスト付きのまとめ記事は、理解が面倒でなんとなく深入りするのを後回しにしていた分野(会社法の組織再編や債権者保護手続等)のまさに欲しかった情報を、横断的に文章や一覧図などでカラフルにまとめてくれていてかなりありがたかったです。一度読むだけでも分かっていたようで分かっていなかった部分が炙り出されて勉強になるし、学習後期の理解が進んだうえで読んでも、知識が整理されてより深まっていく気がします。
その他のコラムなどの記事も、勉強する気が起きない日でも息抜きに読めて面白く、講師の先生の話や先輩受験生の体験談などが大変参考になりました。
令和7年度司法書士試験に合格することができた一番の秘訣
私は他の予備校には通わず、クレアールでの学習だけで合格することができました。先生方の講義で『基本テキスト』等の内容を理解し、過去問を周回しながら分からなかった箇所を『択一六法』で確認してさらに理解を深め、CROSS STUDYも活用しつつ直前期の「実力完成総合答練」、「全国公開模擬試験」でかなり実力を上げることができました。学習に取り掛かったばかりの頃は、「こんなに範囲の広い、難易度の高い試験に合格できるのかな」と不安にもなりましたが、クレアールを信用し、カリキュラムどおり学習を進めていくだけで充分に合格を目指せる力が付き、実際に合格することができました。本当にありがとうございました。
クレアールと自分を信じて努力を続ければ確実に合格できる力はつくと思います。これから受験される皆さんの合格を心よりお祈りしております。
インタビュー動画公開中!
司法書士を目指したきっかけやクレアールを選んだ理由、教材の具体的な活用方法、一発合格の秘訣など、これから司法書士を目指す方にとって参考になる内容を詳しくお話しいただいています。ぜひご視聴ください!