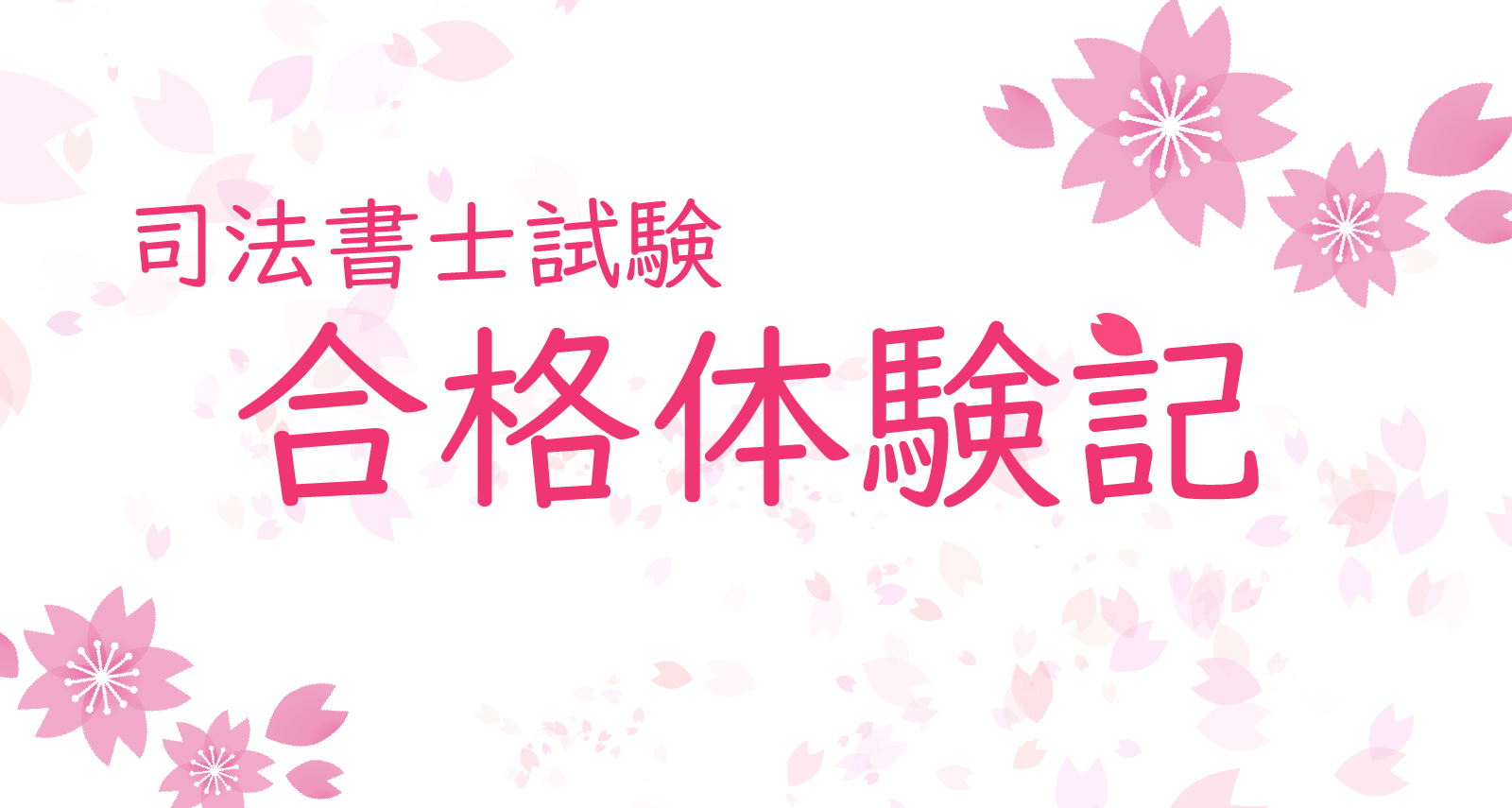T.Kさん
受講コース:記述式攻略パーフェクトコース
なぜ司法書士資格を目指したか
私が司法書士を目指したのは、子育てが一段落し、これから何をしてどう生きたいかを考えたときに、手に職をつけ、生涯現役で、人のお役に立てる仕事をしたいと思ったことがきっかけです。
9年間、病院の受付のパートをしていましたが、父が亡くなったときに行政書士の方にお世話になった経験から行政書士の資格をとり、相続専門の税理士法人事務所に勤めました。行政書士も在籍しており、私の仕事はその補助業務でした。戸籍を取り寄せ、戸籍を辿って古い戸籍を読むことや、不動産の登記事項証明書を見たりするのが好きでした。最終的に必要な書類を揃え、司法書士法人に相続登記の依頼をし、登記が完了した後、お客様にお渡しする仕事でした。その時に司法書士の仕事に興味を持ち、司法書士を目指して勉強している同僚の刺激も受け、自分も司法書士になろうと決め、勉強に専念することにしました。
予備校選びのポイント
私がクレアールを選んだのは、第一に他校に比べて良心的な価格だったことです。そして自分のペースで進められるWeb受講であり、質問制度があることでした。また、受講生が絶賛する『択一六法』にも惹かれました。書店で販売されている一般的な六法全書に比べ、条文のあとに解説などが掲載されている横書きの『択一六法』は、抵抗なく読むことができそうだと感じました。
クレアールで学習して良かった点
良かった点は、クレアール講師陣と、期待通りの『択一六法』です。
先生方それぞれの個性と、講義や解説の持ち味があり、どの先生もとても分かり易いです。全ての講義が同じ先生ではないところが、講義を聴く楽しみでもありました。
なかでも、浅沼先生の商業登記の記述式問題の解説は、会社の機関や組織再編等、問題を解くにあたって理解しておくべき根底となる部分や、なぜそのような手続きが必要になるのかを説明してくださり、苦手な会社法、商業登記法が面白く感じられるようになりました。
また、古川先生の「【中級】択一六法マスター講義」は何度も視聴しました。先生の講義内容は素晴らしく、就寝前、横になってからも目を閉じて聴いていました。
そして、『択一六法』は、条文のあとに超訳、解釈、判例、過去問があり、さらに知識の横断整理を図ることができる表も載っており、テキストのような六法です。私は、『択一六法』に載っていない事項や関連知識を書き込んで、プラスアルファの知識も覚えられるようにしていました。
1度目の受験は、『択一六法』まで手が回らず択一式の基準点に届きませんでしたが、2度目の受験までに『択一六法』を何周もするうちに安定した点数をとれるようになりました。
CROSS STUDYの進め方
(a)どのように利用したか
CROSS STUDYは、令和5年度のお試し受験後にリリースされました。一通り全範囲の勉強を終えていましたので、最初のうちは、民法から順に進めました。1日のノルマは課さず、その日の気分や調子でやるべき範囲を決めていましたが、必ず毎日やりました。できなかった問題には重要度☆をつけて復習し、その他の機能では、クロスワード、ランダム出題機能を利用しました。定期的に配信される確認テストは、その都度解きました。
(b)学習時期・段階ごとの利用方法の変化
CROSS STUDYをやり続けて正解率が9割以上になってからは、毎日取り組むのではなく、苦手な単元や、答練や模試の択一式の復習に時間をあてました。ただCROSS STUDYはどこでも勉強できる手軽なツールでしたので、隙間時間や外出の際などによく利用しました。特に、「過去3回のうち1回でも正答できなかった問題」を抽出できる機能は重宝しました。
直前期は、全科目を選択し、ランダム出題に設定して問題を解きました。今まで正解できていた問題もできなかったり、正誤は判断できても理由付けが曖昧だったりするものが予想以上にあり、少し焦りましたが、それらはスクリーンショット画像に残して見返しました。
CROSS STUDYには、解説のところに知識を横断整理できる『択一六法』から引用された表が載っている問題があり、『択一六法』を開いて確認することなく復習できるところがよかったです。私は、どの問題でもその表が載っていれば必ず目を通しました。問題を進めるのに少し時間がかかりますが、その積み重ねで、直前期にはぶれない正確な知識が身についたと思います。
CROSS STUDYで十分だとは思いましたが、本試験は紙での出題ですので、念のため直前期に紙冊子の過去問題集を1周しました。
学習全般
(a)学習を進めていくうえでの心構え、学習の進め方
学習初期は、クレアールの学習計画表に沿って、遅れをとらないようにすること、提出期限を守ることを心掛けましたが、1日1日やることを細かく決めず、月単位で大まかな計画を立てました。そして、先生のおっしゃるように、わからないことがあっても立ち止まらず、とりあえず最後まで講義を聴き、全体像をつかむことを心掛けました。講義の単元に対応する過去問を解いて解説を読み、分からなければテキストに戻りました。2回目以降の講義は視聴速度を1.5倍にして視聴しました。1度目に理解できなかったことも、2度目、3度目で理解できるようになったりします。さらに他の法律を学んでいくことで、より理解が深まっていくこともありました。
学習中期は、過去問、記述式の勉強が中心でした。記述式は、『合格書式マニュアル』と『合格書式マニュアル対応問題集』を並行して学習し、その後に「【中級】記述式解法マスター講義」、『記述式ハイパートレーニング』の問題を繰り返し解き、直前期は答練、模試の復習もしました。『合格書式マニュアル』はいつも手元に置いて、ひな形を忘れてしまったときや、『択一六法』を読んでいて気になったときは、すぐに確認するようにしていました。
令和6年度の1度目(お試し受験を除く)の受験は、記述式の基準点に届かず不合格となったため、年内はずっと記述式対策をしていました。初見の問題に対する情報処理能力が乏しく、不動産登記記述式が苦手でした。
これを克服するため、問題文を正しく理解し、与えられた情報をとりこぼすことのないよう、いろいろな方の問題の読み進め方を参考にしました。さらに答案構成用紙の使い方、間違い防止策なども参考にし、これまでの解き方を改善しました。商業登記記述式は添付書類を忘れがちでしたので、例えば、印鑑証明書の添付が必要とわかったところで、余白に「印」と書くようにしました。そして、過去問20年分、クレアールの「科目別ベーシック答練(記述式編)」、『記述式ハイパートレーニング』、直前期の「実力完成総合答練」、模試の記述式問題を繰り返し解き、間違えたところはノートにまとめ、見返すことで次回同じ間違いをしないようにしました。20年分の過去問を解くことで出題傾向がわかり、本試験のボリュームにも慣れることができましたので、前の年に過去問をやっておかなかったことには後悔しました。
一方で、択一式は基準点を超えていましたので、学習方針を変えることなく、レベル維持のため、記述式の勉強の合間にCROSS STUDYを解き、『択一六法』を緩いペースで読んでいました。
そして迎えた令和7年度の2度目(お試し受験を除く)の受験でしたが、試験を終えた後、不動産登記、商業登記の記述式のいずれについても、あちらこちらで間違えが判明し茫然としました。あまりの悔しさで合格している自信がなく、試験後も記述式の勉強をずっと続けていましたので、合格を知ったときは本当に信じられませんでした。ぎりぎりでしたが合格基準点を超えていました。記述式では悔いが残り、やり切ったという実感を持てませんでしたが、クレアールの教材や講義、CROSS STUDY をやり続けたことは正しかったと思います。
(b)苦手分野の克服について
苦手分野は、わからなくても避けずに、『択一六法』を繰り返し読みました。苦手分野は特に日が経つと忘れがちですので、『択一六法』に付箋を貼って、たまに思い返して覚えていなければ再度確認しました。
答練や模試の択一式、記述式の関連した問題を解くことで理解できたこともあり、受験生が苦手とする組織再編などの「Palette司法書士コラム」の知識まとめ記事で克服できたこともありました。
本試験での具体的な対策
午後の部の択一式は、全肢検討ではとても間に合いません。私は短い肢から読み、なるべく3肢くらいで解答を導くようにしました。そして全ての問題を解き終えた後にまとめてマークシートを塗り、再度、問題用紙とマークシートの照合をしました。少ない肢で解答を導くために、確信をもって他の肢を切れるような正確な知識を身につけることが必要だと思いました。
午後の部の時間配分は、択一式、不動産登記記述式、商業登記記述式のそれぞれについて、各1時間を目安にしました。答練や模試では必ず時間を計り、常に時間を意識しながら解く訓練をしました。
解く順番は、令和6年度の試験では、択一式→不動産登記記述式→商業登記記述式でしたが、苦手な不動産登記に多く時間を使ってしまい、商業登記で残り40分になり、さらに手や指が固まってきてしまって、最後は思うような速さで書けませんでした。
その反省を踏まえ、記述式を連続して解くことを避け、商業登記で点をとるために、商業登記記述式→択一式→不動産登記記述式の順番で解きました。これはこれで、本番では不動産記述にできるだけ時間を残すため、択一式で気持ちが焦ってしまい、これまで答練や模試でコンスタントに取れていた点数を大幅に下回ってしまいました。本番での想定外でしたが、結果としてはこの順番で良かったと思っています。
モチベーション関係
「絶対に資格を取る!」という強い気持ちでしたので、モチベーションが下がってしまうことはありませんでした。なかなか理解できない単元や、覚えられない条文、苦手な記述式も、「諦めず勉強を続けていけばいつかきっとできるようになる」と自分を信じてひたすら勉強を続けました。
そして、勉強に疲れたときや問題が解けないときは、その合間にする家事がいい気分転換になっていました。そして、たまに実家に帰ってゆっくり過ごしたり、友だちと会ったりしました。
その他
勉強を始めてから合格に至るまで、クレアール、そして家族に感謝の気持ちでいっぱいです。
勉強の合間に読むクレアールの「Palette司法書士コラム」の記事は、楽しみの一つでした。特に、米谷先生の記事を読んだときには、元気が出ました。50代で挑戦することに不安もありましたが、これからなりたい自分を思い描いて、常に「前向きにいこう」と思えました。
最後の方に配信された消費貸借・使用貸借・寄託についての知識まとめ記事は、知識が混同しがちなところでしたが、試験前に知識を確かにすることができました。
クレアールの質問制度も何度も利用させていただきました。毎回、丁寧に分かり易く解説、回答してくださった受験対策室の皆さま、本当にありがとうございました。
家族の存在も大きく、夫は普段から家事を手伝ってくれ、できるだけ勉強時間を確保できるようにしてくれました。そして、子どもに対しては「勉強しなさい。やればできる。」などと言っていた自分へのいい意味でのプレッシャーになり、モチベーションを維持することができました。
今後は、人のお役に立てる仕事ができるよう、日々勉強、努力を怠らず、頼られる司法書士になりたいと思います。
これから合格を目指す皆様、クレアールを信じて自分を信じて、決して諦めずに合格を勝ち取ってください!!