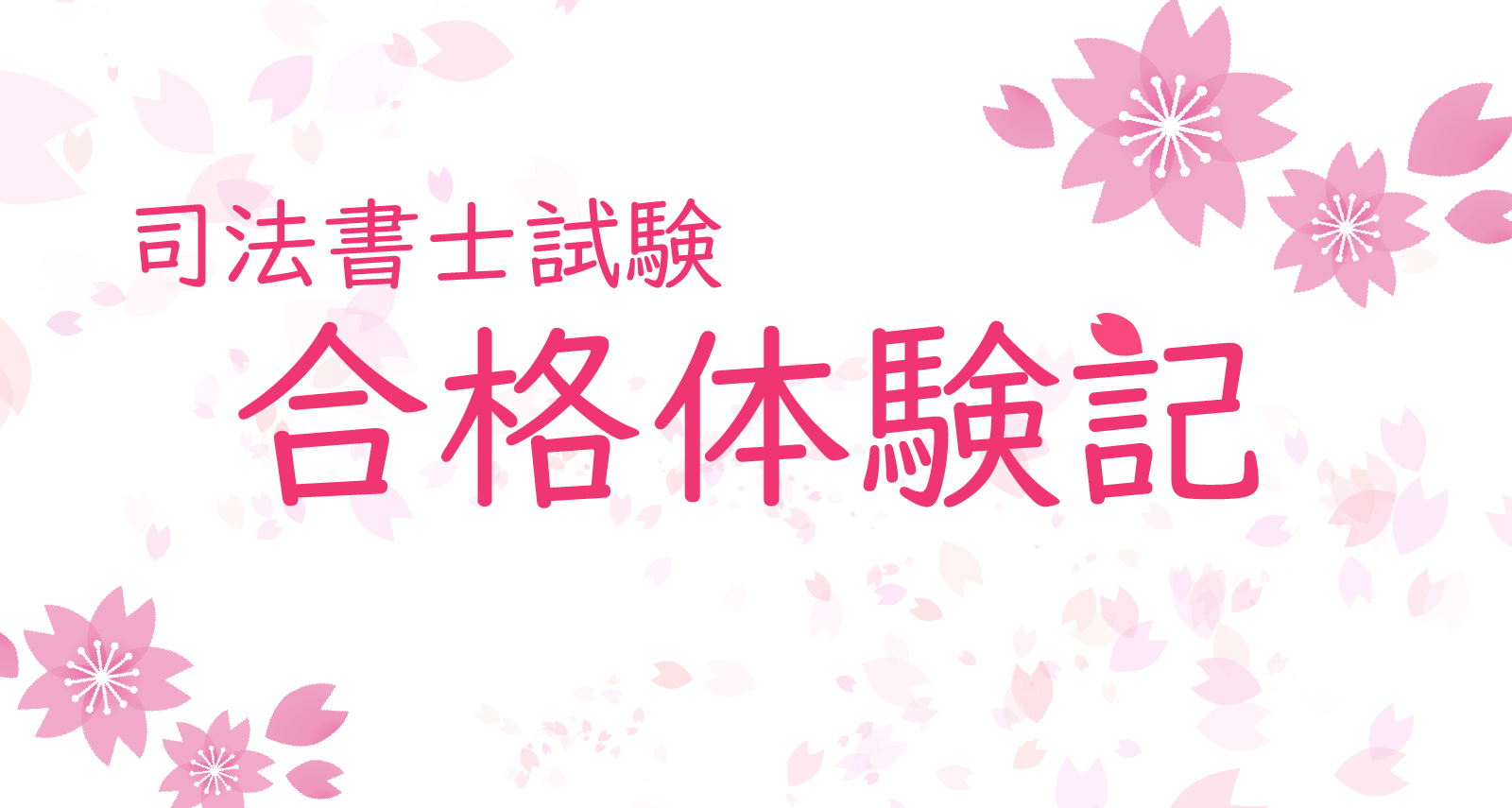O.Tさん
受講コース:上級パーフェクトコース
司法書士資格を目指した理由
コロナウイルスによる経済活動の停滞によって、自営業者である私の売上は減少しており、空いている時間が増えていました。また、ちょうど50歳の節目を迎え、何か新しいことを始めたいと思っていたところです。
私の仕事は、主に不動産の有効活用のお手伝いをするものでしたので、司法書士という資格の存在自体はすでに知っていました。ただ、科目数が多く合格までに時間がかかる資格であることも認識していましたので、すぐに資格を取得して業務に活かすところまで想像できずにいました。
そのような中、たまたまインターネットでクレアールの通信教育を目にし、長く司法書士講座を実施していることを知りました。業務時間が不規則な自分にとって、空いた時間に自分のペースで授業を進めていけるのはとても魅力的でした。また、受講料が比較的安かったこともありがたかったです。
あらためて他の予備校や通信教育機関との比較を行っていくと、コンスタントに合格者を輩出しており、無駄なく効率的なカリキュラムを組んでいることが分かりました。また、『択一六法』という独自の教材が人気であることも目に留まりました。
業務の都合も考慮しつつ、うまくいけば合格に辿り着けそうだとの希望のもと、総合的な観点からクレアールの初学者講座を選択し、2021年6月より学習に取り掛かりました。ただ、今思えば受講開始のタイミングとしては少し遅かったかなと感じます。合格までの流れを思い返してみると、自分的には4月スタートがよかったように思います。
受講開始から合格まで
1年目 令和4年度司法書士試験(お試し受験)
最初は「2023・24年合格目標合格ルート2年セーフティ春コース安心保証プラン」を受講しました。まずは「【初級】基本マスター講義 択一式編・記述式編(基本講義)」をひと通り終えることを目標に、1日1講義(30分×2コマ)を目安に進めていきました。このペースは後々の答練等の日程を考慮すると結構遅いのですが、自分の仕事量と体力的な面を考えれば妥当なところでした。実際には計画よりもさらに遅れてしまい、結局、商法(会社法)・商業登記法関係については記述式も含めて全く手を付けられずに、令和4年7月のお試し受験を迎えることとなりました。
無論合格などできるわけがないのですが、試験の雰囲気を知るにはとても良い機会でした。周りの受験生の年齢層を知ることもできて、その後の励みになったことを覚えています。
なお、この時まで、商法(会社法)関係は先述のとおり全く始めていないのですが、民法と不動産登記法およびその他のマイナー科目は過去問を含め1回は終えました。また、不動産登記の記述式はとりあえず「【初級】基本マスター講義 記述式編」を終えた程度だったかと思います。記述式については、とにかく基本(『合格書式マニュアル』掲載のひな形の暗記)ができていないと話にならないので、この時点では『記述式ハイパートレーニング』に辿り着くことができませんでした。
2年目 令和5年度司法書士試験
2年目に入り、商法(会社法)・商業登記法の基本講義を聴くとともに過去問を解いていきました。また、それ以外の科目については、古川先生の「【中級】択一六法マスター講義」を聴きながら、過去問を1肢ずつ丁寧に解いていきました。商法(会社法)等についても、基本講義を終えた後、続けて『択一六法』を使用したこの講義を聴きました。なお、まだこの時点ではCROSS STUDYはリリースされていませんでしたので、過去問冊子を使用して1肢ずつ解いていきました。
記述式に関しては、不動産登記は『記述式ハイパートレーニング』を一通り解いてみました。この問題集は基本的に過去問を題材とした問題集ですので、いきなり解くと結構しんどいものがありました。そこで、「【中級】記述式解法マスター講義」を並行して聞きながら、少しずつ連件申請に慣れていくようにしました。同時に、『合格書式マニュアル』については何度も見返しながら暗記するように努めました。また、商業登記については、まだ基本講座を聴き始めている段階でしたので、「【初級】基本マスター講義 記述式編」を聴くとともに、『合格書式マニュアル』を全体的に眺める程度だったかと思います。
このような状態で2年目の令和5年度司法書士試験を迎えましたので、やはり合格などできるはずもないのですが、とりあえず商業登記記述式を除くすべての問題を解くことで、できる限りのことはやりました。
結果として、択一式は午前の部・午後の部ともに基準点を超えましたが、記述式はある程度頑張ったつもりであった不動産登記についても、まったく及びませんでした。
この時、択一式については過去問をしっかり解いていけばある程度は正解できるという感想を持った覚えがあります。また、商法(会社法)・商業登記法については、一見難しそうに感じるのですが、過去問を解きながら『択一六法』や『基本テキスト』を見返すことを繰り返すことで、案外点数が伸びることが分かりました。しかも一度正答を出せるようになると忘れたころに解いてもだいたい正解を導けます。むしろ、比較的長くやっているはずの民法の難しさを実感しました。
3年目 令和6年度司法書士試験
ここまでの段階で、残っているのは商業登記記述式を完成させることでしたので、安心保証プランを活用した3年目はこれを中心に、記述式の訓練を優先して行いました。
まずは商業登記の「【中級】記述式解法マスター講義」を聴きながら、『記述式ハイパートレーニング』を1周させました。それと並行して、不動産登記の記述式については、『記述式ハイパートレーニング』をもう一度やり直すとともに、過去の答練の問題を解きなおしました。問題を解きながら、『合格書式マニュアル』については常に見返すようにしました。
年が明けると実力完成総合答練が始まります。それまでは時間がかかってもいいので何とか問題を解き終えるという感じでしたが、この年からは時間を計りながら全体的な時間配分を考えつつ解くように心掛けました。ただし、回によっては時間が足りず、商業登記記述式の途中で時間切れとなることが多かったように思います。なお、私は本試験も含め、すべての問題を順番どおりに解いていました。
3年目の令和6年度司法書士試験の受験の頃には、全体的に一通り終えた実感がありましたので、うまくいけばいいなとは思っていましたが不合格でした。敗因としては、とにかく時間が足りなくなること、すなわち解く時間が遅いので終わらなかったことが挙げられます。特にこの年から配点が2倍になった記述式の解答時間がどうにも足りませんでした。択一式については前回よりも復習した分上乗せができていたため、基準点よりも10問程度多く正解することはできましたが、記述式は基準点に届きませんでした。
年齢的に、ただ暗記しても翌日には忘れてしまうような状態でしたので、理解に努める勉強法をとっていました。本番の解答においても、問題文を丁寧に読み、問われている内容を頭の中に整理する必要がありましたので、択一式で時間を短縮させることはなかなか難しいものがありました。それに加え、記述式を解く際に、答案構成用紙を活用していたため、絶対的に時間をとられていました。
このように、残念ながら安心保証プランの期間中に合格できませんでしたので、やむを得ず「2025年合格目標上級パーフェクトコース」を1年受講することとしました。
4年目 令和7年度司法書士試験(合格)
気力・体力の衰えを感じる50代の受験生としては、この頃はやる気が最もなくなった時期でした。10月の筆記試験合格発表まであまり勉強に身が入らず、とりあえず自分の弱点と思われる民法の講義を少しずつ聴きながら、商業登記の記述式のみ復習していました。合格発表後は、「【上級】上級マスター講義 択一式編」のレジュメを丁寧に読みました。CROSS STUDYは必要に応じて活用しました。
この時期に意識したことは、司法書士試験という実務家養成試験は、記述式ができなければ話にならないので、とにかく記述式の実力を強化することでした。
この時までに、『記述式ハイパートレーニング』は何度か解いていましたが、どうしても本試験の難しさに対応できていない感じがしましたので、他校から出版されている記述式の過去問題集約20年分を年内に一通り解いてみました。本試験の難易度に慣れるとともに、時間感覚を身に着けるにはよかったと思います。
また、不動産登記・商業登記ともに言えることですが、記述式問題を解く際に答案構成を別紙に書いているようでは間に合わないので、答案構成用紙は使用せず、なるべく問題冊子に書き込む形で論点を整理し、解答するように心掛けました。この方針転換は、実は合格した年の春からでしたので、実際にはあまり慣れないうちに終わってしまったのですが、もっと早くから意識していればよかったと思っています。
4年目の令和7年度司法書士試験受験になりますと、だんだんと受験慣れが生じてきますので、マンネリ化しないようにそろそろ区切りをつける必要がありました。とはいえ、記述式の強化と答練を中心とした全体の復習を行った以外は特に新しいことはできませんでした。
合格した令和7年度試験においては、択一式は例年通りといった感じでした。記述式については、不動産登記においてよくわからない部分もありながら、枠ずれなく解答できました。苦手意識の多少あった商業登記は、結構努力したつもりでしたが、結局のところ時間が足りず不本意な結果でした。最終的に記述式の基準点をいくらか超えたため、総合でも合格点に達することができました。司法書士試験に合格するまで約3000時間の勉強が必要と巷では言われていますが、私の場合も、なんだかんだ4000時間弱はかかりました。
合格の秘訣
司法書士試験は、記述式も択一式も両方疎かにできない試験です。記述式が得意になるには択一式の理解が前提となりますので、まずは択一式を得意にする必要があると思います。私が択一式問題を比較的安定して得点できるようになった理由は、『択一六法』の活用のおかげだと思っています。
仕事柄、馴染みのあった不動産登記法を除き、「【初級】基本マスター講義 択一式編・記述式編(基本講義)」はほぼ初めて聞くことばかりでしたので、全体のイメージが湧くように心掛けて聴きました。細かい内容はよく分からないままでした。そしてその後に続く「【中級】択一六法マスター講義」は、『択一六法』を活用した逐条解説のような講義です。ここで古川先生の話した内容を、都度動画を止めながら『択一六法』に書き込んでいくようにしたのですが、これが条文理解と正答率向上に大きく役立ったと思います。「この『択一六法』は合格後もきっと活用するだろう」と思いながら、内容を充実させていきました。
最後に
苦しい時期もありましたが、合格することができ、今後は実務にまい進すべく、さらに勉強を続けていかなければならないと気持ちを新たにしているところです。合格までの道のりはそれなりに長いものでしたが、その間のクレアールの講師の皆様、そして家族の心遣いには大変感謝しています。
司法書士試験は、確かに合格率が低く難しい試験とは思いますが、正しい勉強を続けていけば着実に合格に近づく試験だと思います。何事も「諦めたら試合終了」という精神で、受験生・合格者ともに今後とも切磋琢磨していけたらと思います。