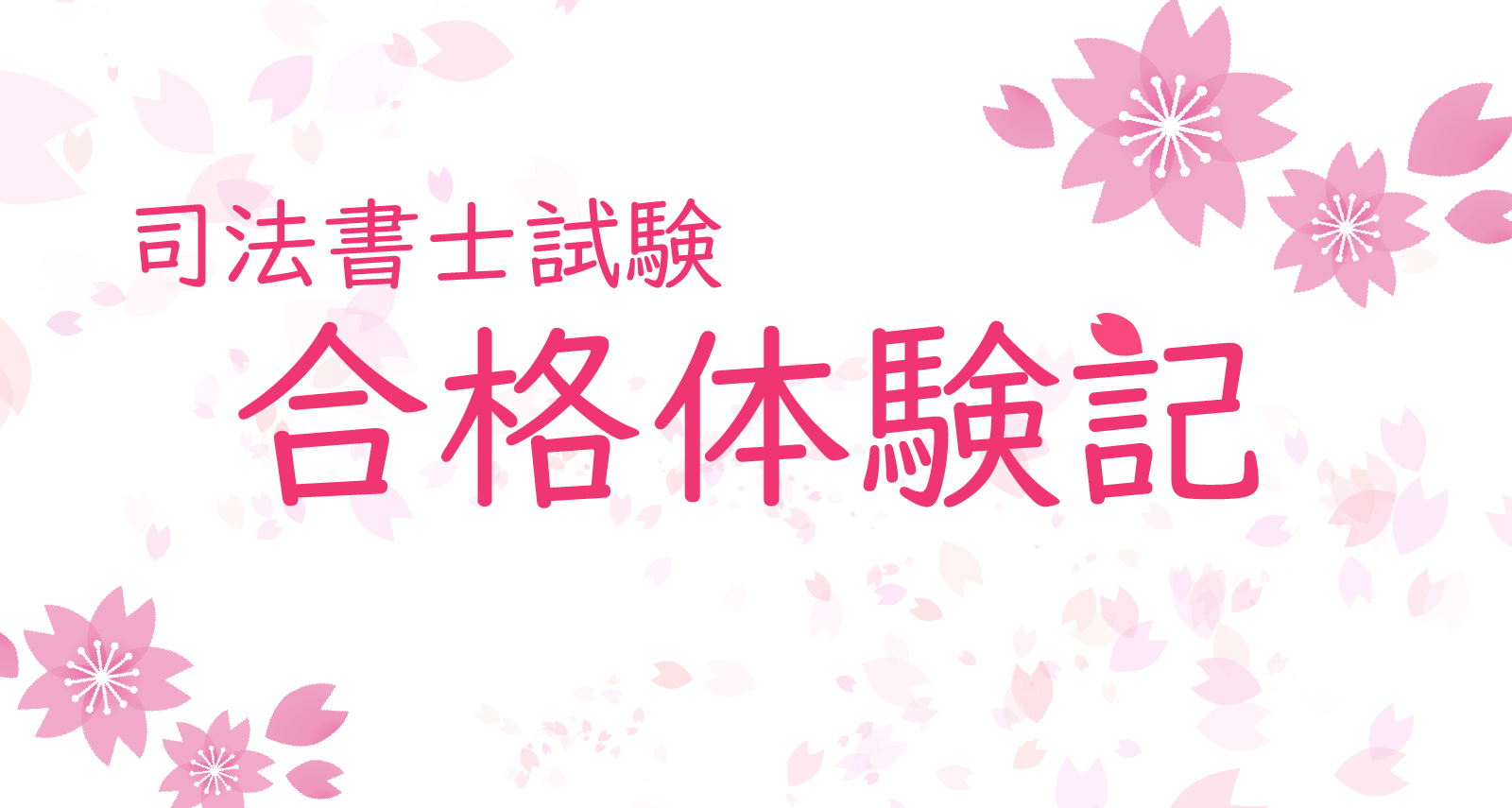川瀬 明久さん
受講コース:上級パーフェクトコース
なぜ司法書士資格を目指したか
私は保険会社の営業職です。当時コロナ禍で一気に使える時間が増えたことにより、この機会に資格の勉強でも始めようと思って軽い気持ちで行政書士の勉強に取り組みました。結果は4か月での合格。これに味を占めて司法書士へと進んだのがきっかけでした。
なぜクレアールを選んだか
約1年半、市販の参考書と問題集をひたすら繰り返し、令和4年度の初受験では基準点をギリギリ突破、しかし記述式に関しては完全に甘くみていて、2週間位参考書にざっと目を通しただけでの受験(本試験でボールペンを使用することも知らなくて)、当然不合格となりました。
そこで記述式対策なのですが、どこから手を付ければ良いかわからず結局独学では無理と判断し、クレアールの「2023年合格目標 中上級パーフェクトAコース」に申し込みました。
クレアールを選んだのは、自分のペースで学習ができる通信教育を選ぶことが前提で、その中でも難関系の資格に強く、老舗のイメージがあったからです(「間違いはないだろう」位の軽い判断でしたが…)。
クレアール申し込み後の受験生活について
クレアールに申込み後の令和5年度は、模試ではBランク、ある程度の力がついたと思って試験に挑んだのですが、あろうことか試験当日に乗る電車を間違えてしまって受験出来ず。
意を決して挑んだ令和6年度は、不動産登記記述式で失敗して記述式基準点割れ。
さすがに精神的にきつくなる中、ここで初めて他社の受験相談も受けながら反省点を絞り込んで令和7年度の対策をすることにしました。
令和7年度司法書士試験対策について
行ったのは、まず不動産登記記述式対策。
これまでは事実関係の正確な把握が甘くても字面を追うだけで記述式を進める傾向があったため、令和6年度の本試験のように、事実関係の材料をイレギュラーな形で提供されるとたちまち筆が止まってしまっていました。
これを解消するためにとにかくひたすら色々なタイプの問題を経験したい、と思い、またクレアールの記述式問題は比較的事実関係が整然と提供される傾向がある、と感じたため、他社の問題集や答練、模試などにも出来るだけ取り組むようにしました。
次に時間のマネジメント。
周知のとおり午後はとにかく時間が足りません。中でも予測出来ないのが記述式に掛かる時間(ここでも特に不動産登記法)だと思います。この不安を解消するために先に記述式を解くことにして、「択一式は最低45分有れば何とかなると思えるようにしよう」と考えました(択一式の時短は出来ても記述式の時短は不可能と考えていたから)。その結果本試験では記述式終了時点で50分残しだったのですが、慌てずに対応することができました。
最後に得点に関してですが、午前択一式で30問以上、記述式は最低7割必須、午後択一式は午前と併せて8割、これ位の得点を解くことが出来れば合格できる、と考えるようにしました。
こんな風に考えながら答練、公開模試などを受けていくうちに、次第に強い手ごたえを感じるようになっていった様に思います。
特に公開模試はクレアールのみならず他校のものも合わせて受験した回数は11回。
これには当然賛否両論あるかと思いますが、自分の中では経験値が上がったことに加え、本番の拘束時間の長さに対するアレルギーが少なくて済んだ、という副産物もあったように思います。
クレアールでの3年間の学習について
クレアールでは3年間お世話になった訳ですが、初年度は「中上級パーフェクトAコース」、2~3年目は「上級パーフェクトコース」でした。
初年度
択一式についてはある程度基準点レベルの力が身についている中で、理解、精度を高めたい、また新しい知識を身に着けたい、という意識で受講しました。
「【中級】択一六法マスター講義」の受講、過去問の擦り直しに終始しましたが、特に「択一六法マスター講義」については条文を中心に講義を進めていくため、条文に親しむ習慣が身につく、という効果はその後の学習においても大変大きな意味を持つものであった、と思っています。またこの講義のおかげで、これまで過去問知識として細切れになっていた知識がつながりを持った知識になり、科目への理解がより深まっていった、と感じています。その講義内容が細分化されていて、理解が浅い部分についてはその部分だけ繰り返し学習できる、というのもありがたいものでした(但し索引にある程度の幅があるため、自分の知りたい部分にピンポイントでたどり着くために結構時間がかかる、というジレンマが有りましたが…)。
記述式については、ほとんど初学からのスタートでした。「【中級】記述式解法マスター講義」で解法を学び、『合格書式マニュアル』でひな形を覚えて、『記述式ハイパートレーニング』等で実践力を養っていく、という定番の学習スタイルです。
最初のころはなかなかとっつきづらく、辛さが先に立ってしまう学習状況だったのですが、ひな形の学習が進んで、問題を解く中でひな形をスムーズに思い出すことが出来る様になってきたころから、一気に苦手な感じが減っていったように思います。
下書きについては、講義での解法の一部にどうしてもぬぐえない違和感を覚えて、自分なりに少し変更した解法で初期のころから学習をし、その後随時マイナーチェンジを重ねていきました(最後はなかなか人には見せられない、自分にしかわからない代物になってしまいましたが…)。
2年目
「【上級】上級マスター講義 択一式編」の視聴が中心でしたが、そのレジュメについては非常にコンパクトにまとまっており、自分なりにマーカーをひいたり、他で仕入れた重要知識を書き加えたりして、手元の便利なテキストとして大変重宝しました。
それ以外は、過去問、CROSS STUDYの繰り返し、『記述式ハイパートレーニング』、答練問題の繰り返しに終始、特に記述式についてはなかなか抵抗感が拭えないものがあったので、朝の目覚めのあとすぐとか、仕事で疲れている時とかにあえて問題を解いてみる、というようなことをしていました。
3年目
前年度の反省から、記述式対策としてできる限り多くのさまざまな問題を解いてみる、ということをテーマにしました。
より細かく、より多様な問題に取り組みたい、という要望に応じて紹介していただいた市販の問題集にとり組み、そこで得たポイントを『合格書式マニュアル』に書き込んだりしていました。その結果、これまでなんとなく経験則で解いていた『記述式ハイパートレーニング』や答練等も、実は細部にまで理解が及んでいなかったことに気づき、細かいことを見逃さずにすべてのことに理由とルールがある、と考えることでかなりの実力向上につながったのだと感じています。
そうなるとあとは、不動産登記においては「なにが起きているのか」を正確に掴むこと、商業登記においては解答スピード向上と、取り組むべき対策が明確になったことも大きかった、と思います。
この間、択一式対策としては新しいことに取り組むことなく、CROSS STUDYや一問一答形式の市販の教材を繰り返すことで実力維持を意識していました。
午後の部の解答の順番について
先に書いた通り、私は記述式から先に取り組むことにしていました(合格年度)。
理由は、記述式の目安は2時間である、とは言うものの、答練や模試では1時間40分位の時もあれば2時間を少し(10分位)超えることもありました。私は決して記述式の解答スピードが速いほうだと思っておらず、また時間が足りない場合に記述式の解答を速める方法はないと思っています。一方、午後の択一式は目安が1時間と言うものの、「解法を工夫することで時間短縮が可能である」と考えていた、というのが理由です。
実際答練や模試でそれを意識して取り組んだところ、午後択一式は45分有れば少なくとも基準点越えは可能、という実感を持つに至り、その後は落ち着いて記述式の解答を進めることができていたと思います。
また得点戦略としても利点があります。
先に書いた「なにが起きているのか」を間違わずに把握して解答すれば最低でも7割の得点を得られるだろうし、失敗すると基準点割れのリスクがある、というのが記述式の試験だと思っています。そうすると、失敗しなければ(記述式の基準点が約5割だとすると)28点程度の基準点上乗せが得られる訳です。
午後択一式に注力してもなかなかこれだけの基準点上乗せは見込めないことを考慮すれば、記述式対策に注力した上で本試験において時間に追われず記述式問題を解答することが最も利に適っている、と思っています。
CROSS STUDYについて
CROSS STUDYはリリースされてすぐにその時公開されている問題を一通り解きました。その後はもっぱら知識の確認用として、通勤途中や会議の合間など、色々なシチュエーションで利用させていただきました。
なかでもランダム出題にすることで、紙の問題集ではどうしても並びで覚えてしまっている知識の定着に役立った、と感じています。
モチベーション対策について
この試験は「やはり難しい試験だ」と今から振り返っても改めてそう思います。
学習初期は当然のことながらモチベーションが高く、学習する内容も新鮮なものばかりで学習すればするほど成長している実感があるものですが、一通りの学習を終えてある程度の実力を得た頃からが本当に大変になるのだと感じています。
学習内容に新鮮味がなくなり、苦手な部分は本来理解が難しい部分であるか個人的に不得手な部分な訳ですし、何年もやっていると自虐的にもなってきますし…
私もモチベーション維持には相当苦しみましたが、解消法とは言えないかもしれませんが、「この教材をいつまでにやりきる」といった短期目標を常に持っておくということと、「自分の苦手な部分はどこなのか、どうすれば解消されるのか」を常に見据えておくことが大事だと思ってきました。
それらを知るためには、「人の意見を聞くこと」が非常に大切だとも感じました。そして続けていれば解けない問題が解けるようになったり、答練などで思ったより良い点数が取れたりして、成長が実感出来てポジティブな意欲がよみがえってくるタイミングが定期的に必ずやってくる、というのが実感です。
これから合格を目指す受験生の皆様へ
今になって振り返れば、クレアールのカリキュラムは司法書士試験に合格するために必要な知識を効率よく学習するための、とても良い内容だったと思います。コースに応じて送られてくる教材に対して真面目に取り組めば、かなりの確率で合格レベルまで到達できるものだと感じています。
しかし、ここでお伝えしたいのは、あくまで「合格レベル=合格」ではないということです。
公開模試などで一般的に「合格推定」とされるBランク以上を取れば、一定の安心感を得ることができます。しかし、その中にも不合格に終わってしまう方が少なからずいるという現実を、忘れてはならないと思います。「どんな試験でも模試とはそういうもの」と言ってしまえばそれまでですが、受験者にとっては「そのどちらに入るか」で、あまりにも大きな違いが生まれてしまいます。
そこで、是非学習相談を大いに活用することをお勧めします。私自身、合格年度はクレアールのスタッフの方に何度か電話で相談に乗ってもらいましたし(イレギュラーかも知れない、と思いながら…)、他社の無料相談も積極的に利用しました。
他人からの助言によって客観的な視点を得ることは、間違いなく現在の自分を理解するうえで大いに役立ちました。また、「合格レベル」から「合格」へと一歩抜け出すためのヒントを得ることができたと思っています。
人それぞれ「なにをすべきか」は違うとは思いますが、そこにかけるエネルギーはそれまでの学習で費やしてきたものと比べると、ごくわずかなものだと思います。そのわずかな工夫が合格確率を大きく引き上げる、というのが私の経験上感じたことでしたので、僭越ながら記させていただきました。
最後に
私は司法書士試験の学習を始めてから結局約4年半、結構長かっただけに合格できたことにはそれなりの達成感があり、また、もっと早いうちに人の意見を聞いてより適切な学習計画を立てることができていたらもっと早く合格出来ていたかもしれない、という反省もあります。
色々思うところはありますが、一つのことにエネルギーを注いだことは貴重な経験だと思いますし、今はこの経験を経て新しくなる時間を大いに楽しみにしているところです。
最後になりましたが、常に寄り添っていただき、応援していただいたクレアールのスタッフの皆様には本当に感謝申し上げます。
そして、これから学習を始める方、来年の合格を目指している方、是非今の学習計画を順調に進められ、試験当日にはその実力をいかんなく発揮されることを心よりお祈り申し上げます。