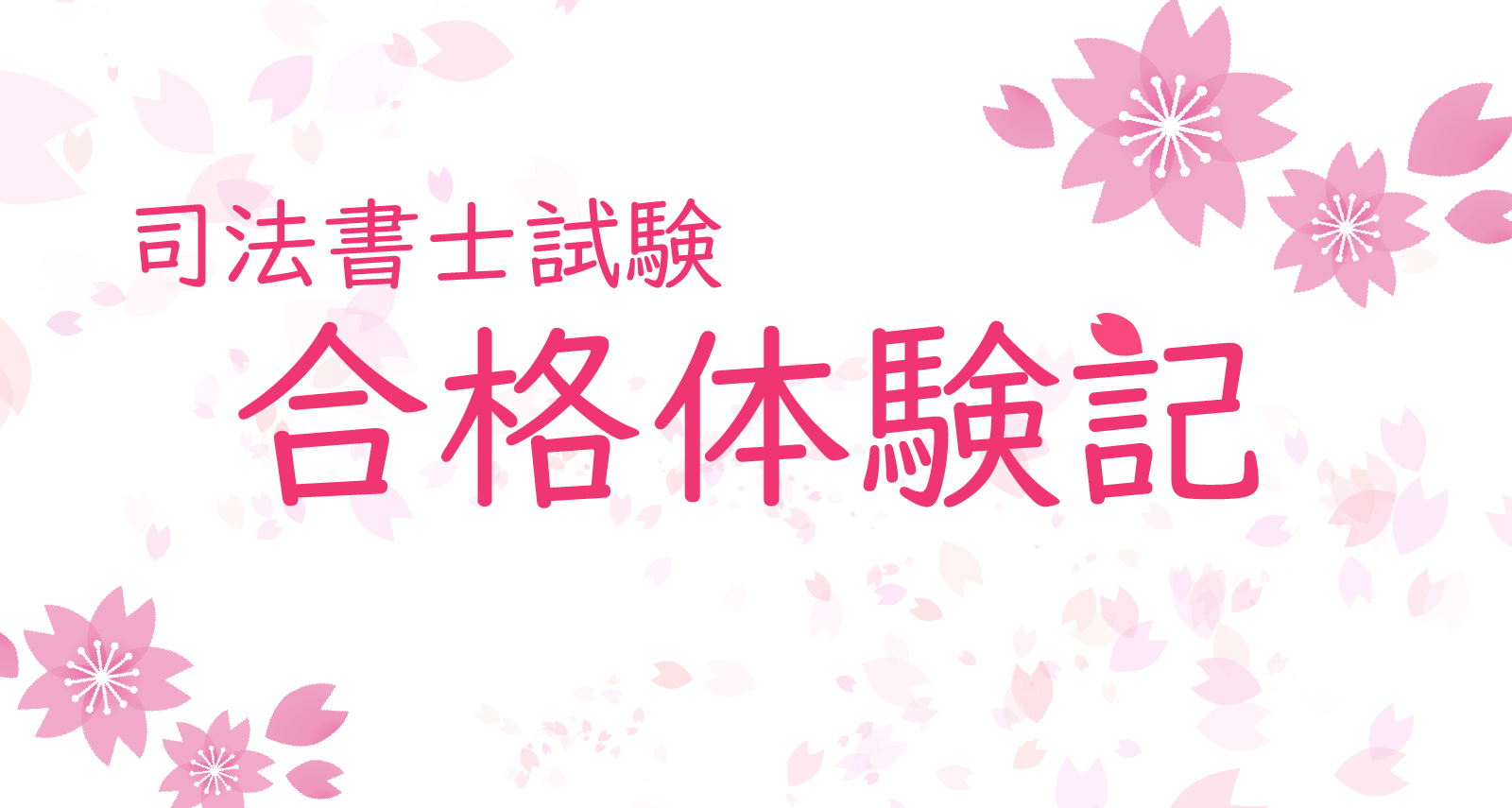F.Hさん
受講コース:中上級パーフェクトBコース
なぜ司法書士資格を目指したか
令和7年11月4日午後4時、私の長かった受験生活がようやく終わりました。令和元年の初受験から7回目の受験でした。
私は、地方機関の国家公務員として働いていました。50歳を超えた頃から定年後何をするか考えるようになりました。65歳までは再雇用可能とのことでしたが、いろいろと思うところがあり、60歳で退職しようと心に決めていました。ただ、私の職場には再就職のあっせんはなく、自ら退職後の仕事を探す必要がありました。私は何か資格を取れば就職に有利になるのではないかと考え、社会福祉士の資格を取りましたが、福祉未経験者にとっては、この資格での再就職は厳しそうでした。
私の職場では法律に接することが多かったため、法律系の資格であれば、これまでの職歴を生かして再就職できるのではないかと考え、司法書士の資格に挑戦することにしたのです。その時点で定年まで5年あったので、定年までに資格を取得し、引き続きどこかに就職しようと考えたのです。
予備校選びのポイント
インターネットで司法書士の試験科目の概要などを調べてみると、民法は過去に学んだことがあるものの、大昔の話であり、その他の科目はほぼ初見の科目ばかりでした。当初は独学も選択肢の1つでしたが、科目の多さや受験対策を考えると、予備校の講座を受けることが合格への早道だと思い、予備校を探すことにしました。大手の予備校以外に、クレアールの司法書士講座の情報もインターネット上で目にしました。
大手の予備校には安心感がありましたが、当時、私はまだ働いていたため、1コマ3時間の授業が普通にある講座はとても消化できないと思い、クレアールは価格も手頃であり、答練・模試などの演習プログラムも付属していたことから、クレアールの講座を受けることにしたのです。初級講座から受講し始め、その安心保証プラン、中上級講座とその安心保証プランと続けて受講し、その間、令和元年から4回、本試験を受験しました。
私の受験記録
午前の部の択一式は2回目から基準点を超えるようになりましたが、午後の部の択一式は4回目まで基準点を超えることはありませんでした。今思えば、4回目までの受験の間は、クレアールのカリキュラムを漫然とこなすだけで、自分から積極的に知識の徹底を図るという作業が十分にできていなかったと思っています。
ひととおりクレアール講座の受講を終えてしまい、次にどうするかを考えなければなりませんでした。私はこの年に定年退職となりましたが、専業で受験勉強を続けるつもりでした。私は、一人で計画的に勉強することは性格からして難しく、ペースメイクのために講座を受講する必要があると自覚していました。その頃はまた、法改正が相次いでいたため、それまで使用していたクレアールの教材は訂正や追加の紙でつぎはぎだらけでした。
そこで、私は心機一転、他校の基礎講座を受講することにしました。当該講座もクレアールの講座と同様、短時間の講義と該当箇所の過去問演習を組み合わせたもので、集中力のない私には最適なものでした。同講座を受け終わった令和5年の本試験では、午前、午後ともにともに択一式の基準点を大幅に超えることができましたが、記述式が基準点に届かず不合格となりました。この講座の受講で基準点を大幅に超えることができたことや、再受講の割引があったことから、もう1度同じ講座を受講しましたが、翌令和6年の本試験でも記述式が基準点に届かず、不合格となりました。
CROSS STUDYとの出会い
ここで私の2回目の転機となります。択一式は基準点を超えるようになったため、記述式の勉強に力を入れなければならないと思いました。しかし、合格者の体験記や学習サイトを見ていると、記述式の対策ばかりしていると択一式の対策がおろそかになり、それまで基準点を超えていた択一式で足をすくわれることがある、と強調されていました。そのため、記述式対策と並行して、択一式対策も最低限は続ける必要があると判断しました。
そこでクレアールの講座案内を見てみると、CROSS STUDYという新しい学習ツールが開発され、記憶が保持できるよう計画的に問題演習ができるという触れ込みであり、これは択一式の演習教材として使えそうだと思い、再度クレアールの中上級講座を申し込むことにしたのです。このときには、「今年で最後にしたい」との思いから、安心保証プランは申し込みませんでした。
当初、紙の問題集がないことに不安もありましたが、CROSS STUDYを使い始めてみると、紙の問題集の必要性は一切感じなくなりました。最初は講義にあわせて一通り問題を解いた後、午前科目、午後科目、全科目などを「ランダム出題」に設定して、毎日150問から200問解くようにしました。
そして、少しでも記憶の曖昧な問題は『択一六法』に戻って確認し、『択一六法』に記載のないものは必要に応じて書き入れるなどしました。また、CROSS STUDYのメモ欄に知識の整理や似た問題との区別の視点などを書き入れ、再度問題が表示されたときに参考にしました。
その他いろいろな設定を試してみましたが、上手く使いこなしたとは言い難いところです。しかしながら、このCROSS STUDYは最強の過去問学習ツールだと思います。定期的に過去に演習した問題が表示されたり、確認テストが定期的に送られてくるなど、記憶を定着させる工夫が随所にみられるばかりか、スマホ1つで勉強でき、細切れ時間を活用するには持ってこいの教材です。
また、クレアールには『択一六法』という定評のあるまとめ教材もあることから、CROSS STUDYと併用することで効果がいっそう高まることと思います。
事実、CROSS STUDYを使用するようになってから択一式の成績はさらに安定するようになりました。お世辞ではなく、CROSS STUDYはデジタル教材による学習環境を一段高めたと思っています。
記述式対策について
さて、次は記述式対策です。2年連続で記述式が基準点を超えず、記述式には本当に悩まされました。原因は、やはりひな形の記憶の不十分さと、問題を解く際にすぐにテンパってしまい、事実関係や指示記載の読み飛ばしがしばしば発生することでした。
クレアールや先ほどの他校の基礎講座以外にも、記述式対策講座を試してみましたが、自分の努力不足もあるのでしょう、うまくいきませんでした。結局、最終年には時間の許す限り、クレアールの答練・模試や『記述式ハイパートレーニング』に加え、他校の答練を受けたり、その他市販の問題集を解いたり、とにかく数をこなしました。
正直言って、記述式対策について「こうすれば高得点を取れる」と胸を張って言えることは何もありません。本年の本試験でも、商業登記で読み飛ばしをしてしまい、筆記試験の合格発表まで、半分以上落ちた気でいました。記述式対策に関して言えることは、迷いなく瞬時にかつ正確にひな形を書けるようにすること、また事実関係や記載指示を正確に把握できるよう工夫することしかないと思います。様々な予備校講師が考案された記述式対策講座のやり方をそのまま踏襲してうまくいく人もいらっしゃるとは思いますが、私はうまくいきませんでした。試行錯誤して自分なりのやり方を編み出すしかないと思います。
また、記述式の配点が令和6年度の試験から上がったことから、午後の部では記述式に十分な時間をとる必要があります。昔から午後の部は「時間との闘い」と言われていますが、記述式に十分な時間を確保するには、択一式で迷っている暇はありません。そのため、午後科目は特に、過去問を覚え込むまで繰り返す作業が不可欠です。過去問と同様の肢を瞬時に判断できるようになるまで演習を繰り返すことが必要です。もう分かっていると思っている部分を何度も何度も繰り返す作業はなかなか苦痛ですが、普通の受験生には、これなくして高得点は望めないと思います。私もCROSS STUDYの繰り返しで、今年の本試験(午後の部の択一式)でも所要50分で29問正解できました。
ベテラン受験生の方へ
ベテラン受験生にとっては、繰り返す作業はなかなかつらいと思いますが、今回が最後だと思って、なんとか踏ん張ってください。
また、社会人の兼業受験生の方にとっては、仕事や家庭の状況に応じ、受験勉強だけに専念できる環境にある方ばかりではないと思います。そのような方にとっては、受験期間がある程度長引くこともやむを得ないことだと思います。ただ、勉強が惰性になってしまうと合格が遠のくことは間違いありません。仕事や家庭に時間を取られることもあると思いますが、逆にそれも一種の気分転換だと思って、合格することへのモチベーションを切らさず、スキマ時間を無駄にせず上手く活用して合格を勝ち取ってください。
ただでさえ勉強時間が少ないのに、娯楽やSNSなどで時間を費やすことは、間違いなく合格を長引かせます。
最後に
私には、「こうすれば早く合格できる」「このやり方をすれば間違いなく合格点を取れる」と胸を張って提案できるようなものは何もありません。何回もテキストと過去問を繰り返したとしか言えません。どちらかというと、泥縄で勉強していたらなんとか合格できた、というのが正直な気持ちです。
率直に言って、私が今年合格できたのは、問題との相性など運が良かったということもあると思います。模試で常に「絶対合格」の判定をもらっていたわけでもありませんし、昨年までと何が違うかといわれても、これといったことは思い浮かびません。
全受験生の約5%しか受からない試験というのは、一部の成績優秀者を除いて、そういうものだと思います。何年も合格できないという方は心理的につらいと思いますが、どうか諦めず最後まで頑張ってください。
私は、定年退職後すぐに司法書士の資格を生かして仕事をするという当初の計画どおりにはいかず、今後、この年齢から仕事があるかどうかも分かりませんが、やっと取れた資格ですから、なんとか生かしたいと思います。