問題1 A所有の甲土地上に乙建物が存在するところ、乙建物の所有者Bが未登記のままこれをCに譲渡した。この場合に、Aが所有権に基づく物権的請求権を行使して建物収去土地明渡請求をするときは、Aは、BとCのいずれをも相手方とすることができる。○か×か?

誤り。土地所有権に基づく物権的請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには、現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである。したがって、未登記建物の所有者Bが未登記のままこれをCに譲渡した場合には、これにより確定的に所有権を失うことになる(最判平6.2.8)。したがって、AはCを相手方としなければならない。【平18-11-ア】
問題2 A所有の甲土地上に乙建物が存在するところ、乙建物は、Bが建築して所有しているが、C名義で所有権の保存の登記がされており、Cは、これまで乙建物の所有権を取得したことがない。この場合に、Aが所有権に基づく物権的請求権を行使して建物収去土地明渡請求をするときは、Aは、乙建物の実質的な所有者であるBのほか、登記名義人であるCをも相手方とすることができる。○か×か?

誤り。本肢のCは乙建物の所有名義人となっているが、実際には乙建物を所有したことがなく、単に自己名義の所有権取得の登記を有するにすぎない場合であるため、Aに対し、建物収去・土地明渡しの義務を負わない(最判平6.2.8)。したがって、原則どおり現実に乙建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害しているBを相手方としなければならず、Cを相手方とすることはできない。【平18-11-エ】
問題3 Aがその所有する甲土地を深く掘り下げたために隣接するB所有の乙土地との間で段差が生じて乙土地の一部が甲土地に崩れ落ちる危険が発生した場合には、Aが甲土地をCに譲渡し、所有権の移転の登記をしたときであっても、Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づく妨害予防請求権を行使することができる。○か×か?

誤り。将来、所有権の行使が妨害されるおそれのある場合に、その妨害の予防を請求する所有者の権利を、妨害予防請求権という。乙土地の一部が甲土地に崩れ落ちる危険を生じさせたのが前所有者のAであっても、人為的に危険状態が作り出された以上、現所有者Cが危険状態をそのままに放置していることは隣地の所有権を侵害するものであり、したがって現所有者Cが予防工事をなす義務を負うとしている(大判昭7.11.9)。よって、BはAに対し、乙土地の所有権に基づく妨害予防請求権を行使することはできない。【平24-8-5】
問題4 Aがその所有する甲土地をBに賃貸した後、BがAの承諾を得ることなく甲土地をCに転貸した場合には、Aは、Cに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して、甲土地のBへの明渡しを求めることはできるが、Aへの明渡しを求めることはできない。○か×か?

誤り。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができず(民612条1項)、承諾のない無断転貸は、賃貸人に対して何ら効力を生じない。したがって、Aは、Cに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して、A又はBへの明渡しを求めることができる(最判昭26.4.27)。【平29-7-ウ】
問題5 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができない。○か×か?

誤り。所有権に基づく返還請求権の相手方は、現に目的物を占有する者であるが、直接占有者だけでなく、間接占有者もそれに含まれる(大判昭13.1.28)。したがって、Aは、甲土地をCに賃貸して甲土地の間接占有者であるBに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができる。【平29-7-エ】
問題6 AとBとが甲不動産を共有していたところ、Aは、その共有持分をCに譲渡したが、その旨の持分移転登記をしていない。この場合において、Cは、Bに対し、甲不動産の共有持分の取得を対抗することができる。○か×か?

誤り。不動産の共有者の1人が自己の持分を第三者に譲渡した場合、譲受人にとって譲渡人以外の共有者は民法177条の第三者にあたる(最判昭46.6.18)。よって譲受人Cはもう一方の共有者Bに対して登記なくして当該不動産の共有部分の取得を対抗できない。【平16-11-ア改】
問題7 Aが所有する土地をBに売却した場合において、AがBとの間の売買契約をBの詐欺を理由に取り消した後、AがCにこの土地を売却し、その後、Cが死亡し、Dが単独で相続したとき、Dは、登記をしていなくても、所有権の取得をAに対抗することができる。○か×か?

正しい。民法177条の第三者とは、当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいう。AとCは売買契約の当事者であり、Cの相続人であるDは、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民896条本文)ので、DはCの当事者としての地位を承継することになる。したがって、AとDは当事者の関係に立ち、Dは登記をしていなくても所有権の取得をAに対抗できる。【平20-9-ア改】
問題8 Aが所有する土地をBに売却した場合において、CがAからその土地を賃借し、賃貸借の対抗要件を備えていたときは、Bは、登記をしなければ、Cに対して賃貸人たる地位を主張することができない。○か×か?

正しい。賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する(民605条の2第1項)。この場合、賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない(民605条の2第3項、最判昭49.3.19)。賃料の二重払いの危険を避けるためである。【平20-9-ウ】
問題9 Aは、B所有の甲不動産を買い受けたが、その所有権の移転の登記がされない間に、甲不動産がBからCに譲渡されて所有権の移転の登記がされ、更にCからDに譲渡され、Dが所有権の移転の登記をした。この場合において、Cが背信的悪意者に当たるときでも、Dは、Aとの関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り、甲不動産の所有権の取得をAに対抗することができる。○か×か?

正しい。不動産が譲渡され、その登記が未了の間に当該不動産が二重に譲渡され、さらに第二の買主から転得者に転売され、登記が完了した場合に、たとえ第二の買主が背信的悪意者に当たるとしても、第一の買主に対する関係で転得者自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、転得者はその不動産の取得を第一の買主に対抗することができる(最判平8.10.29)。背信的悪意者が正当な利益を有する第三者に当たらないとして民177条の「第三者」から排除される所以は、第一譲受人の売買等に後れて不動産を取得し登記を経由した者が登記を経ていない第一譲受人に対してその登記の欠缺を主張することが、その取得の経緯等に照らし信義則に反して許されないということにあるのであって、登記を経由した者がこの法理によって「第三者」から排除されるかどうかは、その者と第一譲受人との間で相対的に判断されるべき事柄であるからである。【平24-7-ウ】
問題10 Aから袋地(他人の土地に囲まれて公道に通じない土地)を買い受けたBは、その袋地について所有権の移転の登記をしていなくても、囲繞地(袋地を囲んでいる土地)の全部を所有するCに対し、公道に至るため、その囲繞地の通行権を主張することができる。○か×か?

正しい。袋地の所有権を取得した者は、所有権移転登記を経由していなくても、袋地を囲んでいる他の土地の所有者及びその利用権者に対して、公道に至るためにその土地を通行する権利を主張することができる(最判昭47.4.14)。なぜなら、民法210条は公道に至るための他の土地の所有者に一定範囲の通行受忍義務を課して、袋地の効用を全うさせることを目的としており、不動産取引の安全保護を目的とした公示制度とは関係がないからである。【平24-7-オ】
問題11 Aの所有する甲土地を承役地とし、Bの所有する乙土地を要役地とする通行地役権が設定されたが、その旨の登記がされない間に甲土地がCに譲渡された。この場合において、譲渡の時に、甲土地がBによって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、Cがそのことを認識していたときであっても、Cが通行地役権が設定されていることを知らなかったときは、Bは、Cに対し、通行地役権を主張することができない。○か×か?
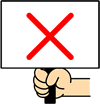
誤り。通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない(最判平10.2.13)。したがって、本肢の場合、Bは、Cに対し、通行地役権を主張することができる。【平28-7-ウ】
問題12 Aはその所有する未登記の甲建物をBに売り渡したが、その旨の所有権の移転の登記がされない間に、Aが甲建物についてA名義で所有権の保存の登記をし、Cを抵当権者とする抵当権を設定してその旨の登記をした場合には、Cは、Bに対し、甲建物の抵当権を主張することができない。○か×か?

誤り。不動産の取得については、当該不動産が未登記であっても、民法177条の適用があり、取得者は、その旨の登記を経なければ、取得後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない(最判昭57.2.18)。したがって、本肢の場合、抵当権を設定してその旨の登記をしたCは、Bに対し、甲建物の抵当権を主張することができる。【平28-7-オ】
問題13 AがBと通謀してA所有の甲土地をBに売り渡した旨仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、AがBに対して真に甲土地を売り渡した場合であっても、その前にAがCに対しても甲土地を売り渡していたときは、Bは、Cに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができない。○か×か?

誤り。仮装の売買契約に基づき不動産の所有権移転登記を受けた者が、その後真実の売買契約によりその所有権を取得し、登記が現在の実体的権利状態と合致するに至ったときは、その時以後、当該買主は、不動産の所有権の取得を第三者に対抗することができる(最判昭29.1.28)。したがって、既に所有権移転登記を備えているBは、Cに対し、甲土地の所有権の取得を主張することができる。【平29-8-ウ】
問題14 A所有の甲土地について、Bの取得時効が完成した後その旨の所有権の移転の登記がされる前に、CがAから抵当権の設定を受けてその旨の抵当権の設定の登記がされた場合には、Bが当該抵当権の設定の登記後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときであっても、Cの抵当権が消滅することはない。○か×か?

誤り。不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続し、その期間の経過後に取得時効を援用したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、上記占有者が、上記不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅する(最判平24.3.16)。【平29-8-ア】
問題15 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売した。その後、AB間の売買契約が合意解除された場合、Cは、Bから所有権の移転の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。○か×か?

誤り。当事者の一方が解除権を行使したときは、各当事者は、相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない(民545条1項)。ここにいう「第三者」とは、解除された契約から生じた法律関係を基礎として、解除までに新たな独立した権利を取得した第三者をいい(大判明42.5.14等)、この「第三者」として保護されるためには、権利保護要件として登記を備えていることが要求される(最判昭33.6.14)。したがって、登記を受けていないCは、Aに対し、甲建物の所有権を主張することができない。【平27-7-ウ】
問題16 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移転の登記をした後、Aは、Bの債務不履行を理由にAB間の売買契約を解除した。その後、Bが甲建物をCに転売し、その旨の所有権の移転の登記をした場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる。○か×か?

誤り。解除後の第三者は、民法545条1項ただし書によっては保護されず、解除後の第三者と解除権者とは対抗関係に立つとされているため、登記を備えた者が優先することになる(民177条、最判昭14.7.7)。したがって、登記を受けていないAは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができない。【平27-7-エ】
問題17 甲土地を所有するAが死亡し、その子であるB及びCのために相続の開始があったところ、Aは、生前に、甲土地をBに贈与し、その旨の所有権の移転の登記をしないまま、甲土地をCに遺贈した。この場合において、Cは、甲土地について遺贈を原因とする所有権の移転の登記をしたとしても、Bに対し、甲土地を所有している旨を主張することができない。○か×か?

誤り。被相続人が生前に、ある不動産を相続人の1人に贈与し、他の相続人にも同不動産を遺贈した後、相続が開始したという場合において、贈与と遺贈による物権変動の優劣は、登記の先後で決定されるとされている(最判昭46.11.16)。したがって、Aから甲土地の贈与を受けたBとAから甲土地の遺贈を受けたCとは、甲土地の所有権をめぐる対抗関係にあるため(民177条、最判昭39.3.6)、遺贈を原因とする所有権移転登記をしたCは、Bに対し、甲土地を単独で所有している旨を主張することができる。【平25-7-イ改】
問題18 甲土地を所有するAが死亡し、その子であるB及びCのために相続の開始があったところ、Bが甲土地を単独で所有する旨の遺産分割協議が成立したが、Cは、Bに無断で、自己が甲土地を単独で所有する旨の所有権の移転の登記をした上で、甲土地をDに譲渡し、その旨の所有権の移転の登記をした。この場合において、Bは、Dに対し、甲土地を単独で所有している旨を主張することができる。○か×か?

誤り。遺産分割も民法177条の物権の得喪変更に該当し、遺産分割によって得た権利は、登記しないと第三者に主張できないとする(最判昭46.1.26)。分割により生じた相続分と異なる権利を取得したBは、その旨の登記がなければ、分割後に甲土地につき権利を取得したDに対し、自己の権利の取得を主張することができない。したがって、Bは、Dに対し、甲土地を単独で所有している旨を主張することができない。【平25-7-ウ改】
問題19 Aは、A所有の立木をBに仮装譲渡し、Bは、当該立木に明認方法を施した。その後、AがCに当該立木を譲渡した場合、Cは、明認方法を施さなくても、Bに対し、当該立木の所有権を主張することができる。○か×か?

正しい。虚偽表示による取得者は無権利者であるため、この者に対しては対抗要件たる明認方法なくして立木の所有権を対抗できる(最判昭34.2.12)。【平21-9-イ】
問題20 A所有の土地をBが自己所有の土地と誤信して立木を植栽していたところ、Cが当該立木を伐採して伐木を持ち出した場合には、Aは、Cに対し、当該伐木の所有権を主張することができる。○か×か?

正しい。Bは無権原で立木を植栽しているので、当該立木は土地に付合し、Aの所有となる。(民242条)。したがってAはCに対し、当該伐木の所有権を主張することができる。【平21-9-エ】
問題21 BがAの所有する土地に地上権の設定を受け、その地上権にCのために抵当権を設定した場合において、BがAからその土地を買い受けたときは、地上権は、消滅しない。○か×か?

正しい。地上権者(本肢の場合B)からその地上権について抵当権の設定を受けた者(同C)がいるところ、地上権者Bがその地上権の設定を受けている土地の所有権者(同A)から当該土地を購入した場合、土地所有権者の地位と地上権者の地位が同一に帰するが、地上権は抵当権者Cの抵当権の目的となっているために、混同の例外(民179条1項ただし書)にあたり、消滅しない。【平16-8-ウ】
問題22 Aがその所有する土地に、抵当権者をB、債務者をCとする1番抵当権及び抵当権者をD、債務者をCとする2番抵当権をそれぞれ設定した場合において、Bが単独でAを相続したときは、1番抵当権は、消滅しない。○か×か?

正しい。ある土地の1番抵当権者(本肢の場合B)が土地の所有権者(同A)から当該土地を相続したところ、当該土地に2番抵当権者(同D)がいる場合は、1番抵当権を存続させておくことで2番抵当権に対抗できるから、1番抵当権を消滅させることは土地の所有権を相続した1番抵当権者の利益を損なうので、民法179条1項ただし書により、1番抵当権は消滅しない(大判昭8.3.18)。【平16-8-オ】
問題23 AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2番抵当権の設定を受けたが、Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けていた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は消滅しない。○か×か?

誤り。本肢の事例に民法179条1項を形式的に適用すると、混同の例外として2番抵当権は消滅しないことになる。すなわち、Bの土地につき所有権及び他の物権(2番抵当権)が同一人(A)に帰したときは、その物権(2番抵当権)は消滅する(民179条1項本文)。ただし、その物(土地)が第三者(C)の権利(1番抵当権)の目的となっているときは混同により消滅しないことになる。しかし、そもそも混同の例外は、地位の併存を認める意味のあるものだけを併存させようという趣旨である。したがって、本肢の場合、2番抵当権を併存させても意味がないので、混同により消滅する。【平20-10-イ】
問題24 AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、AがBを単独で相続したときは、Aの抵当権は消滅しない。○か×か?

誤り。債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅する(民520条本文)。本肢のように、AがBを相続してAとBとの間に地位の混同が生じた場合、Aの被担保債権は混同により消滅し、Cが2番抵当権を有していたとしても、付従性によりAの抵当権は消滅する。【平20-10-ウ】

