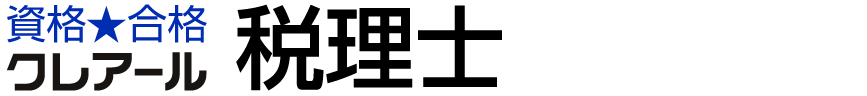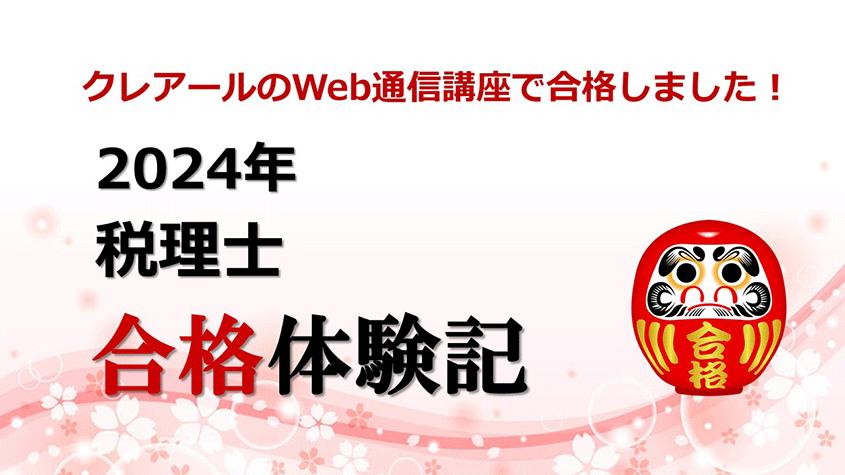S.Fさん(46歳、女性)
【合格科目】財務諸表論(1)
【受講コース】2023・24・25年合格講座 簿記検定トライアル・検定マスター簿財 3級修了者 Web通信
【職業】会社員
【1日の平均学習時間】平日平均4時間
【試験までの総学習時間】800時間
※合格科目のカッコ内の数字は受験回数です。
受験の動機
私自身は、もともと会計とはまったく無縁の研究職をしており、2年前まで簿記の簿の字も知らないような状態でした。
社会人としての経験を積む中で、ビジネスマンの教養として簿記3級ぐらいは勉強しておこうと考え、クレアールを受講したことがきっかけとなりました。
はじめのうちは簿記の仕訳という、慣れない考え方に苦戦しながらも、勉強を進めるうちにその美しさに感動し、さらに簿記2級から簿記1級へと学習を進めていくなかで、税理士試験にも挑戦してみたいと考えるようになりました。
クレアールを選んだ理由
簿記3級から簿記2級までを勉強するにあたり、評判もよく受講料が手軽だったクレアールを選び、簿記2級までは学習開始後3ヶ月でスムーズに合格することができました。
さらに上を目指してみたいと思い、その流れで税理士試験対策にも、クレアールの簿記1級のコースと簿財同時学習のコースがセットになった「簿記検定マスター・簿財アドバンス」を申し込みました。
私の学習方法
学習時間
財務諸表論については、講義の視聴時間や理論暗記時間を含めて、試験までの総学習時間は800時間(1日平均4時間)でした。
そのうち、理論学習と暗記にかけた時間は約200時間です。
計算問題の学習方法
計算問題については、簿記1級まで学習した知識に加え、簿記論との同時学習による相乗効果がかなりありましたので、主に貸借対照表や損益計算書での表示のルールや、注記の仕方など、財務諸表論特有の論点にのみ注力することでほぼ対応することができました。
財務諸表論の学習方法
財務諸表論は授業初回のうちからコツコツと、授業で指定される学習範囲の最低限の理論暗記を積み重ねていったことが、試験直前までずっとアドバンテージになりました。
読む・聞く・書くなどの暗記方法から、自分にあった理論暗記のスタイルを早めに確立し、このぐらいのボリュームならこのぐらいの時間をかければ精度高く暗記できそうだという感覚を養っておいたことが、財務諸表論だけではなく、その後の税法科目の理論暗記にもとても役に立っています。
また、財務諸表論については、公開模試を複数受けた個人的経験から、計算に比べると理論の暗記が追いついていない受験生が多い印象を受けましたので、学習初期から重要理論の暗記を地道に続けていくことで、財務諸表論は上位数%に入ることも難しくないのではないかと思います。
なお、税法科目になると「理論暗記を完璧に仕上げてくる受験生」ばかりと戦うことになりますので、財務諸表論のうちから、とにかく理論を後回しにせずに早め早めにコツコツと取り組む習慣を身に付けておくことは非常に重要だと感じています。
合格までのエピソード
仕事との両立
時間が足りない中、とにかく理論暗記のために、すきま時間を活用することが役に立ちました。
机に座ってじっくり勉強できる時間は計算問題の演習にあて、理論暗記については、覚えるべき理論をスクリーンショットに撮るなどして、すべてスマホで見れるようにし、朝、昼、晩の休憩時間やすきま時間に、1日の中で何度も繰り返し眺めるようにすると早く覚えることができました。
理論暗記をざっくりとでも早めに済ませていたことで、直前期は答練などの計算問題に集中することができましたが、それでも本試験までには圧倒的に時間が足りませんでした。
そのため、試験直前1ヶ月前からは新規の問題集に手を出すのを諦め、ひたすら解いたことのある答練や模試の解き直しに時間をあてました。
学習上の注意
クレアールの受講スタイルでは、自分自身のペースでどんどん講義視聴を進めることができますが、講義視聴を早く終わらせること自体を優先しないことが大事だと思います。
講義受講後は、テキストの復習と計算問題集を解くだけではなく、「理論の暗記を後回しにしない」「次の章に入るまでに、学習済みの章の理論は覚える」と自分にルールを設けました。
また同様に、答練などの演習問題も自分の都合の良いタイミングで受けるということができますので、準備がまだできていないから等の理由を作って、答練の受験を先延ばしにしてしまわないように、「答練を受ける期日をあらかじめ設定し、決めた日に受験する」等の自分なりのルールを設けました。
通信受講は便利な半面、こういった通信受講ならではのデメリットを自分で管理、工夫して克服していく努力が必要だと思います。
最後に
はじめて受験した税理士試験の本試験当日、財務諸表論は過去5年間とは異なる非常にボリュームの多い計算問題で、時間内に解き終えることがまったくできませんでした。
とてもすべてを解き終えることはできないと試験時間中に気付いてからも、ただただ答案用紙を埋めていくことしかできず、空白の多い答案用紙を提出することになった自分にとても悔しい思いをしました。
受験予備校では、解答手順や戦略などについてのアドバイスや指導をいただけますが、一方で、本試験で想定外の問題に出くわしたときに、普段の解答手順に固執せずに、臨機応変に戦略変更できる現場対応力も求められるのが税理士試験だと感じました。
結果的に、第74回試験の財務諸表論には、合格率8%という厳しい条件下で合格することができましたが、気持ちが折れそうになっても最後まで諦めなかったこと、コツコツと努力を積み重ねられたことが総じて合格の鍵になったと思います。
本記事が少しでも皆さんのご参考になれば幸いです。