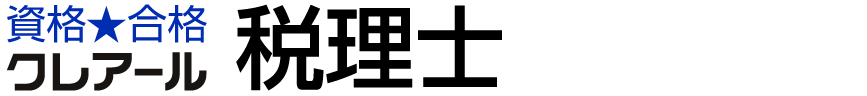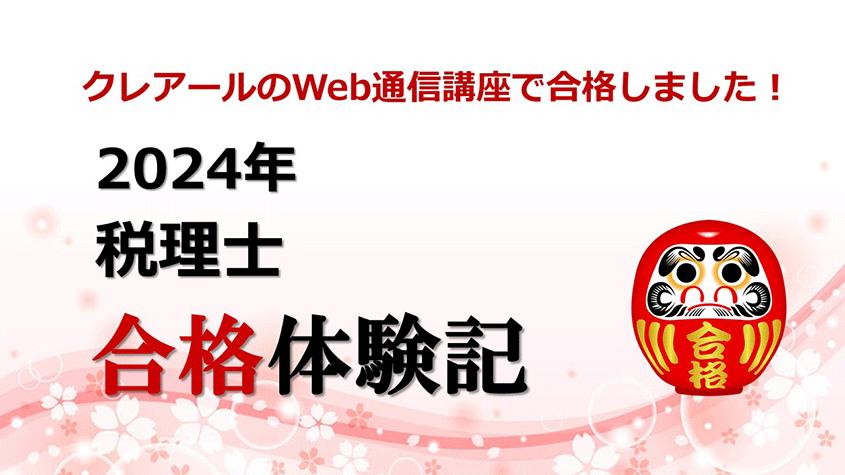K.Fさん(23歳、男性)
【合格科目】消費税法(2)
【受講コース】2024年合格目標講座 消費税法 中級コース Web通信
【職業】学生
※合格科目のカッコ内の数字は受験回数です。
クレアールを選んだ理由
税理士試験の学習をはじめるにあたって、私は自分のペースで進めたいと考えていたため、映像授業特化で、非常識合格法を掲げており、出題可能性の高い論点に絞っていることに魅力を感じました。
税理士試験の学習をはじめるにあたって、私は自分のペースで進めたいと考えていたため、映像授業であることを第一条件に資格学校を探しました。
なかでもクレアールは、映像授業特化であるため、教室授業メインの他校に比べれば便益を最大限享受できると考えました。
また、クレアールは非常識合格法を掲げており、出題可能性の高い論点に絞っていることに魅力を感じました。
前々回、クレアールを受講して簿財に合格を果たしたため、クレアールのやり方が自分に合っていると思い、税法についてもクレアールを利用することにしました。
消費税法を選択した理由は、簿財との関連が強く学習しやすいと思ったこと、簿財と同じ河野上先生が担当していたからです。
私の学習方法
大まかなスケジュール
4月までは理論:計算=7:3くらいの割合で、とにかく理論の暗記を重点的に行いました。
4月ごろからは、理論:計算=4:6くらいの割合で、総合問題や答練をひたすら解きました。
本番1ヶ月前あたりからは1日1題以上総合問題や答練を解くようにしました。
総合問題に要する時間の多くは、仮計表と呼ばれる計算用紙の内容を解答用紙に転記することになります。
そのため、直前期においては、回転率向上のために仮計表の作成のみを行い、1日に何題も解くこともありました。
答練をExcelで管理
答練や総合問題の得点をExcelにまとめることで、何度も解いた問題や点数が低い問題がひと目でわかり、「今日は何をやるか」を考える時間を削減することができました。
それによると、1年間で総合問題や答練を100回近く解いていました(仮計表の作成のみの解答を除く)。
理論は目で覚える
理論暗記の方法にも色々ありますが、私はひたすら目で覚えました。電車内などでひたすら理論問題集を読んだり、赤シートで隠したりして覚えました。
その確認方法として、腕をいためないよう、家でWordを使ってアウトプットしました。
工夫点としては、文章を覚えるだけでなく、そのページのおおまかな景色を写真として覚えました。
例えば、「このページの左下に3行くらいに何かあったな」「5行くらいのブロックが3つくらい箇条書きされていた」などを覚えることで、理論を書き出すときの助けになりました。
用語の意義を重視
前年の試験では、文章を重点的に覚えて、基礎的な用語の意義を正確に書けませんでした。
そのため、今年は特に用語の意義に重きを置きました。
方法としては、用語の名前だけを列挙したWordファイルを作成し、それに用語の意義を打ち込んでアウトプットを行いました。
スピードを重視
計算問題を解くスピードを鍛えるために、制限時間の5割〜7割くらいを目標にしてスピード重視で解くトレーニングをしました。
本番でも残り少ない時間で必要な情報を拾わなければいけないシチュエーションが想定されます。
また、このトレーニングでは集中力も鍛えられます。
前回の試験では、大問1に時間をかけた結果、大問2にかける時間が取れず非常に焦ってしまい、冷静になってみれば取れたはずの箇所をいくつか落としてしまっていました。
その結果、今年の本試験では、制限時間内に計算問題を2問とも解くことができ、なかでも大問1において納付税額の数値を合わせることが出来ました。
合格までのエピソード
問題演習について
計算問題集は、個別問題と総合問題がありますが、総合問題を重視しました。
総合問題は満点を取れるまで何度も解けば、個別問題はそれに包含されると考えたためです。
ただし、納税義務の判定、中間申告などについては総合問題だけでは足りないので、個別問題として何度も解くべきだと思います。
テキストについて
テキストについては、細かいところを中心に何度か読み込むと良いです。
計算問題を解いていてわからないところがあっても、テキストに記載されていることが多く、特に売上げ、仕入れの区分に関する論点はテキストの内容が非常に重要となります。
他校の答練や模試について
前述のとおり、クレアールの答練を何度も解いたため、初見の問題と出会うために他校の答練や模試を解きました。
ここで注意すべきことは、他校の理論の文章構成はクレアールと同じとは限らないことです。
クレアールの理論は、他校のものより法令に忠実であるところが特長であり、覚えにくいかもしれないがそのままの文言で覚えることが望ましいです。
最後に
今回の本試験では、クレアールの未履修論点が出題されました。
理論問題でまったく知らない言葉についての説明を求められ、一瞬困惑しました。
しかし、税理士試験は満点を取らなければならない試験ではありません。
「ここはどうせ誰も知らないだろう」と思い直し、次の問題へ移りました。結果、合格点に届きました。
非常識合格法である以上、未履修範囲から出題されることもあるかもしれませんが、解けるところをしっかり得点できれば合格点には十分届くだろうと思います。