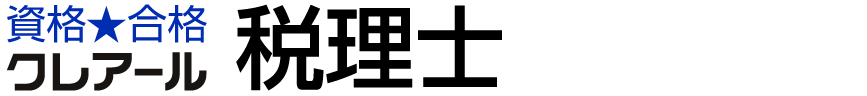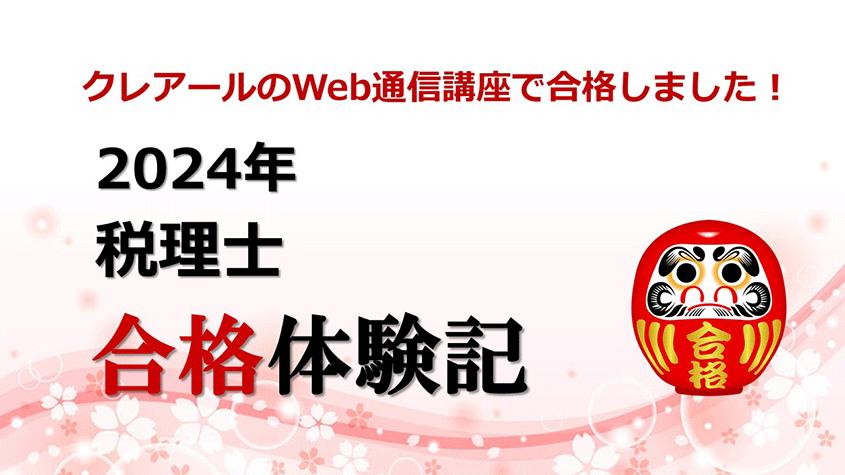H.Hさん(24歳、男性)
【合格科目】法人税法(1)
【受講コース】2023・2024年合格目標講座 科目別合格・2年セーフティコース 簿財アドバンス Web通信(1年目簿財合格の為、科目変更で法人税法を受講)
【職業】会社員
【1日の平均学習時間】平日2~3時間、休日7~8時間
【試験までの総学習時間】600~700時間ほど
※合格科目のカッコ内の数字は受験回数です。
はじめに
私は2024年第74回税理士試験において法人税法を受験し1発合格を達成することが出来ました。
昨年クレアールの元で簿記論、財務諸表論を一発合格した翌年の試験で、今年もクレアールの非常識合格法のもとで講師の方に助けられ無事最高の結果を手にすることが出来ました。
この合格体験記で、クレアールの講座を受講しようか迷っている方、非常識合格法などクレアールの勉強法に不安を持っている方に、少しでも助けになれば幸いです。
受験の動機
私は理系の大学を卒業しており、大学ではほとんど簿記などの講義は受けたことがありませんでした。
しかし、大学生から親元を離れ一人暮らしを始めたことをきっかけに、生活に不可欠なお金のやりくりに興味を持つようになり簿記2級を独学で取得しました。
それがきっかけでさらに簿記の勉強をすすめようと、簿記1級の講座を受講したのがクレアールとの出会いです。
惜しくも1級には手が届きませんでしたが、さらに挑戦を重ねたいという思いから税理士試験を目指しはじめました。
クレアールを選んだ理由
先述の通り、税理士試験の受験を決める前に、簿記1級の勉強でクレアールにお世話になっていました。
また、昨年簿記論と財務諸表論をクレアールのもとで学んでおり合格できたことから、クレアールが掲げる非常識合格法に自分自身手応えを感じており引き続きお世話になることを決めました。
クレアールは、重要で出題確率の高い論点に的を絞り学習をする、いわゆる非常識合格法を用いていますが、それはまずは合格を勝ち取り、そこから余裕を持って知識や経験を高めていこうと考える私の考えと非常にマッチしていました。
試験にほとんど出ないような論点を学んだとしても、試験に受からなければどうしても試験勉強に集中せざるを得なくなります。
それならば、試験は試験であると割り切り、確実に合格ができるような試験対策をして、合格した後で、自分の興味や関心に応じて勉強を進めた方が自分にとって有意義なのではないかと考えました。
社会人2年目となり、新社会人として受験した昨年よりも業務量が増え、去年よりもさらに勉強時間を絞って試験対策を進めていかなければいけなくなったため、限られた時間で効率よく合格をめざすクレアールのスタイルは自分にとってベストだと考えました。
私の学習方法
学習時間
平日は朝6時くらいに起きて出勤までに0.5時間、夜は8時から10時半頃まで2時間ほど、その他通勤時間や昼休みなどを有効活用しました。
机に向かう時間はほとんどの時間を計算に費やしていましたが、通勤時間や昼休み、勉強に疲れた夜遅くなどは理論を勉強していました。
朝は、計算など頭を使うものを行った方がよいことはわかっていましたが、どうしても難しかったため理論の暗記に集中しました。
休日は、演習を中心に朝7時から夜10時くらいまでこまめに休憩を挟みながら勉強しました。
法人税法の学習方法
法人税法の理論に関してはとにかく何度も繰り返しました。
一度に何時間もやるのではなく、1日に細かい時間を何度も作ることで触れる回数を増やしました。
財務諸表論と同様に、理論も最近では考えさせるような問題が増えていますが、暗記した文章をそのまま書けば得点できる問題も多くあり、そこが合否を分けると考え、漢字のミスなどもふまえ一字一句同じような文章が書けるまで暗記を繰り返しました。
計算の分野は、記述に配点が来る可能性を重視し、例えば、寄付金についてなら寄付金の分類、資本基準など書けるものは全て身につけるよう意識しました。
また、時間配分(理論45分~50分、計算75分~70分)を想定して望んでおり、過去問をやる際にはその配分のなかでできるだけ効率よく点数を取る練習を繰り返し行いました。
合格までのエピソード
昨年の簿記論、財務諸表論と異なり、法人税法の膨大な試験範囲のため、勉強が間に合わなかったことが原因で初めて試験範囲の中で出たら解けない分野(留保金課税、欠損金など)を作って望みました。
また、昨年は過去問で十分合格点くらい取ることが出来たものがありましたが、5年ほど取り組んだ過去問で十分合格点がとれたものはなく、高くても各予備校が出しているボーダー付近の点数しかとれず非常に不安な中での試験でした。
それでも試験本番では、自分と講師の授業を信じて、最後まで諦めずに食らいついたことがよかったと思います。
試験本番の理論問題について
まず1問目で留保金課税が出たことで不合格を覚悟しました。
ただ、講師の方が、初学者は無理して留保金課税の計算までは取り組む必要はないと言うことをおっしゃっており、それを信じて計算以外の理論は暗記していたため、特定同族会社の判定→当てはめなど理論の暗記のみで書ける部分や一般論をがむしゃらに書きました。
2問目は講師の方が気をつけた方がよいとおっしゃっていた保険差益についての理論が出題されました。
留保金課税の問題で計算をしなかった分、丁寧に記述しようと考えましたが、途中まで特別勘定ではなく圧縮記帳の理論を書いていたことに気づき、その瞬間は昨年と同様に心臓の音が聞こえるくらいドキドキしたことを覚えています。
3問目は修正申告についての理論だったようですが問題を見た時は全く意味がわかりませんでした。
しかし、講師の方が直前に「自分がわからない問題はみんなもわからないから自信を持って」というような言葉を授業でおっしゃっていたことを思い出し、数行適当に書いたのみで自信を持って飛ばしました。
理論の2問目は出来ていたと思いましたが、1問目は不十分で3問目は、ほぼ空欄であり自分はボーダーよりも下にいると認識しながら計算に向かいました。
本試験での計算について
計算は、理論よりは解きやすかったですが、大企業による完全支配関係があることに気づかないと記述や限度額の計算で大きく失点することから差がつきやすい問題だと感じました。
交際費の800万円基準が適用されないことなど、自信を持って判断できたことが非常に嬉しく、合格していないのに今までの努力が報われたような気がしました。
最後の欠損金の問題は基礎的なことのみ理解していたため解けませんでしたが、全体的にはよい出来でした。
最後に
合格発表を見たときは涙があふれました。
このような経験が出来たのはクレアールのおかげです。
仕事と両立させることも十分に可能な講義や答練の量であり、非常識合格法は部活を頑張る学生や仕事を頑張る社会人の味方になってくれるものだと感じました。
この合格体験記が、受験生や受験しようと考えている方に少しでも助けになれば幸いです。