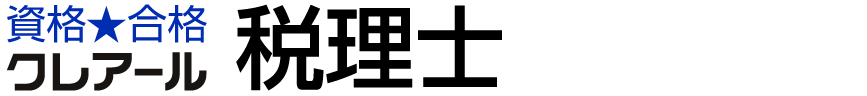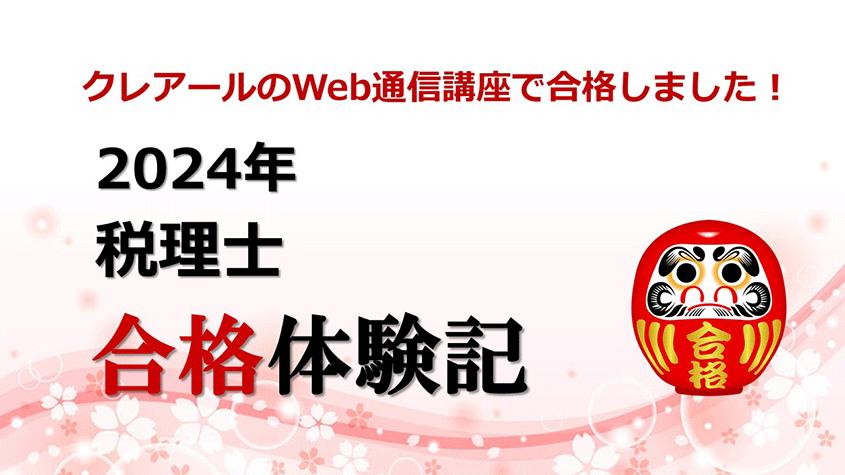H.Kさん(25歳、男性)
【合格科目】法人税法(1)
【受講コース】2023・2024年合格目標講座 科目別合格・2年セーフティコース 簿財アドバンス Web通信 (1年目簿財合格の為、科目変更で法人税法を受講)
【職業】会社員
【1日の平均学習時間】週20時間/(直前)週30時間
※合格科目のカッコ内の数字は受験回数です。
受験の動機
私は、専門性の高い職業でかつ、努力で合格可能な国家資格を取りたいと思い、この税理士試験を受験することになりました。
また、税金という身近なものの専門家ですのでとても興味があることも、税理士試験を目指すきっかけの一つでありました。
クレアールを選んだ理由
料金が安く、動画が分割で視聴可能なのでスキマ時間で勉強できることがとても魅力的でした。
長時間集中することが苦手な私にとっては、とてもありがたかったです。
また、他校のようにほぼ全ての範囲を履修していくことは、時間的にも厳しいと感じていたので、覚える要点を試験に出る最低限の範囲に絞っている点も、クレアールを選んだ理由でした。
私の学習方法
法人税は、とっても範囲が広く覚えることが多いので、いかにして、自分の中に落とし込む時間を減らせるかの努力を最優先にしていきました。
働きながらの学習だったので、理論・計算ともに合格可能範囲まで到達するには、受験専念生と比較すると、とてもじゃないですが時間が足りません。いかにして時間を生み出すかという点を、工夫していきました。
基礎期(9月〜12月)週20時間程度
いわゆる基礎期ですが、計算はあまり難しい論点は出てこないので、とにかく理論を暗記することを意識しました。
理論は覚えるまでが大変ですが、覚えてしまえば、直前期になったとしても、すぐ思い出すことができるので、ここでいかに基礎的でかつ重要な理論を完全に覚えきるかが大事です。
寝る前 1 時間と朝起きてから、その寝る直前に見ていた理論を復習していきました。
これで、すぐに 40 個くらいだったら完璧に覚えきることができます。
また、理論の学習は、理論問題集を見る時間だけではありません。
ふとした時間や、ご飯を食べている時等、理論問題集を持っていない時間にも、頭の中で理論を唱えていました。
頭の中で理論が思いつかないときには、帰宅後それを見返し復習していました。
計算しながら、その計算に必要な理論は何かなども意識しながら理論を回していたので、特段答練の理論問題は苦ではなかったです。
応用期(1月~5月)週15~20時間
ここから、仕事も勉強も忙しくなります。理論は、毎日 10 題程度、個別は授業で学んだところを 2 周+過去の個別問題集をできるだけこなしていました。
土日は総合問題の計算だけ行い、自分ができないところは何かを見つけて平日に行う個別問題を探すようにしていました。
これを続けていくと、だんだん計算が苦痛ではなくなってきました。個別問題を終わらせる時間が早くなっていくので、余った時間で理論をゆっくり深く回していました。
答練は、引っ掛け問題やドボン問題の見分け方や、解法を学んでいくことがメインなので、答練で法人税の試験に対応していくというよりは、個別問題を飽きるまで解いくことが試験に合格できた理由なのかなと思います。
直前期(6月~8月)週30時間
*最後の方は、有給を取って勉強していたので1日 15 時間くらい
ここまで勉強していれば、大概の理論や計算は恐るるに足らず。
試験までの追切が始まりました。
この時期はひたすらに過去問を解いて、足りないところの復習や国税庁の質疑応答を確認して試験に出そうな考え方を学んでいきました。
他校の模試なども受けて、今の自分の実力やほかの受験生は何をやっているのかを確認していきました。
合格までのエピソード
とにかく勉強する時には勉強だけ考えてください。
僕は法人税に受かることだけを第一に考えて、甘い考えなどもってのほかと思い、テレビを捨て、スマホは業務や必要な時以外は一切触りませんでした。
皆さんは暇なときには、スマホを肌身離さず触っていると思います。
そうです、いまこの文章を読んでいるあなたです。あなたが見るべきなのは、理論問題集です。
この合格体験記を見て【自信を付けよう】、【不安な気持ちを払拭しよう】と考えているのではないのですか?
あなたがこの税理士試験の最中、自信を付ける方法はただ1つ、覚えた理論の数を数えている時です。
資格試験ですから、落ちる時は落ちます。
仮に落ちたとしても、その覚えた理論の数は絶対に裏切りません。
必ず、実務や試験に役立つことが約束されています。
だから、絶対に今ここでスマホを見ている人は、スマホから理論問題集に持ち替えて今から勉強を始めてください。
最後に
ここまで、法人税を自分の中では完璧に勉強できたと思っていましたが、試験時間中はとても緊張していました。
カタカタとなる電卓音や、ボールペンの走る音やページをめくる音。
僕は簿記論や財務諸表論の時から、計算を先に解くことを意識していたのですが、最初の問題でつまずいてしまい、焦り散らかしました。
その時は、心臓の音が「ドクンッ」、「ドンクッ」、「ドクンッ」と聞こえました。跳ね上がってしまい、簡単な計算を間違えてしまいました。
しかし、理論に関しては、何とか意識を取り戻し、点を取ることができ、合格することができたと今でも思っています。
ぜひ、この合格体験記を読んでいる人には試験の時に緊張しないくらい、毎日勉強をしていただきたいです。