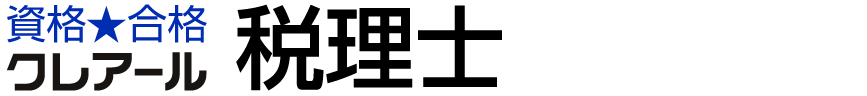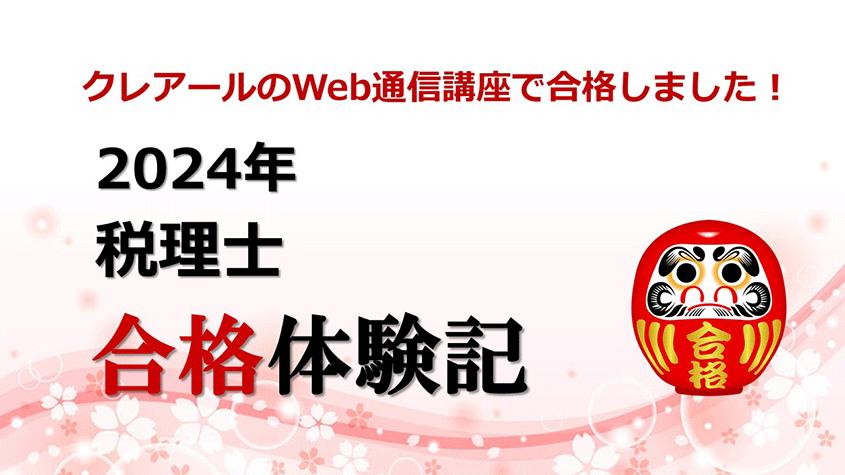K.Fさん(20歳、男性)
【合格科目】簿記論(1)
【受講コース】2026年合格目標講座 3年5科目合格セーフティコース WEB通信
【職業】学生
【1日の平均学習時間】・基礎期(1月から4月)1日あたり3時間
・解法マスター、応用期(4月、5月)1日あたり4~5時間、日曜日は8時間ぐらい
・直前期(6月から本番まで)6~7時間 日曜日は10時間くらい
【試験までの総学習時間】私は、始めたころから自分には、余裕がないことが分かっていたので、時間というよりは、やること・覚えることで区切っていたため、正確な時間は計っていません。
※合格科目のカッコ内の数字は受験回数です。
はじめに
私は、簿記無資格の状態で受験年度の1月からクレアールにて簿記論と財務諸表論の受講をはじめ、令和6年第74回税理士試験に簿記論と財務諸表論を受験し、簿記論に合格することができました。
クレアールを選んだ理由
私は、受験年度の12月頃から税理士受験を検討し始め、受講する予備校を探していたところ、クレアールに出会いました。
そこで、私は本校に資料請求をするのと、同時に、体験授業を受けました。
資料の中で、カリキュラムを見て基礎期、応用期、直前期と分かれており、その中でも、基礎期と応用期の間に、解法マスター講義という基礎期の内容で構成された総合問題の解き方を知り、税理士試験にて合格するために必要とされる正答率の高い基礎的な問題をとれるようになる講義があると知り、受講を考えました。
また、そこの体験授業で簿財アドバンスの最初の方の授業を受け、クレアールにて受講することを決めました。
私の学習方法
私は、受験年度の1月に簿記無資格の状態から学習を開始し、同年8月税理士試験の簿記論に合格することができました。
他の税理士試験生に比べ、遅くから受講を始めたのにもかかわらず、短期間で合格できた一番の要因は、通信講座であることだと思います。
基礎期
基礎期は、120ほどの授業があります。
私は、1月から基礎期を受け、基礎期を4月頃に受講し終えました。
1月から4月の期間では、1日に3から6講座受け、受けた内容を個別計算問題集にて復習するというのを、1日3時間から6時間くらいを目安に行っていました。
次に、基礎期が終わった4月は、解法マスター講義にて、基礎期の復習をしつつ、税理士試験合格のために必要な基礎問題の解法を学び、安定して点数とれるようになるまで、何回も解きました。
また、今回は、財務諸表論には落ちてしまいましたが、この解法マスター講義は、本試験を簿記論しか受ける予定がなくても、財務諸表論の解法マスター講義まで受けていただきたいと思っています。
その理由は、財務諸表論の解法マスターで習う解法でも、簿記論の重要論点となるものを含んでいるからです。
いろいろありますが、私は、貸倒引当金の解法と退職給付の解法は知れてよかったと思いました。
特に、一般的に退職給付は難しい論点とされていますが、クレアールの教材だけでなく、他行の市販教材から本試験まで、すべてにおいて使えたので、難しいと思ったことはなかったです。
応用期
4月の下旬から6月の下旬にて、応用期を受講しました。
通常では、クレアールや他校でも、1月から4月に行うものである応用期です。
私は、かなり遅れを取っていましたが焦らず、1つの単元ごと講義を受け、演習をし、復習をするのを繰り返していました。
4月から6月の間は、1日あたり5時間から6時間ほど勉強していました。
上記の応用期を受けている間、6月上旬に他校主催の全国公開模試を受けました。
もちろん判定は、最低評価のD判定でした。というのは、この試験は、答練などを家や自分で用意した場所でしか受けていなかったことから、本番の臨場感や緊張感を感じることが目的でした。
また、そもそも、この6月という時期は、一般的には、直前期であり、本番に向けて他の受験生たちは、総合問題を何個も解くという段階に入っていましたが、私は、総合問題の解き方を身につけているほど、総合問題を解いていないのと、リース取引などの論点の学習が未学習だったので、全く対応できなかったという状態だったため、D判定という結果になりました。
しかし、落ち込むことはなく、この2か月前の時点で、本試験との相当な距離を知れました。
また、その試験後、解き直しは一切せず、クレアールの直前期の内容を受けてから、内容を忘れたころに力試しとして、再度時間を計り、受けなおしました。
直前期
6月下旬から本番前は、直前期に入ります。
本番と同様にクレアールが作成した直前答練を、簿記論、財務諸表論それぞれ5回ずつほど解きました。
直前期では、1週間に上記の問題を1回ずつ解き、その間違えた問題を解き直して、どの場所なら点を取れるか、間違えた問題を個別問題集で復習し、過去の答練や、解法マスター講義の問題で復習をし、そして、直前答練を解くことを繰り返してやっていました。
他にも、すべての個別問題を1から解きなおしていました。
この期間の学習時間は、1日7時間ほどでしたが、大学生ということもあり、テスト前で学校の勉強も並行して行っていました。
合格までのエピソード
私は、税理士試験は満点を狙う試験でも、合格点を狙う試験でもなく、上位15%に入る試験であり、大多数ができる問題は、落としてはいけないということを、意識して学習をしました。
実際に試験終了後、私は自己採点で簿記論は不合格を覚悟していましたが、合格することができました。
大多数ができていた問題をしっかりとれていたことが合格に繋がったのだと思いました。
なので、解法マスター講義はクレアールを受講するうえで、必ず理解してほしい講座だと思います。
最後に
私は、令和6年税理士試験にて、簿記論に合格することができ、同年9月から、次年度の令和7年の税理士試験に向けて、引き続き、クレアールにて法人税法を受講しています。
令和R7年税理士試験では、今回落ちてしまった財務諸表論と法人税法を受ける予定です。
クレアールで大学在学中に5科目取得できるように頑張ります。