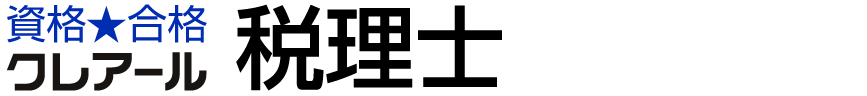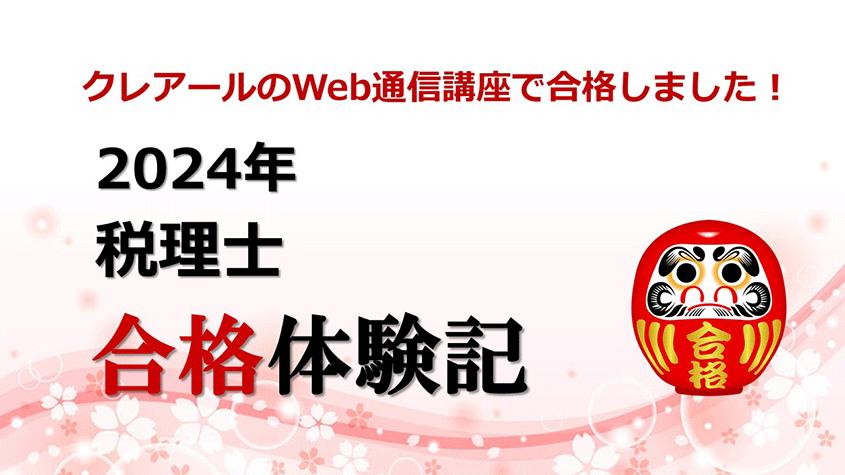N.Kさん(43歳、男性)
【合格科目】簿記論(3)
【受講コース】2024・2025年合格目標講座 1年3科目合格セーフティコース 簿財+法人税法 Web通信
【職業】会社員
【1日の平均学習時間】平日1時間~1.5時間、土日2~3時間
【試験までの総学習時間】1000時間超
※合格科目のカッコ内の数字は受験回数です。
受験の動機
受験の動機は、生涯学習の観点でゆっくり腰を据えて専門的な知識を身に着けたいと考えたときに、仕事も忙しく資格試験の勉強に割く時間が限定される中で、税理士試験は、大学で単位を取得するように、1年で1科目ずつでも積み上げていけるチャンスがあることに興味を持ったからです。
また、30代後半になってから仕事で会計・税務に携わることになりました。
それまで簿記に触れたことはなかったのですが、なんとか仕事に食らいついていきたい思いで、簿記3級の学習をスタート。
勉強の甲斐もあって簿記1級を取得できました。
自分の中ではここでいったんやり切ったと思い、一息ついてはいたのですが、2022年夏になって、簿記の知識でどこまでやれるか、腕試しの気持ちで簿記論・財務諸表論の受験に挑戦しました。
ただ、当然ながら簡単には合格ラインに達することができませんでした。
仕訳の種類などは概ね簿記一級で学習していた範囲と変わらないのですが、簿記論・財務諸表論特有の設問のクセ、あるいは解答方法を学ぶには、やはり体系的な学習の必要性を感じたことから、ネット検索で見つけたクレアールの講座を受講することにしました。
クレアールを選んだ理由
クレアールを選択したのは「非常識合格法」と語られていた、とにかく受験生の負担を減らして最短距離で合格に導こうというコンセプトが良かったからです。
そのコンセプト通り、学習ボリュームも私からすると多すぎると感じることはなく、ちょうど良かったです。
私は、昨年からクレアールの簿財アドバンスを受講しており、昨年の受験では財務諸表論に合格しました。
残念ながら簿記論は不合格となり、今年はそのリベンジです。
引き続きの受講になりますが、やはりクレアールの講義は毎回コンパクトで隙間時間での学習がしやすいメリットがあり、今年もフル活用させていただきました。
講義も、講師の先生の話がテンポ感良く進んでいくのでストレスなく進めて行けます。
ちなみに、私の場合は、既に簿記論に関してはある程度の知識があったこともあり、1.5~2倍速で聞くことが多かったです(それでも理解しづらい、ということはなかったです)。
私の学習方法
簿記論に関して、クレアールの講座受講もあって個人的には内容の理解に問題はなかったかなと思うのですが、昨年の敗因はとにかく計算を解くスピードが上がりきらなかったこと、ことさら桁数の多い処理に対して、戦いに挑む前から抵抗感があったことでした。
どうしても桁数が多くなると最終的な解答数値があってないのではないかと疑心暗鬼になり、そこで自信を持って進めなくなるということがありました(その点、財務諸表論は桁数の多い処理はないので個人的にはとっつきやすかったです)。
今年の受験にあたっては、なるべく毎日総合問題を解き、計算処理と集計処理のスピードを上げることに邁進しました。
特にクレアールの応用答練・直前答練・過去問題、市販の総合問題集など、今回はとにかく問題を解きまくって少しでもスピードを上げる、というのを重視しました。
簿記論に関しては毎日解くことでスピードが上がるので、その点にも意味があったと思います。
結果、受験直前には、自分のイメージする時間で解き切れる感覚にまで成長できました。
合格までのエピソード
今回は、なんとしても簿記論に合格したかったので、当日の解き方に関しては予め解く順番に戦略を立てて臨みました。
私の場合は、まず、最も解答時間を意識しながら進めやすい第三問の総合問題から解いて、その後第一問、第二問に戻る、という戦略を取りました。
解き方の順序に関しては、合格体験記でも色々な人がそれぞれのアドバイスを書いていますが、その時々で構成がトリッキーではない第三問から解くのが私には合っていると思い、そのような形を取りました(ここは個人差があると思います)。
また、時間配分に関しても、第三問を70分、第一問で20分、第二問で20分、残った時間で行けそうなところを積み上げる、というのを予め決めて進めました。
第三問の70分は長いと思われるかもしれませんが、私はT勘定で集計等進めていくと、このくらいの時間がないと概ね解答が埋まらないと考え、70分を想定していました。
令和6年度の試験に関しては、結果的に、これらの戦略が的中しました。
私からすると、今年の第三問は仕訳も含めて比較的オーソドックスなものが多く、落ち着いて取り組めば点を重ねて行ける問題であったため、最初の70分間、腰を据えて総合問題を解きました。
ほぼ解答欄が埋まったところで大体70分だったので、そこから急ぎ第一問に。
一見して、「あれ?」という気分になったのですが、わかるところだけ20分程度で埋め、すぐに第二問へ。
第二問はセールアンドリースバック等の処理や減価償却の基本的な論点だったので、結果的に30分近くかけてこちらも解答欄を埋めきることが出来ました。
結果的としては自己採点で、70点近くは積み上げられたかなという感じです。
最後に
私は正直、簿記論は得意不得意の論点や、全体のボリューム感に左右される部分もあるかと思います。
昨年は、第二問の外貨建ての為替予約にハマったり、逆に第一問の簡単な問題を落としまくったり、あまり戦略性を持った戦いが出来なかったことで、不合格となってしまいました。
今年は財務諸表論が難しかったと聞きますが、やはり、簿記論と財務諸表論は同時に勉強して、どちらか合格出来たらいいな、というくらいの気持ちで受けられるといいのかなと思いました。
ダメなら翌年リベンジする。その意味でも、簿財アドバンス、非常識合格法を掲げるクレアールの講座は社会人にとっては非常に良いと思います!
今年もありがとうございました!