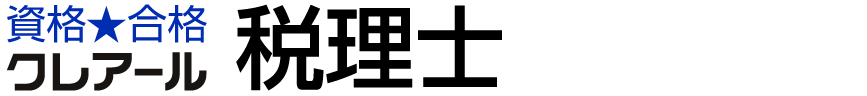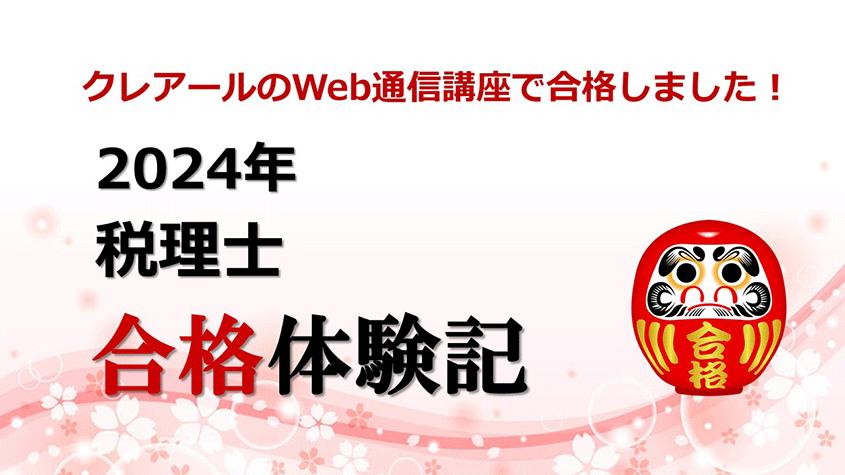T.Kさん(30歳、男性)
【合格科目】簿記論(1)
【受講コース】2024・2025年合格目標講座 1.5年3科目トライアル合格 簿記2級 C Web通信
【職業】会社員
【1日の平均学習時間】週25時間
【試験までの総学習時間】720時間
※合格科目のカッコ内の数字は受験回数です。
受験の動機
私が税理士試験を受験することを決めた理由は、妻の妊娠が判明したことです。
以前より、税理士試験には興味があったのですが、何年にもわたる学習、また長きにわたる学習の結果、5科目合格できないことも十分に考えられるため躊躇していました。
しかしながら、今後の生活を考えたときに、ゆくゆくは地元に帰りたい気持ちがあるので地方でも生かせる税理士資格の有用性、子が活発に歩きだしたりすると学習に集中できる時間を確保できなくなっていくことなどから、いま挑戦しなければ一生できない!と思いたち、中途半端な時期ではありますが、2024年2月に学習を始めました。
クレアールを選んだ理由
クレアールを選んだ理由は、日商簿記3級・2級をクレアールの講座で学習した経験があったためです。
その際の講義動画の内容やその他教材、また良心的な受講料等が印象に残っており、税理士試験の学習をすることを決めた時も、迷いなくクレアールの講座から探すことにしました。
学習の開始が2024年2月という中途半端な時期でしたが、1.5年(2024年2月~2025年8月)で3科目の合格を目指すというぴったりの講座があったので、そちらを選択しました。
クレアールの場合、簿財2科目合格までの標準学習時間が720時間とされており、学習期間を2月~7月までの6か月とした場合、月120時間を確保できれば、いまからでも24年の試験に臨めるという計算ができました。
私の学習方法
学習時間
まず、総学習時間としては2月4日の受講開始から試験前日の8月5日までのおよそ半年間でちょうど720時間を当初の目標通り確保できました。
6か月で720時間を目標としていたので、2月~7月は1月あたり最低でも100時間、1週間あたりだと最低25時間(×4週)をノルマとして必ず達成するように努めました。
土日祝日は最低8時間の学習時間を確保し、平日で1週間のノルマである25時間に不足している分を分割するようなイメージです。
加えて毎月数日の端数分は、仕事の進捗に余裕があれば月に1回程度有休や半休を取って学習する日を設けました。
8月に入り試験直前の数日間分の学習時間を含めて、ちょうど720時間となります。
学習方法
2月の学習スタートでしたので、今年に関しては基礎期→応用期→直前期というようにきれいに区切りをつけて進めることは難しかったのが正直なところです。
ひとつの章ごとに①講義動画を視聴、②テキストを通しで読みながら例題を復習、③問題集を解く、ということをひたすら繰り返して進めていきました。
それがひと通り終わったら次は、①各種答練を解く、②解説動画を見る、③理解が不足している部分については講義動画やテキスト等に戻る、④また答練を解く、ということを繰り返しました。
学習方法で意識していたのは、状況に応じて学習方法を変えることです。
通勤の電車や何かの待ち時間など、落ち着いて机に向かうことができない時間では、講義動画(特に理論中心の回)を見たり、理論問題集を読んだりする時間に充てました。
机に向かってしっかり時間を取って学習できる時には、計算問題や答練を解いていました。
合格までのエピソード
クレアールでの学習で特に良かった点は、講義動画が約30分単位で区切られていることだと思います。
30分単位の講義になっていることで、「今日は通勤時の電車で1つ視聴しておこう」とか、「今日は残業で遅くなり疲れたが、30分の講義を1つだけ聞こう」というように、少しずつでも学習を進めることを手助けしてくれているように感じました。
理論問題集の音声をダウンロードできる点も、個人的には大変助かりました。
私はこれまでの受験勉強等では「書いて覚える」タイプでしたが、税理士試験の理論暗記を「書いて覚える」というやり方でやっていると、特に税法科目に入った際に苦労するという情報があったので、「とにかく繰り返し読んで覚える」という方法に変更しようと考えていました。
(まったく書かないというわけではなく、タイミングに応じて書いてみて、しっかりアウトプットできるか確認することはしました。)
ですが、特に最初のほとんど何が書いてあるか分からないという時期には、ただ読むだけではなかなか集中力が続かず、気づいたら理論問題集を開きながら別のことを考えて時間だけが過ぎているということが多々ありました。
いろいろ方法を探っていったなかで、理論問題集の音声をダウンロードして聞きながら読む方法に変更した時から、すごく暗記が進んだように感じました。
音声がペースメーカーのような役割となり、集中力を持続させるように作用したものと思っています。
最後に
私自身の学習の取り組み方について書いてきましたが、基本的には先生がガイダンスでおっしゃる通りに、カリキュラム通りに、学習を進めていれば実力はついてくると思います。
今年は簿記論と財務諸表論の2つを受験し、簿記論合格、財務諸表論不合格という結果でしたが、財務諸表論も難易度の高い年であったこと、当日ケアレスミスでの失点があったこと等を考慮すると、実力としてはかなり前進したと自分自身感じています。
来年はより確実な実力をつけ、25年の試験に向けて新たに学習を開始する消費税法と併せて、簿記論・財務諸表論・消費税法の3科目の科目合格を果たしたいと思います!