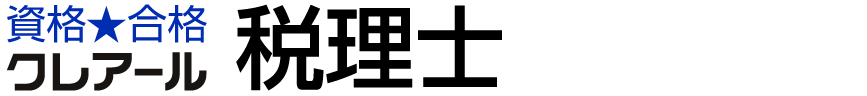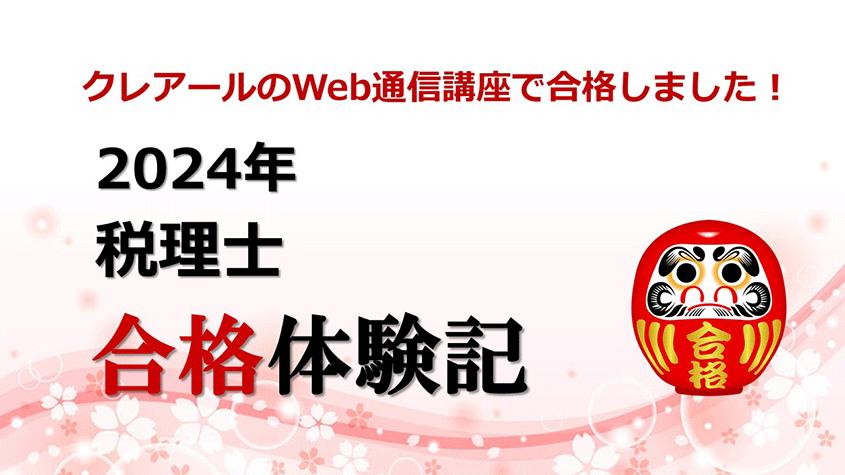T.Oさん(36歳、男性)
【合格科目】簿記論(2)
【受講コース】2026年合格目標講座 3.5年5科目合格セーフティコース WEB通信
【職業】会社員
【1日の平均学習時間】1日平均30分
【試験までの総学習時間】200時間
※合格科目のカッコ内の数字は受験回数です。
受験の動機
私が税理士を目指すこととなったきっかけは、自らが専門性をもって職務に努めることで、日本経済の発展の一助となり、人々の生活をより豊かにしたいという思いからでした。
専門性となると、様々な士業がありますが、特に会計分野に興味があったことから、はじめは公認会計士を目指しておりました。
しかしながら、個人や企業と近い立場でのサポートのため、独立した事務所で働きたいと考えた結果、税理士がその希望により適合するものと考え、方針を変更して税理士を目指し、会計事務所での業務や勉学に励んでおります。
クレアールを選んだ理由
私とクレアールとの出会いは、公認会計士試験を受験しようと考え、働きながらでも効率的に学べるスクールを探したことからでした。
クレアールは非常識合格法を掲げ、効率的に必要な情報だけに集約して学習するスタイルであることから、仕事と学習を並行しなくてはならない環境にあった私にとって、これ以上ないものであったと思います。
実際に他校の教材や講義を確認していないことから単純な比較はできないながらも、ハッキリと出題可能性が低い論点は切り捨てる考え方や、必要最低限の知識を習得することで発展的な思考へと繋げる手法には魅力を感じました。
残念ながら受験の動機にて記述したとおり、公認会計士を目指すことは断念しましたが、現在は税理士を目指してクレアールの学習方針を信じ、日々勉学に邁進しています。
私の学習方法
基本的に私の学習方法は「短時間でもアウトプット」を重視しています。
簿記論は日商簿記の延長線上にあるため、日商簿記1級に合格した時点で自分の中に基礎はできていたことから、インプットに関してはさほど時間を必要としておらず、日商簿記と税理士試験・簿記論の問題の相違点に着目し、アウトプットを繰り返しました。
試験における各論は、日商簿記と相違ない解答方法で問題なく進められたのですが、税理士試験には総合問題があり、その解答スピードなどは、アウトプットを繰り返すことで養いました。
また、学習において重要に感じたのが、短時間であっても継続することです。
相当の勉強時間を必要とする税理士試験においては、日々の学習時間が十分でないといけないというプレッシャーがありますが、最も必要と考えられるのが継続性だと思います。
そのため、何かしらの理由により例えば10分の学習時間しかなくとも、とりあえずは問題を解くことを日々の癖とすることで、やらない理由を自分の中に作らないように努めています。
合格までのエピソード
河野上先生の簿財アドバンスの講義は、端的に申し上げて「面白い」と感じました。
学習というものは、ともすれば単調になり、インプットしたつもりになりやすいもので、それは単調がゆえに感情と連動せず、記憶に残りにくくなってしまうものです。
そこで河野上先生は、ご自身の経験からエピソードトークを織り交ぜてくださることで、財務が関係する社会のニュースなどとの関連性まで教えてくださったことで、「面白い」を私に提供してくださり、それが感情との連動で記憶に残りやすくしてくださったように思います。
簿記論の前年に合格することができた財務諸表論は、会計における理論を必要とする分野であったことから暗記が必須であるため、先生の講義によるエピソード記憶は大いに役立ったと感じています。
最後に
私は現在、会計事務所にて職務に従事しておりますが、税理士を目指し始めた当初は大学の事務職員として働いておりました。
前職では会計の知識を必要とする職務ではなかったのですが、概ね定時にて業務を終えられる環境であったことから、日商簿記1級の取得を目指し、朝はなるべく早く出勤することで業務開始までに自主学習の時間を数十分ほど確保し、退勤後は自宅にて1時間ほどの学習をすることで、1日1時間半ほどの学習時間にて1年強にて日商簿記1級を取得しました。
資格取得にて学んだ知識を、職務でアウトプットできる環境を求めて会計事務所に転職し、その後は業務が以前よりも忙しくなったことから1日1時間ほどの学習時間にて、初年度は簿記論・財務諸表論を受験しました。
何とか財務諸表論には合格できましたが、簿記論は解答スピードが養われておらず不合格となりました。
日商簿記の学習にて計算の基礎はできており、理論を重点的に学習していたために簿記論対策が疎かとなった当然の結果でした。
2年目は簿記論と消費税法を受験すべく、それらを並行して学習を進めておりましたが、新たに学ぶ消費税法の比重が重くなってしまい、簿記論の学習は思ったように進められておりませんでした。
そんな中、受験日の数か月前に子供が生まれ、仕事・育児・勉学と非常にタイムマネジメントが難しい状況となったことから、消費税法と簿記論の学習比重を大きく見直し、2年目は最低でも簿記論に合格すべく答練を繰り返すことで合格することができました。
初年度の不合格後、同様の学習内容を改めて学びなおすことは苦痛に感じることが多いと思いますが、私の場合は消費税法を並行したことで、新鮮な知識を学ぶことができ、それにより簿記論の勉強し直しの苦痛を和らげることができたように思います。