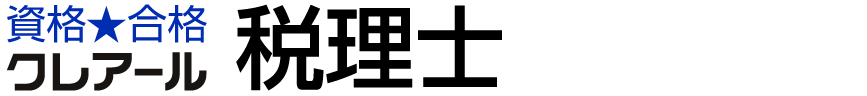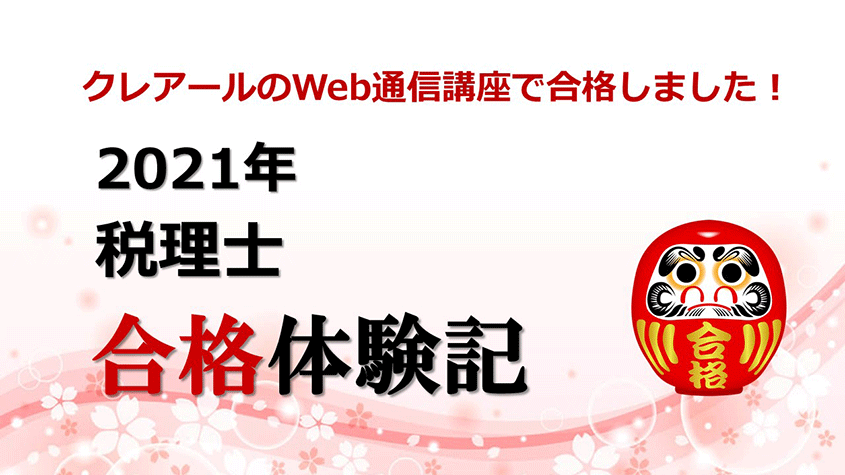S.Oさん(54歳、男性)
【合格科目】財務諸表論(3)
【受講コース】簿財アドバンス 上級コース
【職業】会社員(メーカー勤務)
※合格科目のカッコ内の数字は受験回数です。
はじめに
私の税理士試験への本格的な挑戦は、50歳から始まりました。
新卒以来、同じメーカーに勤務しています。簿記については会社が用意してくれた通信教育で3・2級を学習しましたが、資格の取得までは求められていないので、簿記の知識は通信教育の課題をクリアするレベルに留まっていました。
それでも、クレアール流の戦い方を身に付けることで、仕事と両立させながら合格にたどり着くことができました。
受験動機
そろそろ定年がリアルな話として見えてくる年齢になり、定年後をどうするかを考えたときに、個人として独立的に仕事をやっていける税理士が、真っ先に候補として挙がりました。
また、時代も移り、会社の仕事においても会計系の成果物については、資格などの裏付けがない状態では評価すらしてもらえない状況となったこともあり、税理士資格取得を目指すこととしました。
クレアールを選んだ理由
長期の出張が年に何回かある仕事に就いているため、通学では欠席も多くなって、講義の録画などによるフォローがあるにしてもキャッチアップしきれるかどうかの不安があり、通信教育でないと難しいと考えました。また、通学と通信ではノウハウに違いがあると思いましたので、通信に特化していて実績がある学校ということでクレアールを選びました。
ただ、やはり一番には、「非常識合格法」に惹かれたということが大きいです。
私の学習方法
理論
講義内容をしっかり理解することと、理論問題集の音声データを通勤時に聞く、あとは応用・直前答練の解答を何度も書き写して覚えるようにしました。クレアールの答練はどれも実戦向けで、これをやり込むことで自然と合格レベルに到達すると思います。河野上先生の講義は、実務経験を交えて記憶に残るような形でお話しいただけるので、本試験でも、迷った時にすっと講義の内容を思い出すことができ、得点につながりました。理論は手を広げだすとキリがありませんが、答練だけでもやり込んで、しっかり記憶に定着させれば、たいていの問題には対応できる(空欄にしない)ようになると思います。
計算
最初のころは、答練で先生が「ここまで〇分を目標」というのに対して2倍近くかかっていました。問題を解くスピードがなかなか上がらず、読んだり書いたりするスピードを上げて対応しようとしましたが、そうすると読み飛ばしや計算ミスも増えて結局得点アップにはつながらず、こんなの時間内にやり切れるわけがない、〇分で通過できるなんて神か、と幾度か心が折れそうになりました。さすがに何回転かすると解くスピードは少し上がりましたが、一方で転記ミス・計算ミスはあまり減らず、気持ちも疲れてきてモチベーションの維持が難しくなってきました。
そこで、スピードの追求は止めて、転記ミス・計算ミスを減らすのを主体とする方向に切り替えました。具体的には、答練でのミスの発生原因を分析して、解法マスターで教わった「下書き」を、自分が陥りやすいミスを予防できるような形にカスタマイズすることにしました。(最後には、絶対に基本形を崩すことはないと思っていた貸倒引当金の「下書き」も、縦型から横型に変わっていました。)
また、本試験の場でも解法の型が崩れないよう、多少の手間は増えても様々な論点に対応できるようにメンテナンスし、答練を使って徹底的に体に染み込ませるようにしました。
その結果、問題への取り組み方が安定し、これが解く時間の短縮にもつながりました。出題項目がある程度決まっている財務諸表論においては、自分なりの解法の確立というのが特に有効だと思います。
合格までのエピソード
ある程度想定はしていましたが、やはりこの年齢からの新しい学習は大変で、暗記するということ自体が難しくなっていることに愕然としました。計算も、すぐに解き方を忘れてしまい、本当に合格にたどり着けるのか心配でした。
1年目は、勉強時間は週10時間、月40時間を目標として設定しましたが、勉強の習慣付けができず、出張の影響もあり、目標勉強時間の半分、答練は2回転が精一杯でした。
2年目も、目標勉強時間の8割程度が精一杯でしたが、応用答練は6回転、直前答練は3回転させることができました。しかし、合格にはあと1点不足でした。後から見直すと計算では取れるはずの問題がいくつかあり、後悔するところ大でしたが、絶対に合格するぞという強い気持ちを持てていなかったことがその様な結果を招いたのだと感じ、気合を入れ直して3年目に臨みました。
3年目は、月40時間、直前期は70時間の勉強ができ、応用答練を7回転、直前答練を3回転させ、無事合格にこぎつけました。必要以上に間口を広げるのではなく、この論点ならこのレベルまでは確実に取れる、というものを増やしていったことが結果につながったと思います。
最後に
日常的に会計と関わるような仕事ではなく、簿記も学習経験だけで取得はしておらず、年齢も50代ということで、他の受験生と比べてもかなり後方からのスタートであると思います。それでも、クレアールの講義と教材だけで合格することができました。
どの学校でも、指定したカリキュラムをやりきることで合格力が身に着くようになっているはずですので、迷ったときは、自分がそのカリキュラムをやりきれるかどうかで選ぶのが、一番の近道になると思います。