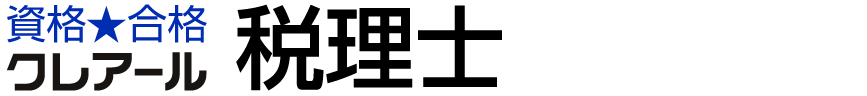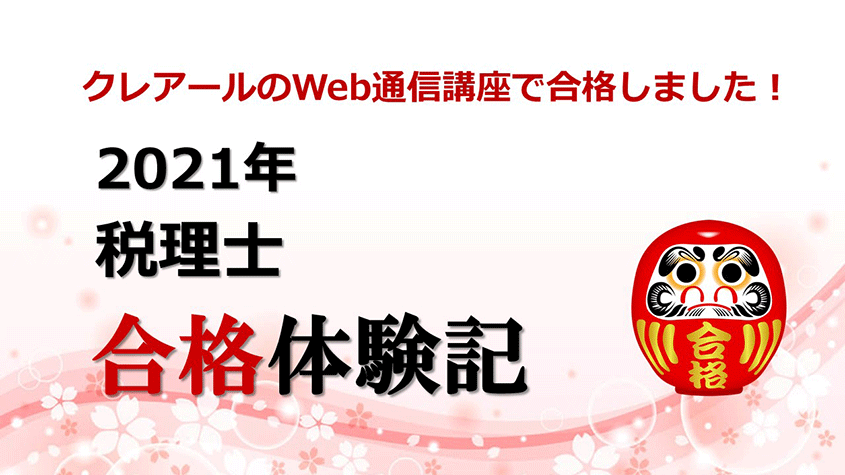M.Kさん(30歳、男性)
【合格科目】財務諸表論(1)
【受講コース】2年5科目合格セーフティコース 2年目(簿財アドバンス・相続税法)
【職業】会社員
※合格科目のカッコ内の数字は受験回数です。
税理士試験の受験動機
大学卒業後、会社員として数年間勤務し、その間に複数の部署での業務を経験しました。幅広い業務を経験できたと思う一方で、組織外でも通用するような専門的な知識を身につけられていないのではないかという危機感が強まり、日商簿記の勉強を開始しました。
簿記2級を取得した頃には、会計、そしてそれと関係の深い税務という分野への関心がさらに深まり、いっそのこと税理士の勉強をしてしまおうと思い、まずは税理士試験の会計科目を受験することを決意しました。
クレアールを選んだ理由
簿記2級までは独学で取得しましたが、学習範囲が段違いに広いらしい税理士試験に挑むからには、専門学校の教材を利用した方が効率的と考え、複数の学校のパンフレットを取り寄せました。
パンフレットを一通り見た中で、クレアールは受講料が圧倒的に安く、しかも、他校に比べてポイントを絞った教材を売りにしている点に惹かれ、受講を決めました。
講義について
他の学校の授業を受けたことがないので比較はできないのですが、河野上先生の講義を聞いて感じたのは、
① 重要論点と、そうではない点のメリハリが付いている
② 図や表を多用し、ビジュアル的に分かりやすい板書になっている
③実務についての解説が充実している
という点です。
特に③について、公認会計士・税理士両方の実務経験をお持ちの河野上先生は話の引き出しが多く、今学習している論点はこのような形で将来使えるのか、といった具体的なイメージができ、記憶の定着に役立ちました。時には受験に直結しない内容もありますが、それらの小話も、無味乾燥になりがちな受験勉強の中での清涼剤的な役割を果たしてくれ、飽きずに講義を聞くことができました。
私の学習方法
1年目
これを書かずに2年目のことから書いてしまおうかとも思ったのですが、正直に打ち明けますと、私は簿財の勉強を始めた初年度はうまく勉強のサイクルを作ることができず、受験を断念しました。
前述のとおり、講義を聞くことは苦ではなかったものの、実際に計算問題を解こうとすると思うようにいかず、計算を億劫に感じていました。結局、講義は一通り視聴し終えたものの、計算問題集や答練はほぼ手付かずで、ただ講義を聞いただけのような状態で終わってしまいました。
2年目の4月まで
1年目の体たらくを反省し、2年目はテキストの例題や問題集を一通り解くことを目標にし、答練も期限から大きく遅れないうちに提出するようにしました。
平日は1時間、休日は3時間程度勉強することを目標にしていましたが、仕事で疲れていることを言い訳に、勉強時間がゼロになってしまう日も多く、勉強のサイクルを作るのにまだ苦労していました。
この頃は、制限時間1時間の基礎答練を解くのにもテキストを見ながら2〜3時間かかり、制限時間2時間の応用答練に至っては2日かかってしまうようなレベルで本当に辛かったのですが、実際に問題を解くうちに、インプットした知識がつながって身になっていく感覚が少しずつ出てきました。
5月以降
直前期になると、ほぼ毎週答練が送られてくるようになります。この頃からようやく2時間の制限時間を守って答練に取り組めるようになりました。
平日は相変わらず勉強時間がゼロになってしまう日がありましたが、土日祝は必ず簿記論・財務諸表論の答練を1回分ずつ、2時間測って解くことをルールにしました。その結果、応用答練と直前答練は3〜4回ずつ回すことができ、解法マスター講義で習った下書きが使えるようになっていきました。特に財務諸表論の計算に関しては、税効果会計に関係する部分を優先的に拾っていく、河野上先生直伝の攻略法が身につき、かなり自信を持って本番を迎えることができました。
財務諸表論は理論の対策も必要ですが、自分の場合は目で見るだけでは暗記することができず、理論問題集の赤字部分をシートで隠しながら紙に書き出すという方法が一番記憶に残りやすい気がしました。
クレアールの教材を消化するだけで手一杯だったため、他校の教材は、模試を含めて一切利用しませんでした。というより、それどころではありませんでした。本番までの総勉強時間は、簿財合わせて5〜600時間くらいだったのではないかと思います。
これから受験される方へのアドバイス
これまでの文章で察していただけたかと思いますが、私はあまり模範的な受講生ではなかったと思います。そんな私がアドバイスなどを書くのはおこがましいのですが、以下の2点は強調したいと思います。
①とにかく、やること
当たり前のことですが、どんなに良い教材が手元にあっても、自らの意思でそれを使わないと意味がありません。
特に私のように、大学受験以降、机に向かって勉強する習慣が途絶えてしまったような人間にとって、フルタイムの仕事をしながら勉強のサイクルを作るのには相当の苦しみが伴います。
疲れていても、気分が乗らなくても、とにかく少しでもやる。これを継続して、勉強を習慣にするのが第一歩です。……第一歩なのですが、私は学習1年目には、これができませんでした。
②アウトプットしないと身につかない
これも当たり前なのですが、講義を聞くだけでは問題は解けるようになりません。できないことをするのは辛いことなので、ついつい、気力を使わなくても勉強をした気になれる講義視聴を優先してしまい、「まずは講義を一通り聞いて全体像を掴んでから問題を解いた方が効率的。」などと屁理屈をこねてこの行為を正当化しがちなのですが、これは間違った考えです。
手を動かして、苦しんで、初めて本当に理解ができるようになるので、計算演習は講義視聴と並行して必ずやるようにしてください。
最後に
今回この合格体験記を執筆するに当たって、他の方の合格体験記を参考に読んだのですが、やはり皆さんものすごく熱心に勉強をされていて、頭が下がる思いがしました。答練を10回ずつ解いた、と書かれている方もいらっしゃいましたが、そこまでコミットできれば、危なげなく簿財ダブル合格ができると思います。
私は、今回の受験で財務諸表論は合格できたものの、簿記論は58点で不合格でした。この原因は一重に、自らの努力不足にあると思っています。次回の試験で簿記論と消費税法を受験すべく引き続きクレアールにお世話になっていますが、勉強に必要な体力のようなものが、以前に比べれば付いてきている気がするので、少なくとも再受験の簿記論については必勝の体制で望みたいと思っています。
教材という意味では、合格に必要なものは全てクレアールに揃っています。あとは我々受講生が、どれだけの時間と気力を注ぎ込めるか、勝負はそこにかかっています。ともに頑張りましょう。