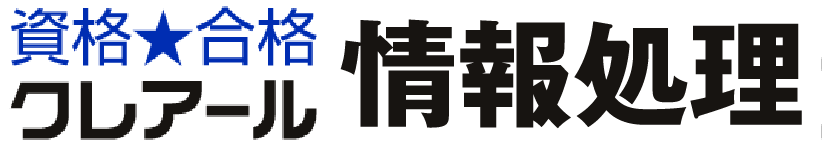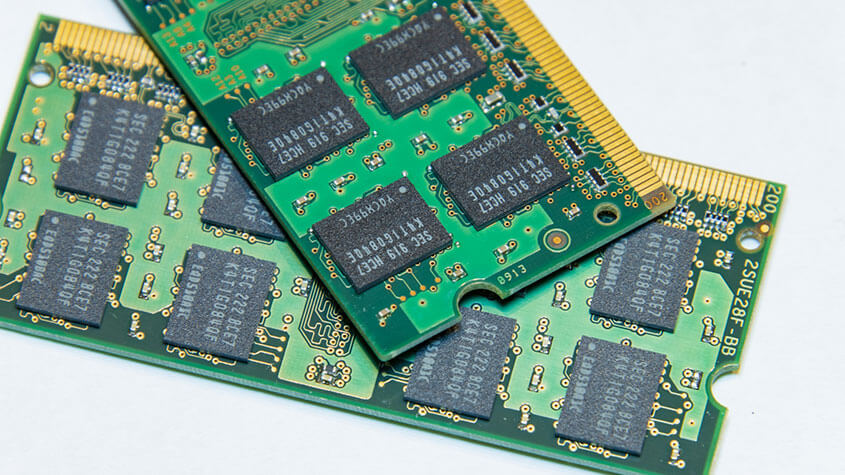メモリの種類と特徴
メモリとは、コンピュータが処理するプログラムやデータを記憶する装置のことであり、大きく分けてRAM(Random Access Memory)とROM(Read Only Memory)に分類することができます。
RAM
一般的にRAMはデータの高速な読み書きができますが、電気の供給が停止すると記憶内容が消去される性質(揮発性)を持っています。高速なアクセスが可能なため、レジスタやキャッシュメモリに使用されます。
ROM
ROMは電源を切っても記憶内容が消えてしまわないように不揮発性メモリを使用している読出し専用メモリでしたが、技術の進歩に伴い、ある程度の回数は書き込みできるものがあります。
ROMは主にコンピュータの動作準備のためのプログラムを格納するために使われます。
記憶媒体の種類と特徴
記憶媒体は補助記憶装置とも呼ばれ、文字通り主記憶装置を補完・補助するための記憶装置です。主記憶装置上ではコンピュータの電源が入っている間しか情報を保持できないため、長時間にわたって(電源が切れても)大量の情報を記録・保持することのできる記憶媒体を利用します。
| 分類 | 記憶媒体名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 磁気ディスク | HDD | 円盤型の磁気ディスクを回転させて、データを記録します。 |
| 光ディスク | CD | ・CD-ROM 樹脂製の円盤に細かい凹凸を刻んでデータを記録します。 読み出ししかできません ・CD-R 有色色素をレーザ光で焼いてデータを書き込みます。 追記には専用のドライブ装置が必要です。 |
| DVD | ・DVD-ROM 見た目はCD-ROMと同様ですが、記憶容量が大きいです。最大記憶容量は記録方式(片面1層・2層など)により異なります。 ・DVD-R 一度飲みかき込みが可能です。 ・DVD-RAM 10万回以上の書き換えが可能です。 | |
| Blu-rayDisc | 技術革新により、片面8層(200GB)などの大容量の保存が可能です。 | |
| フラッシュメモリ | USBメモリ | コンピュータに接続するUSBインターフェースを備えています。 |
| SDカード | デジタルカメラやスマートフォンなどの記憶媒体として幅広く利用されています。 | |
| SSD | 大容量の補助記憶装置として、近年はHDDから置き換わりつつあります。 |
記憶装置は、種類によって読み取り速度・書き込み速度・記憶容量・価格などが大きく異なります。
コンピュータの性能だけを考えれば、すべてを高速にアクセスできる記憶装置にすれば理想的ですが、高速な記憶装置ほど、容量あたりの価格が高価になるため、コストと性能のバランスを考慮して、適切な記憶装置を使います。
記憶階層
キャッシュメモリ
キャッシュメモリは、高速のレジスタと低速の主記憶装置の速度差を解消(処理を高速化)するために、CPUと主記憶装置の間に設置されるメモリであり、SRAMが用いられます。最近のCPUでは、容量や速さの異なるキャッシュメモリを高い層で搭載しているものがあります。その場合、CPUに近く、高速で容量の少ないほうから順に1次キャッシュ・2次キャッシュ・3次キャッシュといったように呼称します。
まとめ
今回はメモリについて解説しました。
クレアールではこのほかにもITパスポートに関するコラムを投稿していますので、併せてご覧ください。