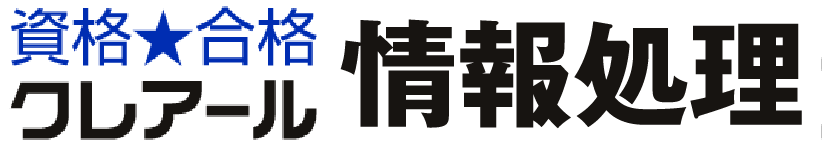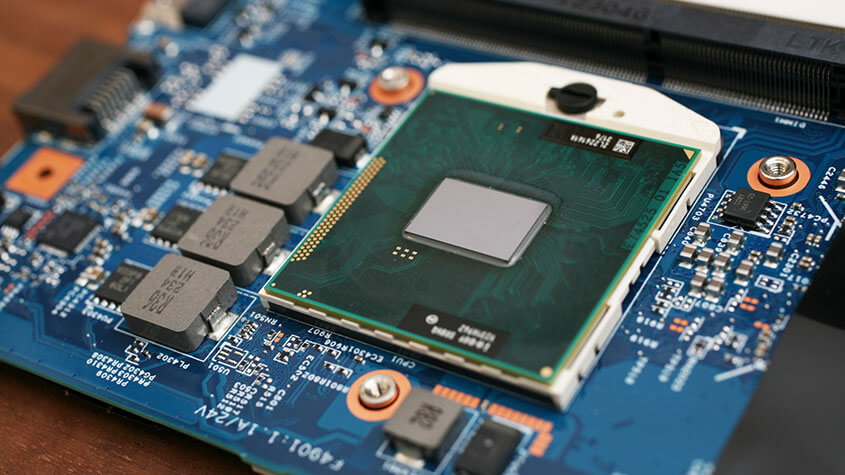①コンピューターの構成
コンピューターは演算装置、制御装置、記憶装置(主記憶装置と補助記憶装置に分けられます)、入力装置、出力装置の5つの基本機能から構成されています。
中央演算処置装置(演算装置・制御装置)
中央演算処理装置は、CPU(Central Processing Unit)とも呼ばれ、コンピューターの中枢で頭脳に相当します。与えられたデータをプログラムに従って処理するための装置です。中央演算処理装置は、さらに制御装置と演算装置からなります。制御装置は命令を解読し、その命令を実行するのに必要な指示を各装置に送ります。演算装置は制御装置からの命令によって四則演算や論理演算を行います。
記憶装置
記憶装置は、処理を行うために必要なプログラムやデータを保持する装置です。記憶装置にはさまざまなものがありますが、コンピュータが処理する上では、主記憶装置(メモリ)が重要な役割を果たします。また、主記憶装置を補完する補助記憶装置(ハードディスク・DVD・Blu-ray、SSDなど)は、用途や性能によって使い分けが必要です。
入力装置・出力装置
入力装置・出力装置(合わせて入出力装置と呼ぶ)は、コンピューターに指示を与えたり、その指示の結果を出力したりするための装置です。指示を与えるものが入力装置(キーボードやマウスなど)、結果を外部に出力するものが出力装置(モニタやプリンタなど)です。
プロセッサの基本的な仕組み
CPU(Central Processing Unit)
プロセッサは別名CPUとも呼ばれ、パソコン内部の中心となるパーツです。CPUには、各装置に命令を出す「制御」機能と、プログラムからの命令に従って計算を行う「演算」機能が備わっています。コンピューター性能はCPUの能力に大きく左右されますが、その性能を示す例として、32ビットCPU・64ビットCPUがあります。32ビットや64ビットは、一度に取り扱えるデータ量を示しており、数値が大きいほうが能力は高いです。
また、CPUが扱うデータ量とOSが使うデータ量は本来一致している必要がありますが(32ビットCPUでは32ビット版OSを使う)、OSとCPUの開発タイミングは必ずしも一致しないため、64ビットCPUは32ビットCPUとしても動作可能とする互換性を持っており、32ビット版OSを64ビットCPUでも使用することが可能です。
マルチコアプロセッサ
一般的なCPUでは、プロセッサコア(演算処理を行う論理装置など、CPUの中核部分)が1セット入っています。マルチコアプロセッサにはこのプロセッサコアが複数個入っており、ちょうどCPUを複数個搭載しているような状態になります。つまり、1つのCPUに複数のプロセッサコア(中枢機構)を集積したCPUです。
クロック周波数
コンピュータ内の各回路での処理タイミングを取るテンポの速さをクロック周波数と呼びます。例えば、「1GHz」という形式で表記される指標であり、この例で言えば、タイミングを取る信号を1秒間に10億回発生させていることを示しています。値が高い(クロックの間隔が短い)ほど処理速度が速いです。
GPU(Graphics Processing Unit)
GPUとは、3Dグラフィックスなどの画像描写に特化した演算処理装置のことであり、画像処理についてはCPUよりも高速に処理することが可能です。
まとめ
今回はプロセッサについて解説しました。
クレアールではこのほかにもITパスポートに関するコラムを投稿していますので、併せてご覧ください。