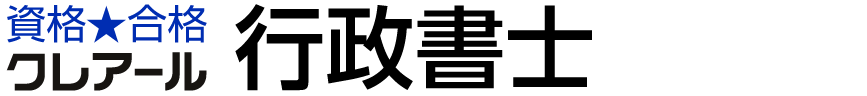受験回数:2回(2年目合格!)
受講コース:2020.21年度目標カレッジ2年セーフティコース
行政書士を目指したきっかけ
私は会社を経営しており、業務の中で税理士や司法書士そして行政書士の先生方へ顧客を紹介することが多くありました。 あるとき税理士の先生から行政書士資格の取得を勧められたのがきっかけです。今後は会社経営と並行して行政書士としても活躍したいと思っております。
クレアールを選んだ理由
私は行政書士試験を受験するにあたって、独学という選択は最初からなく、複数の予備校を比較検討しました。その結果、クレアールを選んだ理由は大きく下記の4点となります。
- クレアールのいう「非常識合格法」は、私の中では常識的な合格法であったこと。
- ほぼ全てがWebで完結すること。
- 受講料が低価格であること。
- 3の低価格な上、セーフティコースを選択することにより、不合格の場合でも翌年の受講料がかからないこと。(予備校を利用することによって合格できる可能性は高くなる・・・とは言っても、この試験の合格率は約10%で10人中9人が不合格となる難しい試験ですから、このセーフティコースはお守りのような存在でした。他校では受講料がこの価格帯で、クレアールのセーフティコースと類似した講座を設定している予備校はなかったと思います。)
科目別学習方法と合格後に改めてクレアールの講義を振り返って・・・
まず使用した教材はクレアールから送られてきたテキスト・答練や模試の冊子(画像参照)+六法になります。
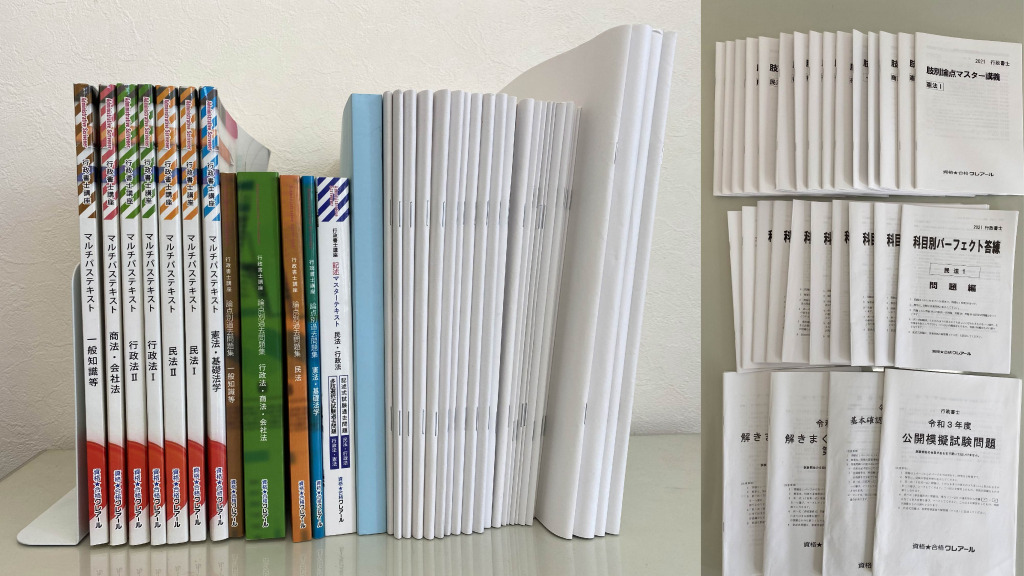
勉強方法に関してはどの科目も、
- 講義を視聴(1.5倍速)
- テキストを読む
- 過去問を解く、これが基本でした。
そして過去問・答練・模試に関しては、
- 問題を解く
- 答え合わせをして間違えた問題をピックアップする
- 2でピックアップした問題を「解説を見ないで」テキストや六法を見て自分で調べる。
この「解説を見ないで」とするところがですが、もちろん解説が悪いということではなくて自分で調べることで記憶が定着しやすくなるということに気付いたからになります(どうしてもわからない場合は解説を見ますが)。
また、1日の勉強時間は平均すると約3時間ぐらいですが、直前期は1日に5時間ぐらい勉強していました。これが多いのか少ないのかはわかりませんが、私はこれ以上やっても集中力が続かないため5時間以上の勉強はしなかったです。
・基礎法学
基礎法学はやりだしたらきりがない分野なのでクレアールの教材を信じてやり抜くだけで十分だったと思います。逆に深入りは危険だと思います。
・憲法
憲法は条文と判例が大事だと思いますが、私は条文を暗記するのが苦手なので統治に関しては過去問や答練などの問題を解く程度しかしておりません。逆に判例は好きなので、事案と結論はもちろんのこと判旨についても可能な限り調べて理解するようにしていました。
・行政法
行政法は範囲も広くて日常生活においても馴染みのない分野も多く、とっつきにくい科目ですが、得点源になるので、苦手な分野を作らないように意識して勉強していました。最後の最後まで行政法総論と地方自治法に苦戦しましたが・・・。
とにかく過去問を解いて→テキストで復習を繰り返し、問題に慣れるようにしていました。そして憲法のところでも書きましたが、判例はまんべんなく勉強しておりましたが条文の暗記はしておりません。
また記述式については、テキストを読んでいるときや問題を解きながら、こう問われたらこう解答するなどをイメージしながら勉強していましたので特別な対策はしていませんでした。
・民法
民法は1000条を超える範囲が広い科目ですが、行政法と違い馴染みのある分野が多いため頭に入りやすくクレアールのテキストを読み講義を聴き過去問を解くだけで十分だったように思います。別途、判例はまんべんなく勉強しておりましたが条文の暗記はしておりません。
記述式については行政法と同じく、テキストを読んでいるときや問題を解きながら、こう問われたらこう解答するなどをイメージしながら勉強していましたので特別な対策はしていませんでした。
・商法会社法
商法会社法は範囲が広いわりに択一で5問しか出題されない科目ですが、捨てるのはもったいないですし深入りは効率が悪いと思っておりましたので、テキスト・講義・過去問を勉強した程度ですが、この試験においてはこの程度で十分だったように思います。
・一般知識
〇政治/経済/社会
政経社はほとんど勉強しておりませんでした。対策しても対策した部分が出題されることはないと思ったからです。
ですが過去問に目を通すことによって、こういうふうに問われるんだなぁと分かることと、同じ問題は出題されないとわかることによりそれが対策になりました。
時事問題に関してニュース等を積極的に見ていた程度で、私は十分でした。
本試験では見たこともない訳の分からない問題がほとんどで、それらを解くことになりますが、そういう問題こそ冷静に文章をよく読み、消去法で2択まで絞り、より常識的な肢を選ぶ・・・これでなんとかなりました。(まぁその2択をことごとく間違える訳ですが(笑))
〇情報通信/個人情報保護法
情報通信もつかみどころがない分野になりますが、テキストと講義で十分でした。
個人情報保護法は、テキストの範囲から出題されると思ったため対策が立てやすかったです。講義を聴きテキストを読み過去問を解く。これで十分でした。
〇文章理解
講義を一度聴いた程度でほかに対策はしなかったです。
六法について
私はただ暗記をするということが苦手なため条文を暗記するために六法の素読はしなかったです。
その代わりに①問題を解いた後に該当箇所の条文を読む②なぜそうなるのか理解する③前後の条文も読む。を意識していました。さらに④類似の条文との比較もするようにしていました。
このような勉強方法でも合格することが出来ましたが、今後の受験生に一言アドバイスさせていただくとすれば、〇行政手続法〇行政不服審査法〇行政事件訴訟法ぐらいは得点に直結するので最低限読んで覚えておくことをおすすめします。時間があれば憲法(特に統治)もですが・・・。
本試験を振り返り&記述式の採点はブラックボックス
クレアールの講座のみで合格圏内(択一で150~170点+記述)までは十分可能だと思います。(というよりこのボリュームを1年間まじめに取り組めば、多くの方がこれぐらいの点数はとれるのではないでしょうか。)
しかしこの試験は180点で合格!という絶対評価の試験を装って、記述式の点数配分等で合格者数を調整する相対評価の試験だという側面もあると思います。
もっとも択一で180点をとれれば問題ない訳ですが、そんなに甘い試験ではありません。
法律初学者の私が、クレアールを信じて勉強を続けた結果、
1年目(2月~11月まで/約530時間勉強)は択一168点+記述4点=合計172点で不合格でした。11月の試験の後に自己採点をしたとき、記述次第ではあるがおそらく合格だろうと思っておりました。が、まさかの不合格(記述4点)・・・とショックでした。
この結果から、2年目は記述式に頼らないように択一逃げ切り(択一で180点以上)を目指して勉強を続けましたが、2年目(5月~11月まで/約400時間勉強)も択一166点と、またも記述次第となってしまいました。最終的には記述で24点とれており合計190点で合格となりましたが、はっきりとわかったことは記述式の採点基準は公表されておらず完全にブラックボックスということです。したがって記述式の得点次第で合格という状態は、面白おかしくいうと運ゲーであるということです。
そして多くの方が、この運ゲーに参加させられることになると思いますし、記述式の採点はどうすることもできない以上対策のしようがないということになりますが、それでも私の経験からこの運ゲーを制するためのアドバイスとして下記の三点をあげさせていただきます。
① 「記述式の勉強は十分にするということ。」
当たり前のことですが記述式の勉強をするということは、最終的に条文を覚えるということになり、条文を覚えるために六法を読むということになります。(私は出来なかったので)
② 「本試験のときわからない問題でも白紙にはしないこと。」
完答出来ない場合でも、わかる部分だけでも書いて部分点を取りに行くこと。2点でも4点でももらえるかもらえないかで合否が変わることがあります。
③ 「本試験が始まったら記述式の問題から解く」
これは人によって違うと思いますが、記述式からとりあえず解いてみて分からなければ先に進むという方法が私にはあっていました。なぜなら一度記述式の問題を見ているため、択一の問題を解いているときに突然思い出すこともあれば、わからなかった漢字が出てくることもありますので、効率的だと私は感じました。模試など解いてみる際に一度試してみてください。
終わりに
杉田先生・竹原先生のわかりやすい講義に助けられ無事に合格することができました。約2年間勉強を続けることができたのもお二人の講師のおかげです。クレアール関係者の皆様、この度は大変お世話になりました。ありがとうございました。