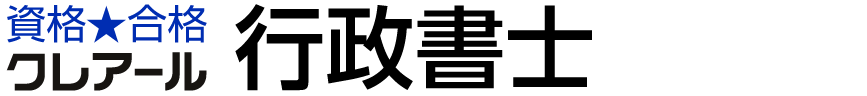受験回数:2回
(1回目は約10年前に独学で受験。)
受講コース:2021.22年度目標司法書士受験経験者対象行政書士2年セーフティコース
はじめに
受験回数を重ねましたが、フルタイムで働きながら、令和3年度司法書士試験に合格することができました。
令和3年度行政書士試験も、司法書士試験受験時同様、フルタイムで働きながら受験しました。
私の行政書士試験合格体験記は以下の方に参考になるかと思います。
- 司法書士試験に挑戦中の方
- これから行政書士試験と司法書士試験に挑戦しようと考えている方
行政書士を志した動機
私が行政書士を志した動機は、下記の通りです。
- 法律関係の仕事に興味がある
- 司法書士になれた場合、行政書士の資格があれば業務の幅を広げ、役立てることができる
- 試験科目のうち民法、商法、憲法が司法書士試験と重なっている
クレアールを選んだ理由
- 司法書士試験合格年度に受講していた予備校がクレアールだった
- 独学で行政書士試験を受験した際、行政法に苦手意識を持ったため今回は受験予備校を利用しようと思っていた
- 司法書士試験受験者向けコースがあり、かつ受講料が割安だった
- 合格した際には祝い金が出るとのことで、モチベーション維持になると思った
以上4つが、私がクレアールを選んだ理由です。
具体的な学習法
まず、司法書士試験受験後すぐに行政書士試験の勉強に取り組んだわけではありません。7月4日の司法書士試験後、2週間くらい勉強はしていませんでした。
その後は、インターネットなどで行政書士試験について調べることから始めました。調べると以下のことがわかるかと思います。
- ①司法書士試験の憲法より、行政書士試験の憲法の問題の方が細かい知識が必要
- ②一般知識等は個人情報保護法等と文章理解で正解数を稼ぐ
- ③司法書士試験合格レベルであれば民法・商法はアドバンテージがある
- ④地方自治法は条文数が多い
上記①から④を踏まえ、地方自治法を除く行政法と個人情報保護法等をまず学習することにし、8月中に、それぞれ2周することを目標としました。
学習の仕方としては、クレアールから配布される教材と市販の六法で
- ①講義を聴く
- ②テキストを読む、条文・判例を六法で確認する
- ③過去問を解く
- ④過去問で誤った問題についてテキスト・六法に戻る
以上の繰り返しでした。
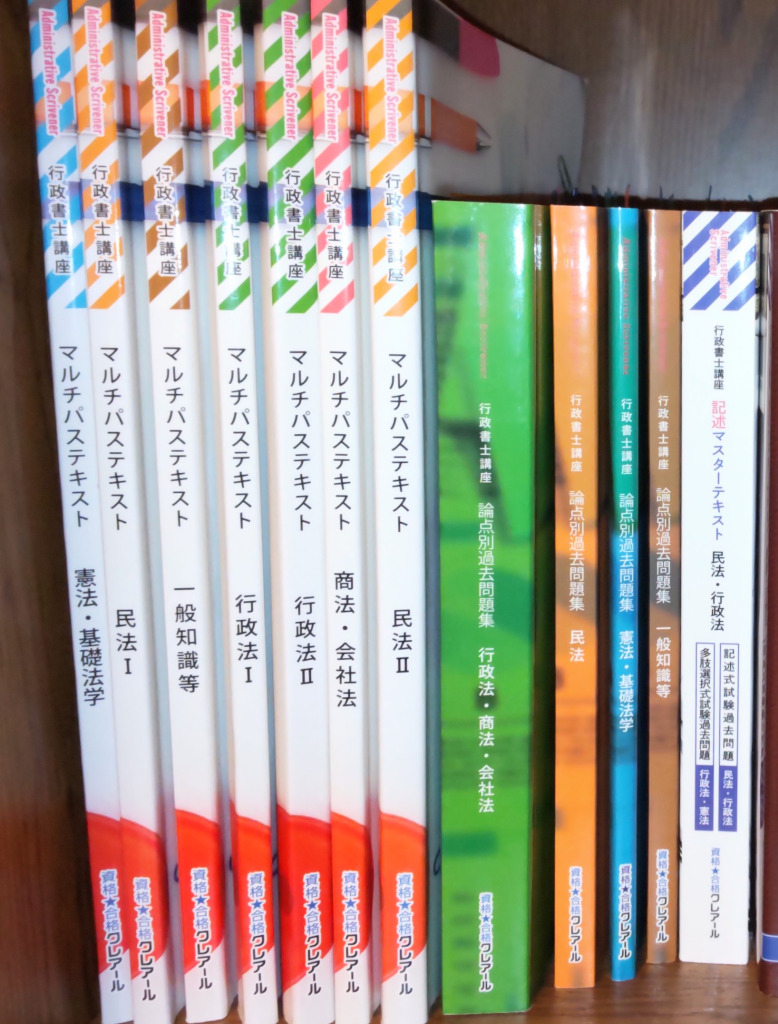
- 決断
8月の下旬頃になると、それまで触れてこなかった民法・商法・憲法の知識の抜けが気になり出し、また学習してきた行政法について、あまり知識の定着が良くないと感じていたので、思い切って地方自治法は捨てると決めました。
- 9月からの学習
9月以降は毎日少しでも行政法に触れ、平日は行政法と他1科目(民法、憲法、個人情報保護法等)を学習し、休みの日に商法の過去問演習を取り入れました。
なお、民法は記述式対策メインの学習でした。クレアールから配布される教材で記述式問題の演習をし、条文を確認するという学習です。
- その後
10月11日に司法書士試験筆記試験の合格発表があり、10月25日に司法書士試験口述試験でした。この間の2週間は口述試験が気になり、あまり行政書士試験の勉強に集中できませんでした。
- 口述試験後
この頃から、過去問以外の問題演習や模試を受け始めましたが、結果は散々でした。法令科目や一般知識で足切りにはならない成績でも、合格点までは遠く、時間をかけている行政法もあまり得点できない状態でした。
行政法については、条文や判例が理解できないのではなく、行政法の用語の定義をなかなか覚えられず、曖昧に理解していることが失点の原因でしたので、11月の直前期は、定義の確認・理解を重点的に行いました。
試験結果
- 基礎法学0/2
- 憲法4/5
- 行政法15/19
- 民法7/9
- 商法4/5
- 一般知識等8/14
- 多肢選択式12点
- 記述式22点
合計186点で運良く合格できました。
最後に
司法書士試験と重なる試験科目と重点的に学習した行政法で得点できたことが合格につながりました。
司法書士試験合格レベルの方は知識的にはアドバンテージがあるかと思います。
ただ、行政書士試験の勉強中や試験中、問題を解いていて、問題が簡単とは思いませんでした。
働きながら、短期間で行政書士試験に挑戦するなら、司法書士試験受験時と何ら変わらない学習態度が必要です。
計画がうまく進まず不安になることもありますが、本試験、どんな問題が出題されるかわかりません。
受験申込みをしたら、あきらめないで受験してください。