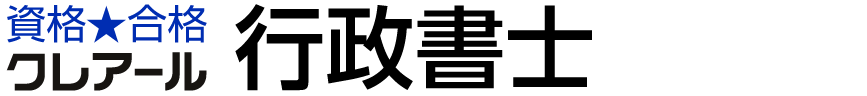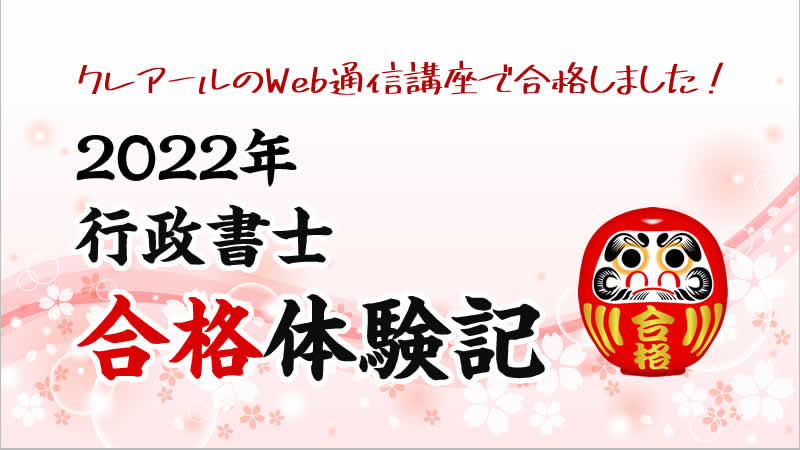受験回数:5回
受講コース:2022.23年度目標中上級W受講セーフティコース
☑2022年度合格体験記
☑リベンジ合格
<はじめに>
令和4年度の試験に合格することができました。「記述待ち」の不安な状況でしたが、結果は記述式で20点以上をとることができ合格ラインを超えることができました。不合格が続いても諦めずチャレンジを続けることの大切さを実感しました。
参考になるかどうかわかりませんが、私の体験記を述べさせていただきます。
<行政書士を志した動機>
現在の業務が消費者や事業者のトラブル相談に対し助言を行うことを求められる仕事で、どうしても民法や会社法の基本の部分は押さえることが必要でした。そこで過去に「ビジネス実務法務(商工会議所)」にトライし2級合格後、1級のチャレンジを考えましたが、1級の試験内容はすべて記述で学習には相当数の時間が必要と思われ、限られた時間を学習に費やすなら国家資格の「行政書士」を目指そうと思い、トライすることにしました。
<学習方法>
まずは不合格試験の振り返りから
過去の不合格の原因の分析を行うことから、次の合格に向けての学習を始めました。
私の場合、本試験で「記述式の3問を3時間の試験時間のどこで解くか」が大きな課題となっていました。多くの場合最後に解いていたのですが、ある年は既に合格している友人の助言で「間に挟む作戦」で臨んだ年もありましたが、記述式に多くの時間を費やしてしまい失敗しました。
最終的には元に戻し、最後に解く作戦で臨むことにしました。どちらにしても実力が十分に備わっている場合は、記述式を解く順序がどこにあろうと影響はない話であろうと思いますが、私のようにボーダーライン上の場合はどうしても効率よく解く方法を考えてしまいます。
「記述式は最後」と決め、「基礎法学・憲法」、「行政法」、「商法・会社法」は、各2分以内、「民法」、「多肢選択式」は各4分以内、「一般知識」は文章理解を4分以内、その他を1分半以内として、記述式に取り掛かる時点で45分以上を残すことを目標に、科目ごとの所要時間を設定して臨みました。
この結果、「時間不足で問題を考える時間がない」ということは無くなりましたが、「行政法」と「民法」の得点不足で合格に届かない、という重要な課題は複数年続きました。
因みに今回は多肢選択式で時間を使いすぎ、記述式前で35分程度しか時間を残せなかったことが悔やまれますが、その中でも1問は20点近く取れたと思われ、助かりました。
「行政法」と「民法」 の得点不足への対策
年間の学習において「行政法」と「民法」で確実に得点を確保するため、この2科目を中心に学習時間を確保することと、特に今回は覚えたことを忘れていない時期に本試験を迎えるように、直前期に行政法の繰り返し学習を配置し、民法、憲法、商法・会社法は直前期までに十分に時間を使い学習するという計画で取り組みました。
また、一般知識の情報通信や個人情報他も直前期に繰り返し学習を行い、本試験で一般知識を12問正解することができた一因になったのではないかと思っています。
さらに、答練等で間違えた内容や、テキスト等で間違え易い部分を備忘録として書き出し、自身の「虎の巻メモ」の今年版も作りました。
学習の時間と場所
仕事をしているため、平日は通勤途中の電車内と帰宅する前のファーストフード店での学習をトータルで最低でも2時間程度は確保しました。土曜・日曜は約3時間から4時間といった感じでした。「飲み会」は直前期を除き、あえて週1回は行いストレスの開放につながり学習の継続に効果があったと思います。
<クレアールを選んだ理由>
- 受講料金のお得感
- セーフティコースがある
- 講義音声をダウンロードでき、通勤電車で活用できた。
- 過去に「社会保険労務士」をクレアールで学習し合格した。
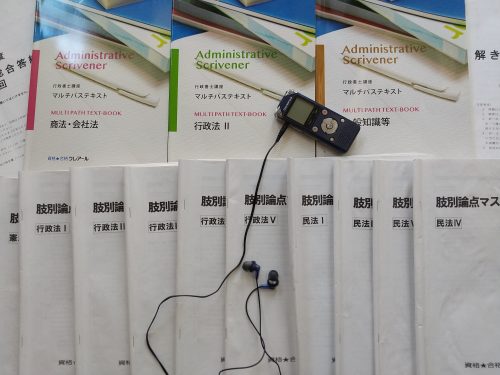
<今後の使い道>
行政書士試験の学習により、行政法、民法、商法は現在の仕事にも役立っています。
今後は幅広い行政書士の業務の中でどの分野を専門にするか、現在の勤務を離れ「行政書士事務所」等で実務を積み、社会保険労務士とのWライセンスで開業が叶えばと考えています。