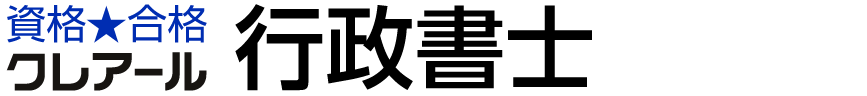(一発合格)山本 雅之さん
はじめに
この度、令和6年度の行政書士試験に合格することができました。今後受験される方の一助になればと思い、反省も込めて自身の体験を書かせていただきます。
なぜ行政書士資格を目指したか
令和5年度の社会保険労務士試験に合格し、既に取得していた中小企業診断士の資格とあわせ、独立を志し始めたところ、社会保険労務士試験でお世話になったクレアールより行政書士講座の案内をいただきました。行政書士資格を持つことで業務の幅が広がると考え、挑戦することにしました。
予備校選びのポイント
最初は費用のこともあり独学を考えました。しかし、重要科目である行政法は全くの初学であることや、記述式の学習は独学では難しいと考え、社会保険労務士試験の講座がすごく良かったこともあり、引き続きクレアールにお世話になることにしました。
クレアールで学習して良かった点
行政書士試験の合格最低ラインである180点をクリアするために何をするべきかを講義の中で繰り返し話されたこともあり、メリハリをつけた学習ができたことが大きかったと思います。講義自体はボリュームが多く時間の確保に苦労しましたが、初学者にわかりやすい内容だったと思います。答練は個人的にはもう少し量が欲しかったですが、模試も含め適度な難易度で、3回ほど繰り返し解きました。私は良質な問題の演習量を更に稼ぐために、市販の紙上模試を1冊利用しました。問題演習を通じて自分の足りないところを補っていくことは大変重要だと思います。
学習を進めていくうえでのポイント
行政書士試験は行政法と民法を制すれば合格に近づくと言われており、行政法と民法の2科目は徹底した学習が必要です。一方、憲法(基礎法学含む)・商法会社法は難易度や学習範囲の広さと配点との関係から多くの時間をかけるのは割に合わないと考えますが、「ここだけは点数が取りやすいので押さえておくべき」という論点があります。そのような論点をしっかりと押さえておくようにしましょう。実際の講義や答練の解説でもそのような説明がありました。
基礎知識は「行政書士業務と密接に関連する諸法令」が出題範囲に追加されましたが、本試験では前年までの出題傾向と変わらない印象でした。基礎知識はポイントが絞られる法令関係と3題出題される文章理解で確実に点数を稼げれば、格好はつくと思います。加えて新聞やインターネットで話題になっている事象に注目しておけば、時事問題で点数を少しでも稼げるかもしれません。
また、憲法・行政法・民法は条文の読み込み(重要な条文は暗記するレベルまで)と判例の理解(結論だけでなく過程も含めて)が極めて重要です。私は学習開始当初から条文の読み込みが不足しており、答練が始まってそれに気づきました。それ以降本試験まで条文の読み込みに重点を置きましたが、本試験では「条文と判例の学習が不十分だった」と痛感させられました。
結果、行政法は19問中14問、民法は9問中5問、記述式は4割程度の得点に留まり、合格したものの冷や汗ものでした。逆に憲法(基礎法学含む)がほぼ満点だったことに救われました。
記述式の勉強法について
記述式は何を問われるのかが全く予想できず対策の立て方は今でもわかりません。私が取り組んだのは、①クレアールの記述式テキストの徹底学習②市販の記述式問題集での演習量確保、の2点です。
しかし、②についてはクレアールで学習してきた内容と全く異なる観点での問題設定がされており、かつ本試験まで余り時間がないタイミングで始めたにもかかわらず満足に答案が書けず自信を失いかけたので途中で打ち切りました。
逆に①については4回繰り返しました。とにかく原稿用紙に答案を書き続けました。
前述の通り、記述式は4割程度の得点しかできませんでしたが、やはり条文や判例をしっかりと勉強することで部分点を稼ぐことはできますし、これ以外に有効な勉強法はないと思います。
初学者の方へ
行政書士試験は法律科目が中心となるので、初学者、特に法律の学習が初めての方は取っ付きにくい可能性もあると思います。私の場合、学習経験のない行政法対策に、平易に解説している市販の参考書を1冊購入し、予備校のテキストと併用しました。また、最新の六法全書は必須です。常に手許に置き、学んだ内容に該当する条文を読み、キーワードに印を付す等して、何度も読むようにすると、そのうち記憶に残るようになります。
最後に~受験生の方へ
受験生の方は、行政書士試験にチャレンジされる理由を必ずお持ちだと思います。この理由こそがモチベーションだと思います。途中で勉強が嫌になることも少なくないと思います。そんな時は少し勉強から離れ、「なぜ行政書士資格を目指すのか?」ということを思い返してみましょう。最後までモチベーションを維持できれば、合格に近づくと思います。頑張ってください。