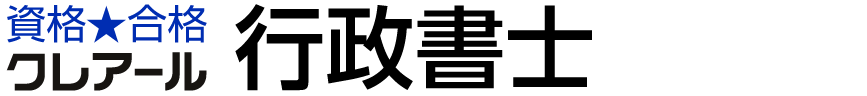K.Nさん
なぜ行政書士資格を目指したか。
簿記3級と宅建を取得し、その後様々な資格の勉強をしていましたが、どれも中途半端な状態で終わっていました。自分にとって行政書士が一番合格の現実性があると思い勉強を開始しました。
なぜクレアールを選んだか
一番は魅力的な価格です。私は専業主婦で子供も小さかったので通学は考えず、自宅で勉強できる通信一択でした。
クレアールで学習してよかった点
テキストは明確、最低限の量で学びやすかったです。授業時間も1コマ30~40分程度と集中力が途切れない、1日に2コマやっても疲労感がない、家事、育児に支障が出ないことが挙げられます。過去に別資格の授業を他校で受けたときは1コマ2時間30分で集中力の継続が大変でした。
効果的な学習方法
理想は毎日数時間勉強することですがそれは不可能なので、授業を1コマでも視聴する、できない日はテキスト1頁、過去問1問でも目をとおす、テキストさえ開けない日は、頭の中で数日前に暗記した事項を思い出す、など少しでも毎日頭に何か入れることが効果的だと思います。
科目別学習法
〇憲法は、判例以外の事項は理解が非常に難しいため、判例中心に学習しました。出題される判例は大体きまっているので、重要判例のポイントとなる言葉、解釈は理解するよう心掛けました。条文数が少ないので全暗記すべきだったなと感じています。
〇民法は、奥が深く学習しても点数に結び付かない難しいところがあります。そのため、基礎的な条文知識、解釈、基本的な判例は絶対抑えて、あとはそこから派生して考えることにしました。学習範囲は六法で条文を確認しました。
〇商法は一番苦手でした。条文も膨大でパワーをかけてもダメだと感じ、極力過去問を回すことに集中しました。無機質な事項の暗記は語呂合わせにしたりしました。設立、組織、株式など出題可能性から学習の優先順位をつけ、なかなか想像できない企業内部や株主総会のことについては、インターネットで検索して説明しているサイトで理解を促しました。
〇行政法は、とにかく正確に細かく条文を理解し暗記することが必要です。やればやるだけ点数に跳ね返ってくる科目ですので、過去問→条文→テキストで確認、の作業を繰り返しやる。暗記はすぐに忘れてしまうので前回やった所を少し間を開けて再度解く、という地味な作業が一番点数に結び付くと思います。行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、それぞれ似て混乱する箇所は比較して横断的に覚えることが必要でした。
仕事、家事、育児等との両立、学習スケジュール
勉強開始から合格までの間にかなり時間がかっています。その間、二人目出産、長男中学受験などがあり、多忙を言い訳に学習から遠ざかっていた期間もありました。
私の場合は育児家事との両立になりますが、子供の学校がない土日祝日は勉強できませんでした。また、春休み、夏休み、冬休み等長期休暇もやはり学校がないため、勉強に時間を割くことができませんでした。そのため、7月までにできるだけ講義の視聴をしてインプットをする、9月から本試験までに追い込みをかける、というイメージでやっていました。答練、公開模試は自宅で行い自己採点しましたが、クレアールのスケジュールとおりにやるべきだったと感じています。
来年度の合格を目指す方へのアドバイス
私は過去5回程受験して不合格、6回目でやっと合格しました。今年本腰を入れて勉強できたのも9月以降であり、合格点も高得点での合格ではなく、合格基準点を少し上回るギリギリの合格でした。ですので、こういう人もいるんだという程度でみていただければと思います。
受験1回目の点数が一番合格に近く、あと6点不足だったと記憶しています。現在よりも若く、体力も記憶力もありました。あと6点だし、来年は合格するでしょうと完全に慢心していました。2回目以降の受験からはどんどん合格点から差が開き、長い期間低迷しました。ほぼ勉強していない状態であるにもかかわらずとりあえず受験だけはしておこう、と試験に挑んだり、かなり彷徨っていました。英検等と異なり、行政書士試験は1年に1回しかチャレンジすることができないため、時間もお金も無駄にしています。出来るだけ学習に集中し一発合格、最短合格を目指すべきであったと後悔しています。
また、1回目~4回目までは独学でした。その間に民法、商法改正、新しい判例が出て判例変更があり、自分の知識がどんどん古くなりました。そこで5~6回目はクレアールの講座を受講しました。私のように長期にわたって学習することになってしまった場合は、資格学校の講座を受講することを強くお勧めします。