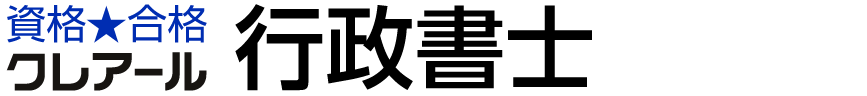講義を担当されている杉田徹先生と、受講生サポートを担当されている玉村一博先生のお二人に「行政書士合格への道」について対談を行っていただきました。

- 杉田 徹講師
- 行政書士。早稲田大学法学部卒。確かな試験分析力と見る者を惹きつけてやまない情熱的な語り口で、毎年多くの受験生を合格へと導く。近年では法律に関する執筆活動も行うなど、精力的に活躍のフィールドを広げている。

- 玉村 一博講師
- クレアール行政書士アカデミー受験対策室長。長年にわたり受験予備校、大学などで行政書士、宅地建物取引主任者講座の受験指導に携わる。その豊富な指導経験に基づいた親身なアドバイスは多くの受講生から厚い信頼を得ている。
昨今の行政書士試験の動向
─── 本日は「行政書士への道」というテーマで、杉田徹先生と玉村一博先生に対談形式で色々とお話を伺います。よろしくお願いいたします。まず始めに、近年の行政書士試験の動向について、お聞かせいただけますでしょうか。
杉田 行政書士試験は近年、出題数の変化や試験様式の変更などもあり、一昔前の試験と比較はできません。特に平成18年度の試験制度の変更で、法令科目が40問から46問の出題へ増え、一言で言うと、法律の実務家向けの試験になったと思います。それまでは一般教養が20問もあり、しかもその内容が国語や社会など高校の授業や大学入試で勉強するようなものまで出題されていたのに対して、平成18年の改正によって出題数は14問となり、出題範囲も政経社会、情報通信・個人情報、文章理解という様に高校や大学入試レベルの問題とは異なる範囲から出題されるようになってきています。
また、法令については、従来の40問から46問へ増え、しかもそのうち、民法、行政法が中心となったことは、「行政手続の専門家」「街の法律家」といった行政書士に期待される役割を十分に果たすことができるように、実務に必要な法律を中心に科目設定されているような気がします。また、その内容も具体的事例から法的解答を導き出すという事例解析問題がちらほら含まれており、単なる法的知識のみならず、その知識から法的問題を解決する法律実務家に必要な能力も試す試験になってきているようです。
玉村 そうですよね。世間的にはまだまだ、行政書士試験は入門的資格で簡単というイメージがありますが、実際はかなり高度な試験になってきていますよね。単に知識を暗記しただけでは点数が取れなくなっています。杉田先生もおっしゃったように、事例を解析させたり、法的問題解決能力を試すものも出題されたりしています。学習される方は心して始めないと、途中でついていけないということにもなりかねません。
ただ、それが全てではなく、基礎力をしっかりと身に付けていけば、合格ラインの6割はクリアできる試験だと思います。すなわち、基礎部分をそのまま問う問題は出題されないのですが、それをカモフラージュして、難しく見せている問題が多いのです。だから、問われている問題の本質を見抜くことができれば、基礎知識で解けてしまうのです。行政書士試験が法律家になるための試験に変貌してきたということは言えるでしょうか。これが、昨今の傾向だと思います
講義について
─── なるほど、近年の行政書士試験の傾向が分ってきました。では、このように変貌を遂げてきた行政書士試験に合格するための必要なポイントはどこにありますか。まず、最初に杉田先生の講義についてお聞きしますが、難化傾向をみせる法令科目の講義をどんな点に注意されて講義されているのでしょうか。
杉田 当たり前ですが、「わかりやすく、メリハリのついた講義」を心がけています。「わかりやすさ」とは、抽象的で難解な法律をなるべく具体例を出してその意味を理解してもらうことを意味します。「メリハリのついた」とは、試験対策上、重要な箇所は講義中でも特に強調して丁寧に説明するのに対して、試験対策上、比較的出題頻度が低い箇所は、講義中、さらりと時間をかけずにコメントするといったように、重要な箇所が特に講義後に頭に残るように強弱をつけた講義を心がけています。
─── やはり、メリハリが無いと長期にわたる、試験勉強が苦痛になってくるでしょうね。 先生の講義は分かりやすいと受講生に聞きます。楽しく学習されている方が多いように見えるのですが、先生はどのようにお感じですか。
杉田 自分で言うのも何ですが、楽しく学習されている方は結構多いですよね。(笑)
玉村 私も、直接教室で、授業終了後に受講生の皆さんの顔を見ていると、スッキリした顔をした人が多いですよね。何かを気づかせる講義を杉田先生が心がけておられるからこそ、最後まで続けられ、「分からないことが、分かってきた」という表情なんでしょうね。

予備校の学習方針を信じて、
最大限利用することが合格への近道。

基礎力をしっかりと付ければ、
合格ラインの6割は取れる試験。
合格に必要な学習姿勢とは
─── それは、素晴らしいですね。難解な表現も身近な例に置き換えて講義を行っていただくと、最初は分からなかった所が、雲が晴れたように理解できる。理解できるから続けられる。理解できるから覚えていられる。そんな相乗効果もあるのですね。 ところで、先生方は毎年多くの受験生の方を見てきていると思いますが、短期合格する方のタイプなどあるのでしょうか。また、どんな姿勢で学習に取り組むべきですか。
杉田 そうですね。難しいのですが、私が見てきた中で合格するタイプは、素直な人が多いように思います。素直とは、人の指示をそのまま守るタイプの人を意味します。具体的には、講義中、「ここは条文で確認しておいてください。この問題を何回もやってください。」など、講師が指示したことをそのまま実践してくださるようなタイプの人は合格しやすいようです。
逆に、人の指示を守らない、講義で説明したのにその説明と違う解釈を自分でしてしまい、その自分の考え方に固執する、といったタイプの方は合格しにくいと思います。このような素直でない人が合格しにくい理由は、まずは学習効率が悪くなる点です。予備校では合格に向けて考え出されたテキスト、講義を提供しております。それなのにその予備校を利用しながら、講師の指示に従わず、違う勉強方法をとってしまうことは、その予備校に通っている効果が減ってしまうのです。また、人の話を素直に聞かない人は、問題文を読むときもその傾向にあります。その結果、試験のときに問題の趣旨を履き違えて、出題者が求めている正解にたどりつけない危険があるのです。それに対して、素直な人は講師の指示や、自分が通っている予備校の方法に従うことで学習効率も上がりますし、何よりも本試験のときに問題文を素直に読むため、出題者が求めている解答にたどり着きやすいのです。
玉村 私も、長年、受講生を見てきて、「素直さって大切だな」と思っています。講義で聴いた内容を素直に理解し、素直に覚える。これが一番効率のいい学習だと思います。もちろん、いろいろ考えることは大切だと思います。法律を勉強しているのですから、「このような場合はどうなるか」とか、いろいろな事例が考えられます。それを、変に考えすぎて、わけのわからない方向へ行かないことです。考えることは大切ですが、それは、試験で解答を導くためのプロセスであれば重要ですが、行政書士試験合格という本質から外れてしまっては、それこそ時間の無駄だと思います。
受験生へのメッセージ
─── それでは、最後に、これから学習をスタートする方へのアドバイスをお願いいたします。
杉田 試験勉強はしんどいですが、法律をマスターしていくことで、世の中を法律的な目で捉えることができるようになってきますので、おもしろい部分もあります。一人でも多くの方にこの法律の面白さを実感していただければと考え、これから1年、教壇に立って講義を進めていきたいと思っております。楽しく、分かりやすい講義を行いますので、皆さん最後まで諦めず、合格へ向けて一緒に頑張っていきましょう。
玉村 行政書士の受験生の方は、いわゆる専業受験生ではなく、お仕事を持たれながら、育児・家事を行いながら、学業と並行しながら、受験勉強をされている方が多いと思います。何かと並行しながら、勉強されるのは本当に大変なことだと思います。だけど、挑戦するだけの価値がある資格だと思います。皆さんの学習が楽しくなるようにサポートしていきたいと思います。安心して学習のスタートを切ってください。
─── 本日は、貴重なお話を聞かせていただきまして、ありがとうございました。これで、対談を終了とさせていただきます。