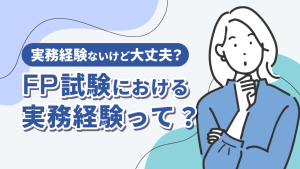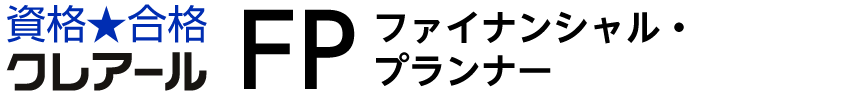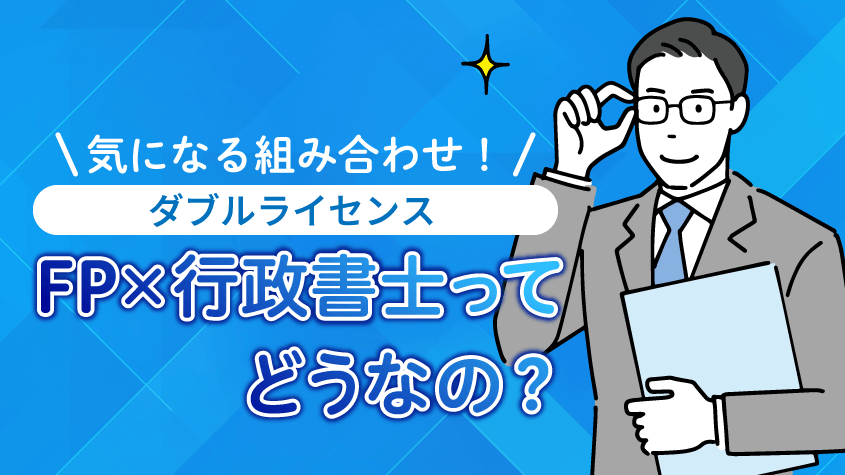行政書士とは
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格。
資格を取得すると、官公署へ提出する書類や権利関係に関する書類の作成・申請の代理、書類に関する相談を業務とし、報酬を得ることができます。
行政書士の主な業務は、次の3つです。
●書類作成業務
●手続きの申請代理業務
●相談業務
扱う書類は、国や地方公共団体などの官公署に提出する書類、内容証明や財務諸表など事実証明に関する書類、遺言書・師団所などの権利義務に関する書類など多岐に渡ります。
FPと行政書士の違い
行政書士は、法律を勉強して取得する資格です。
FPも法律の勉強はしますが、ファイナンシャルプランニングという大きな枠組のなかの1つとして、法律への対応があるというイメージです。
FP1級と行政書士の相性
FPと行政書士は、扱う範囲が幅広いため、重複する部分があります。
なかでも特に相性が良いのは、「相続」です。
行政書士として遺言や相続に関する相談を受けた場合、相続関係説明図や相続財産目録、遺産分割協議書の作成を行うなど、書類に関する手続きを代行することができます。
その際、FPとしての知識があれば、財産管理のコンサルティングや相続に関する相談、相続後のライフプランの提案等も行うことができます。
FPと行政書士 ダブルライセンスのメリット
前述した相続の手続き代行のほかに、FP業務が主である場合であっても、実際の書類の手続きを提供できるのは、相談者にとっても大きなメリットといえるでしょう。
また、行政書士として許認可をメイン業務とする場合には、顧客は事業主、経営者である場合が多くなります。
そのため、行政書士の手続きを入口として、資産運用やライフプランの提案、相続や年金に関する相談といった、FPコンサルティング業務でコンスタントな関わりを持つこともできるでしょう。
FPと行政書士の難易度の違い
難易度は、一般的にFP1級よりも行政書士の方が少し難しいとされています。一方で、FP1級には受験資格が必要で、その点を加味すると行政書士の難易度に匹敵するといった考え方もできます。
| 合格率 | 勉強時間 | |
|---|---|---|
| 行政書士 | 10%~15% | 約800時間~1000時間 (法律初学者・独学の場合) |
| FP3級 | 40%~80% | 約30~100時間(学科&筆記) |
| FP2級 | 20%~60% | 約150~300時間 |
| FP1級 | 7%~18% | 約450~600時間 |
まとめ
FP1級と行政書士のダブルライセンスがあると、いろいろなメリットがあります。
それぞれの資格だけでも独立開業して食べていける資格ですが、両方があれば仕事の幅も広がります。