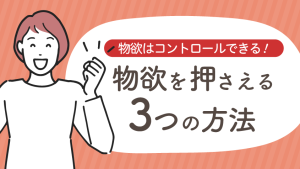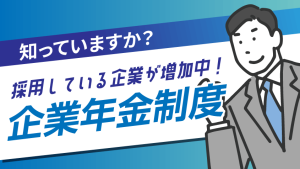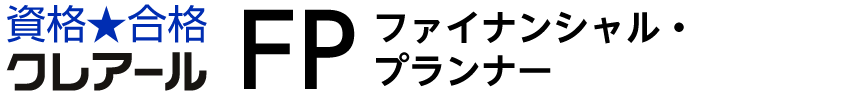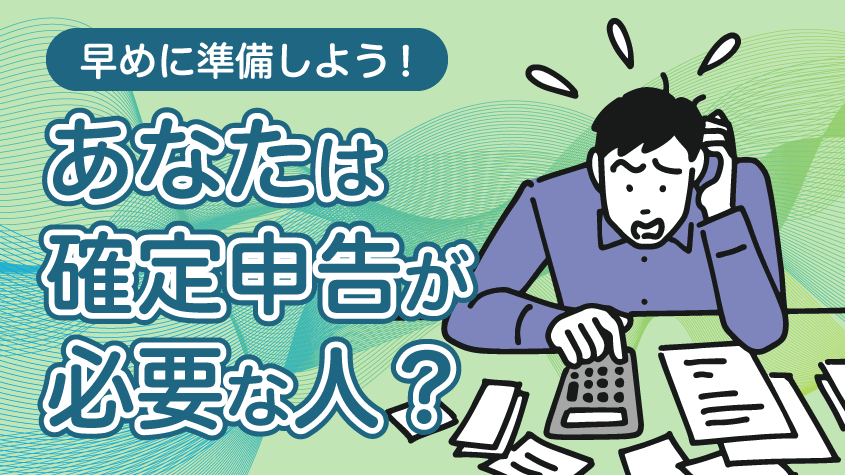2月から2024年の確定申告が開始されます。そもそも確定申告とは、何のために行うのでしょうか?
確定申告とは
納税者本人が、納付すべき所得税額を計算し、申告書の提出と納付を行うこと。
所得税は、原則として1月1日から12月31日までに生じた所得について所得税額を計算し、翌年2月16日から3月15日までに申告を行う必要があります。
給与所得者は、源泉徴収制度により原則として確定申告の必要はありませんが、下記の場合には確定申告が必要となります。
- 1か所から給与の支払いを受けている場合で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
- 複数の勤務先から給与の支払いを受け、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得を除く所得との合計所得金額が20万円を超える場合
- その年に支払いを受けた給与等の金額が2,000万円を超える場合
- 雑損控除・医療控除・寄付金控除の適用を受ける場合
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合(給与所得者については適用初年度のみ)
源泉徴収制度とは
給与等の支払者が、その支払時に所得税を徴収して納税者に代わって納付する制度。
給与所得者の場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整により年税額の清算が行われるため、所得税の確定申告をする必要はありません。
なお、利子所得(預貯金の利子)・配当所得(株式の配当)・退職所得・雑所得(国民年金や厚生年金)についても源泉徴収制度が採用されています。
確定申告により適用が可能な所得控除
医療費控除・雑損控除・寄付金控除(ふるさと納税についてのワンストップ特例制度を利用する場合を除く)について適用を受ける場合には、給与所得者で原則として確定申告をする必要がない人についても所得税の確定申告が必要。
準確定申告
確定申告をする必要がある人が死亡した場合に、その人の代わりに相続人が行う死亡した者に関する所得税の申告のこと。
その相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告書の提出と所得税の納付を行わなければなりません。
税額に誤りがあった場合
税額が不足している場合には正しい金額による修正申告を行う。
逆に、税額が過大(納めすぎ)となっている場合には、法定申告期限から5年以内に限り、その納めすぎとなっている税額の還付を請求する更正の請求を行うことができます。
まとめ
自分自身は確定申告が必要な人に当てはまっていましたか?
最近はふるさと納税を行っている人も増加しているので、ワンストップ特例制度利用者以外は、忘れずに申告しましょう!