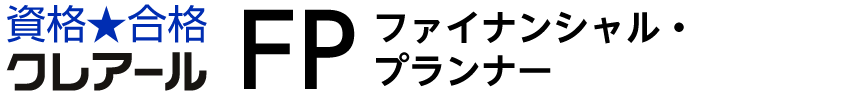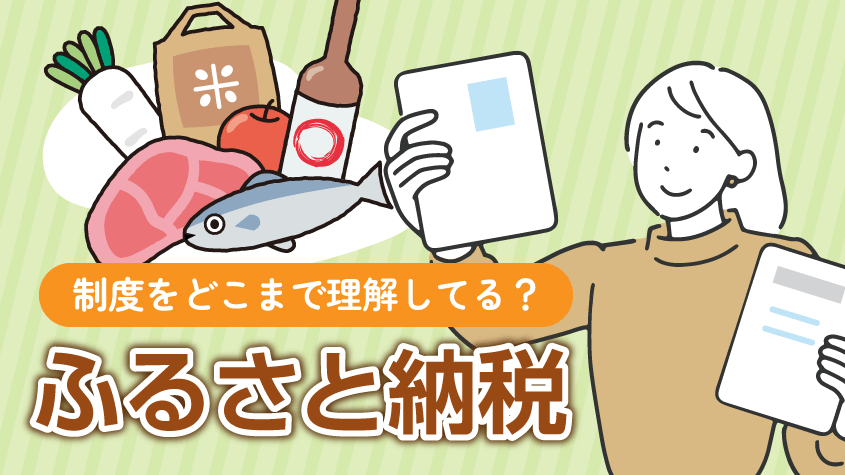年々利用者が増えているふるさと納税。
12月31日で2024年分の申込も締め切りとなりますが、制度についてどこまで知っていますか?
そもそも何のために作られた制度?
もともとは自分を育ててくれた「ふるさと」に自分の意志で納税できる制度があってもいいのでは!という問題提起から生まれた制度です。
税金を納めるの?
「納税」という言葉がついていますが、実際には都道府県や市区町村への「寄付」です。一般的に自治体に寄付した場合には「確定申告」を行うことで、その寄付金額の一部が所得税や住民税から控除されますが、ふるさと納税では原則として、自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となります。
自治体はどうやって選ぶの?
「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意志で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されましたが、実際には自分の故郷に限らず、どの自治体でも寄付をすることができるので、各自治体ホームページ等で公開している、ふるさと納税に対する考え方や、寄付金の使い道等を見て、応援したい自治体を選ぶといいでしょう。
確定申告が必要?
所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
なお、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、あらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」もあります。ただし、適用を受けられるのは自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
まとめ
最近は、豪華な返礼品の影響で、返礼品で寄付先の自治体を選ぶ人が多くなり、本来の目的からズレてきていることが指摘されています。本来の目的である「自分が生まれ育った自治体」「応援したい自治体」はどこでしょう?そこから寄付先を考えてみてはいかがでしょうか。
寄付金控除については、FPの学習カリキュラム
Chapter 4「タックスプランニング」で詳しく学びます
こちらの記事もおすすめです。